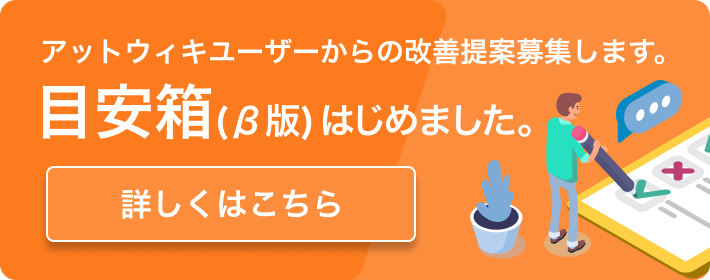▼ ▼ ▼
この世界は、間違っている。
僕たちは、喰べるしかない。
喰べる しか、喰べる しか、喰べる しか、喰べる しか。
ない。
僕たちは、喰べるしかない。
ない。
僕の救いは、微睡み揺蕩う夢。僕の救いは、ただ誰か を守ること。
僕の、救いは―――……
僕の、救いは―――……
▼ ▼ ▼
気が付けば、誰も周りにはいなかった。
僕一人だけが、そこに立っていた。
僕一人だけが、そこに立っていた。
燦々と照りつける初夏の陽射しが、草木や土を豊穣の色へと染め上げる。
緑、小麦色、茶。生命の息吹に溢れるそれは、全て命の色だ。
けれど、風がたなびく中で、僕の目に映るのは、赤。
一面にぶち撒けられた赤一色。既に失われてしまった命の色。
僕が喰らい奪った、ネギ・スプリングフィールドという少年の血。
緑、小麦色、茶。生命の息吹に溢れるそれは、全て命の色だ。
けれど、風がたなびく中で、僕の目に映るのは、赤。
一面にぶち撒けられた赤一色。既に失われてしまった命の色。
僕が喰らい奪った、ネギ・スプリングフィールドという少年の血。
「――――――」
何かが砕け散るような音が聞こえた。そんな気が、した。
そこからは何も覚えていない。
あれほど酷かった傷はいつの間にか治っていて、口の中は甘い血の味がした。
目的も曖昧に歩き続けた。胸に去来する悲哀を掻きだすように。
ただ歩いて、歩いて。どれだけの時間が経っただろう。
いつしか僕は、元の場所まで戻っていた。
学校、雑木林、裏山。逞しい銀の拳士と、嘲笑する風の道化師と戦ったあの場所へ。
僕がネギくんを守れなかった、あの場所へ。
あれほど酷かった傷はいつの間にか治っていて、口の中は甘い血の味がした。
目的も曖昧に歩き続けた。胸に去来する悲哀を掻きだすように。
ただ歩いて、歩いて。どれだけの時間が経っただろう。
いつしか僕は、元の場所まで戻っていた。
学校、雑木林、裏山。逞しい銀の拳士と、嘲笑する風の道化師と戦ったあの場所へ。
僕がネギくんを守れなかった、あの場所へ。
「僕は……」
何をしているのだろう。
守れなかった、救えなかった。敵の攻撃を易々と通し、あまつさえ自分の口で彼を貪り喰らった。
少し考えれば分かることだろう、如何に魔術師とはいえサーヴァントと比するまでもなく脆弱なマスターを前線に晒せばどうなるかくらい、簡単に。
一度成功したから味を占めたか? あの白銀のサーヴァントを、子供を傷つけず守り抜く強さを持つ彼を、ネギと協力して撃退したことで慢心していたのか。
何を馬鹿な。彼は自分たちより弱かったのではない、単にネギを傷つけないよう慮ってくれていただけだというのに。
よりにもよって敵の優しさに甘えて慢心したのか、なんて無様。
守れなかった、救えなかった。敵の攻撃を易々と通し、あまつさえ自分の口で彼を貪り喰らった。
少し考えれば分かることだろう、如何に魔術師とはいえサーヴァントと比するまでもなく脆弱なマスターを前線に晒せばどうなるかくらい、簡単に。
一度成功したから味を占めたか? あの白銀のサーヴァントを、子供を傷つけず守り抜く強さを持つ彼を、ネギと協力して撃退したことで慢心していたのか。
何を馬鹿な。彼は自分たちより弱かったのではない、単にネギを傷つけないよう慮ってくれていただけだというのに。
よりにもよって敵の優しさに甘えて慢心したのか、なんて無様。
(弱った状態で表は危険だ……早く、どこかへ……)
自責に歪む感情とは裏腹に、理性はひたすらに生存へ向けた行動を取り続ける。
この状態で交戦など以ての外、まずは傷を回復することに専念すべし。そのためにもまずは安全に隠れる場所を探す。それから、それから……
それから、僕はどうすればいいのだろう。
こうしている間にも、蓄えられた魔力はどんどん嵩を減らしていく。魔力運用など門外漢である故に、零れていく力を抑える術を何も持たない。そしてそれは傷を癒していく毎に加速度的に消費量を増やしていくのだ。
この状態で交戦など以ての外、まずは傷を回復することに専念すべし。そのためにもまずは安全に隠れる場所を探す。それから、それから……
それから、僕はどうすればいいのだろう。
こうしている間にも、蓄えられた魔力はどんどん嵩を減らしていく。魔力運用など門外漢である故に、零れていく力を抑える術を何も持たない。そしてそれは傷を癒していく毎に加速度的に消費量を増やしていくのだ。
マスターを失うということは、当然だがサーヴァントにとっては致命的な事態である。
サーヴァントの実体とは、霊核と呼ばれる存在の周囲を魔力で覆って疑似的な肉体とすることで形作っている。有体に言ってしまえば、サーヴァントの肉体とは魔力で構成された仮初のものなのだ。
物質として在る肉ではないから、当然魔力が消費されればその分霊核が消耗する。サーヴァントは現界だけで魔力を要する以上、魔力の供給源たるマスターがいなければ存在を保つことができない。
アーチャーのクラススキルである「単独行動」や、キャスターが扱うような魔力発生源さえあれば話は別だが……生憎、ランサーはそのようなものを持ち合わせてはいない。
現状の彼は、聖杯獲得のための長期的行動はおろか数戦すら危うい状況にある。令呪の補助、食人による魔力回復が合わさることで今は何とか体裁を保ててはいるが、体から抜け落ちていく活力が最早一刻の猶予もないのだということを如実に知らしめていた。
サーヴァントの実体とは、霊核と呼ばれる存在の周囲を魔力で覆って疑似的な肉体とすることで形作っている。有体に言ってしまえば、サーヴァントの肉体とは魔力で構成された仮初のものなのだ。
物質として在る肉ではないから、当然魔力が消費されればその分霊核が消耗する。サーヴァントは現界だけで魔力を要する以上、魔力の供給源たるマスターがいなければ存在を保つことができない。
アーチャーのクラススキルである「単独行動」や、キャスターが扱うような魔力発生源さえあれば話は別だが……生憎、ランサーはそのようなものを持ち合わせてはいない。
現状の彼は、聖杯獲得のための長期的行動はおろか数戦すら危うい状況にある。令呪の補助、食人による魔力回復が合わさることで今は何とか体裁を保ててはいるが、体から抜け落ちていく活力が最早一刻の猶予もないのだということを如実に知らしめていた。
ならば早急に新たなマスターを探さねばならないことになるが、それまではどうやって急場を凌げばいいのか。
簡単な話だ。そこらじゅうにあるではないか、手軽で美味そうな食料(魔力源)が―――
簡単な話だ。そこらじゅうにあるではないか、手軽で美味そうな食料(魔力源)が―――
「……ッ、駄目だ! 駄目だ! 僕は、僕はもう……」
一瞬でも浮かんでしまった考えを、頭を振って強く否定する。
ネギくんを食い殺して、その上で更に人を喰らうというのか。なんて愚想、吐き気がする。僕はそこまで堕ちたくない。
僕は人間だ。僕は人間だ。そうだ、僕は―――
ネギくんを食い殺して、その上で更に人を喰らうというのか。なんて愚想、吐き気がする。僕はそこまで堕ちたくない。
僕は人間だ。僕は人間だ。そうだ、僕は―――
「僕は……」
ただひたすらに歩き続けて、身を隠すように木々の中へと分け入って。つま先が木々の根っこに引っ掛かった。
踏みとどまろうとした膝が呆気なく崩れ、彼の体は地面の上に投げ出された。
どさり、という重い音。とっさに手をつくこともできず、顔から地面に突っ込む。土煙が口と鼻に入り込み、身を起こして荒く咳き込む。強かに打ち付けた体に痛みは無かった。
今までに何回転んだのかさえ、もう覚えてはいない。のろのろと立ち上がり、俯いたまま、足を引きずるようにして歩き出す。
四肢のどこにも、入れるべき力は残ってなどいなかった。放り出されてぶらりと揺れる両の腕が、酷く無力に思えた。
踏みとどまろうとした膝が呆気なく崩れ、彼の体は地面の上に投げ出された。
どさり、という重い音。とっさに手をつくこともできず、顔から地面に突っ込む。土煙が口と鼻に入り込み、身を起こして荒く咳き込む。強かに打ち付けた体に痛みは無かった。
今までに何回転んだのかさえ、もう覚えてはいない。のろのろと立ち上がり、俯いたまま、足を引きずるようにして歩き出す。
四肢のどこにも、入れるべき力は残ってなどいなかった。放り出されてぶらりと揺れる両の腕が、酷く無力に思えた。
歩いて、歩いて、歩いて。どこまで来たのかも分からぬまま、彼は力尽きるように倒れ伏した。糸の切れた人形のように、体が地面に投げ出される。
そこは開けた場所だった。木々がなぎ倒されたような痕があり、しかし動乱の音は消え去り静寂だけが満ちている。
そこは開けた場所だった。木々がなぎ倒されたような痕があり、しかし動乱の音は消え去り静寂だけが満ちている。
(ここなら……少しは時間が稼げるかもしれない)
思考する気力さえ、ほとんど残されてはいなかった。どうしようもなく、疲労感と無力感が全てを支配していた。
目の前の現実から逃げるように、意識を闇に手放そうとした、その時。
目の前の現実から逃げるように、意識を闇に手放そうとした、その時。
突如として、臓腑を突き刺されるような気配が辺りに充満して。
そして。
そして、それは現れた。
そして、それは現れた。
最初、それは中空に現れた黒い小さな球体であった。異様な気配に頭だけを引きずるように前へと向けて、金木はそれを目撃した。
影が渦巻くように模様の動作するそれは、数瞬の後に一気に人間大まで巨大化し周囲に暴風を発生させる。
木々が揺れる。葉が舞い踊る。吹きすさぶ音と共に、逆巻く空気が圧倒的な風圧を伴って体に叩きつけられ、霞む視界は無意識に暗闇に閉じられた。
瞑られた瞼を遅々として開けば、信じられないことに、そこには二つの人影があった。
影が渦巻くように模様の動作するそれは、数瞬の後に一気に人間大まで巨大化し周囲に暴風を発生させる。
木々が揺れる。葉が舞い踊る。吹きすさぶ音と共に、逆巻く空気が圧倒的な風圧を伴って体に叩きつけられ、霞む視界は無意識に暗闇に閉じられた。
瞑られた瞼を遅々として開けば、信じられないことに、そこには二つの人影があった。
一人は少女だ。小学生か中学生か、白いセーラー服を纏った銀髪の少女。見覚えはない。泣きそうな顔を隠すことなく、ただ絶望に打ちひしがれるように地に伏せている。
そして、もう一人は―――
そして、もう一人は―――
「……トーカ、ちゃん?」
見覚えのある姿だった。見覚えのある顔だった。
それは何よりも守りたかった人だった。帰るべき場所で、平穏に過ごしていて欲しかった人だった。
いいや、人ではない、人を食い殺す喰種だった。
それは何よりも守りたかった人だった。帰るべき場所で、平穏に過ごしていて欲しかった人だった。
いいや、人ではない、人を食い殺す喰種だった。
―――なんで、そんなんなっちゃったのよ……
かつての記憶にある姿、彼女の問いかける声が聞こえる。
答えられない。
答えられない。
答えは出ず、話す機会は当の昔に失ったはずだった。
答えられない。
答えられない。
答えは出ず、話す機会は当の昔に失ったはずだった。
自分でもよく分からない何かが、胸に去来した。
▼ ▼ ▼
あらゆる尊厳をマイナスにされ、それでも私たちはこうして生きている。
戦い、勝ち取り、願いを叶えるために。例え絶望の淵に落とされようとも未だ終わりは訪れない。
戦い、勝ち取り、願いを叶えるために。例え絶望の淵に落とされようとも未だ終わりは訪れない。
ああ、なんて滑稽な道化芝居だろう。
奪われた後でいくら力だけが戻っても、何の意味もないだろうに。
奪われた後でいくら力だけが戻っても、何の意味もないだろうに。
▼ ▼ ▼
「ガァ、ァッ!?」
剣呑に覗く砲塔から放たれる規格外の砲弾が、金木の肉体ごと空間を抉りながら背後の地面を爆散させる。
地に穿たれた爆痕は蜂の巣と形容することすら躊躇われるほどに巨大かつ凄惨で、それを成した魔弾の砲撃が見た目通りの華奢な豆鉄砲などではないのだということをこれ以上なく示していた。
体の末端をいくつも削られながら、しかし錐揉み回転を余儀なくされる金木は中空にて身を捻ると音もなく着地、瞬間予備動作もなく地を蹴り跳躍。魔弾の主たる少女の顔に照準を合わせ、一息に拳を叩き込もうとするも。
地に穿たれた爆痕は蜂の巣と形容することすら躊躇われるほどに巨大かつ凄惨で、それを成した魔弾の砲撃が見た目通りの華奢な豆鉄砲などではないのだということをこれ以上なく示していた。
体の末端をいくつも削られながら、しかし錐揉み回転を余儀なくされる金木は中空にて身を捻ると音もなく着地、瞬間予備動作もなく地を蹴り跳躍。魔弾の主たる少女の顔に照準を合わせ、一息に拳を叩き込もうとするも。
「――――!!」
最早言葉にならない叫びを悲壮な形相に木霊させながら、弓兵の少女は疾走上へと左手とその表面に具現させた単装機銃を差し向ける。次々と火を噴く銃口、放たれる弾丸は大気の壁を容易く破壊し金木の体を撃ち貫く。
7.7mm機銃。威力は最小ながら、故に連射性を確保した銃撃は金木を窮鼠の如く追い詰める。のみならず、それら弾丸はガードした金木の手足に深く食い込み、それ以上の前進を阻むと同時に少なくない傷を秒間ごとに与えていく。
しかしそれでも彼は動きを止めることはない。四足獣に近い前斜体勢を維持したまま側方へと跳躍、そのまま少女の周りを回るように円形上に疾走する。一筋の颶風となって駆ける金木の足跡をなぞるように一瞬遅れて少女の銃弾が地を抉り、僅かではあるが照準を標的たる金木に追い縋ることができなくなる。
そして、その隙を逃す金木ではない。自身の背後から瞬時に四本の赫子を顕現、螺旋を描いて跳ね上がった漆黒の一閃が、少女の喉元めがけて突きこまれた。
けれど討ち取るには至らない。少女は地に足を固定された木偶の坊では断じてなく、故に後方へ跳躍すると赫子の射程外へと瞬時に退避。一歩の跳躍で十mの距離を稼ぎ、体勢を立て直した瞬間には既に右手の砲塔が金木に狙いをつけている。
三連装の長大な砲口が漆黒の内部を晒して死の重圧を叩き付ける。25mm三連装機銃、対戦車砲をルーツとするこの機銃は最早対人に向ける域を遥か超越し、未だ中空にある少女を狙い撃とうと近接する金木を真正面から迎え撃つ。
鼓膜が劈けるような轟音が空間自体を震撼させる。金木が移動する先を、障害物たる木々を重ねて五本紙屑同然に引き裂いて、彼方よりの砲撃は確かに届いた。
7.7mm機銃。威力は最小ながら、故に連射性を確保した銃撃は金木を窮鼠の如く追い詰める。のみならず、それら弾丸はガードした金木の手足に深く食い込み、それ以上の前進を阻むと同時に少なくない傷を秒間ごとに与えていく。
しかしそれでも彼は動きを止めることはない。四足獣に近い前斜体勢を維持したまま側方へと跳躍、そのまま少女の周りを回るように円形上に疾走する。一筋の颶風となって駆ける金木の足跡をなぞるように一瞬遅れて少女の銃弾が地を抉り、僅かではあるが照準を標的たる金木に追い縋ることができなくなる。
そして、その隙を逃す金木ではない。自身の背後から瞬時に四本の赫子を顕現、螺旋を描いて跳ね上がった漆黒の一閃が、少女の喉元めがけて突きこまれた。
けれど討ち取るには至らない。少女は地に足を固定された木偶の坊では断じてなく、故に後方へ跳躍すると赫子の射程外へと瞬時に退避。一歩の跳躍で十mの距離を稼ぎ、体勢を立て直した瞬間には既に右手の砲塔が金木に狙いをつけている。
三連装の長大な砲口が漆黒の内部を晒して死の重圧を叩き付ける。25mm三連装機銃、対戦車砲をルーツとするこの機銃は最早対人に向ける域を遥か超越し、未だ中空にある少女を狙い撃とうと近接する金木を真正面から迎え撃つ。
鼓膜が劈けるような轟音が空間自体を震撼させる。金木が移動する先を、障害物たる木々を重ねて五本紙屑同然に引き裂いて、彼方よりの砲撃は確かに届いた。
「ぐ、ぅあッ!」
致死の銃火に晒された金木に取れる選択肢は回避の一択。大きく身を仰け反らせると同時に上体と紙一重の位置を砲弾が通り過ぎていく。それを後ろ目に確認する暇もなく赫子を前方に突きだしつつ後方へ跳躍、苦し紛れの一撃は少女に届くはずもなく、間髪入れずに放たれる機銃の掃射を木々を利用した多角移動でなんとかやり過ごす。
一進一退の攻防劇、息を吐かせぬ死の舞踏。何故こんなことになったのかと問われれば、少なくとも金木の側は一切説明することができなかった。
突如として目の前に浮かび上がった黒球と、その中から現れた二人の少女。その片割れはよく見知った知己のもので、故に金木には一切の敵意はなく戦闘行為を仕掛けることは無かった。
だがそれは相手側の譲歩を引き出すものとイコールではない。金木の存在を確認した少女―――恐らくはアーチャーか―――は間髪入れることなく砲撃、その後一切の手心なく金木を殺さんと攻撃を仕掛けている。
掛ける言葉もないとはこのことだ。元より説得など選択肢に入れていないとはいえ、襲いくる少女は最早言葉も通じぬと言わんばかりの狂乱ぶりを露呈している。それは純粋な殺意というよりも、何か別の意思によって突き動かされているような違和感すら感じられて、それ故に攻撃の一つ一つには一切の躊躇が見られない。
突如として目の前に浮かび上がった黒球と、その中から現れた二人の少女。その片割れはよく見知った知己のもので、故に金木には一切の敵意はなく戦闘行為を仕掛けることは無かった。
だがそれは相手側の譲歩を引き出すものとイコールではない。金木の存在を確認した少女―――恐らくはアーチャーか―――は間髪入れることなく砲撃、その後一切の手心なく金木を殺さんと攻撃を仕掛けている。
掛ける言葉もないとはこのことだ。元より説得など選択肢に入れていないとはいえ、襲いくる少女は最早言葉も通じぬと言わんばかりの狂乱ぶりを露呈している。それは純粋な殺意というよりも、何か別の意思によって突き動かされているような違和感すら感じられて、それ故に攻撃の一つ一つには一切の躊躇が見られない。
これはまずい状況だと、金木は一人そう思考する。現状、彼らが互角の戦いを演じていられるのは複数の要因が存在するからだが、故に無駄な時間を浪費することだけは避けねばならないということを金木は誰よりも身を以て知っている。
彼らが拮抗状態にある理由の一つは、言うまでもなくアーチャーの狂乱だ。バーサーカーの如く狂化でも付与されたのかと疑いたくなるような猛攻は、しかし一切加減がない代わりに著しく精彩さを欠いていた。
常ならば決してこのようなことはないであろう、積み上げられた修練は一挙一刀足から如実に感じられる。しかし流麗なその技量を、今の彼女は完全に失っているのだ。それは糸で無理やりに動かされるマリオネットのような有様が原因であることは、一目で理解できる。
そして二つ目に、今の金木の状態が挙げられる。
本来、マスターを失った彼は即座に消滅するか、そうでなくとも著しい弱体化は免れない状態であるはずだ。拮抗どころか、本当ならば戦闘行為それ自体が不可能であるはずの彼が、一体どうしてこの激烈な闘争を演じることができているのか。
それは二画に相当する令呪と、マスターたるネギを喰らったことによる喰種スキルの最大活性化が挙げられる。
令呪とは、仮に一画であろうとも命じる内容如何によれば時空間すら捻じ曲げる規格外の魔力塊である。それを二画に加え、人肉を食したことによる全身の活性化が合わさることにより、彼は単独行動スキルを持ち合わせない身でありながらも一時的に十全にも等しい戦闘能力を発揮しているのだ。
彼らが拮抗状態にある理由の一つは、言うまでもなくアーチャーの狂乱だ。バーサーカーの如く狂化でも付与されたのかと疑いたくなるような猛攻は、しかし一切加減がない代わりに著しく精彩さを欠いていた。
常ならば決してこのようなことはないであろう、積み上げられた修練は一挙一刀足から如実に感じられる。しかし流麗なその技量を、今の彼女は完全に失っているのだ。それは糸で無理やりに動かされるマリオネットのような有様が原因であることは、一目で理解できる。
そして二つ目に、今の金木の状態が挙げられる。
本来、マスターを失った彼は即座に消滅するか、そうでなくとも著しい弱体化は免れない状態であるはずだ。拮抗どころか、本当ならば戦闘行為それ自体が不可能であるはずの彼が、一体どうしてこの激烈な闘争を演じることができているのか。
それは二画に相当する令呪と、マスターたるネギを喰らったことによる喰種スキルの最大活性化が挙げられる。
令呪とは、仮に一画であろうとも命じる内容如何によれば時空間すら捻じ曲げる規格外の魔力塊である。それを二画に加え、人肉を食したことによる全身の活性化が合わさることにより、彼は単独行動スキルを持ち合わせない身でありながらも一時的に十全にも等しい戦闘能力を発揮しているのだ。
だが、それはあくまで短時間に限定されたことである。疾走する脚部、展開する赫子、修復される損傷。それらが戦闘に際し最大出力で稼働される毎に、身に秘めた魔力は栓が抜かれたように急速に失われていくのだ。
現界に必要な魔力を削り、戦闘に充てることで何とか見せかけの拮抗状態を作っているに過ぎない。ネギが繋いでくれた命の時間、文字通り魂を削って、今の金木は戦っているのだ。
だからこそ、今は一分一秒でも時間が惜しい。早急にこの戦いを終わらせる必要があるし、しかし同時に彼はこの場を離脱することを一切考えていなかった。
単純な理屈だ。仮にこの場を切り抜けたとて、果たしてその後はどうする?
新たなマスターを探す―――都合よくサーヴァントだけを失ったマスター候補が運よく現れることを祈って?
他のサーヴァントを倒し契約を強制する―――たかが一戦闘にこれだけ消耗してしまう自分にそんなことが果たして可能か?
否、否だ。そんなのは可能性が低すぎる。自分は何としても聖杯を獲らなければならないのだから、取るべき道は何時だって現実的に考えなければならない。
そして彼が考えたのは―――今この場でアーチャーを打倒し、他ならぬ霧嶋董香と契約を結ぶことだった。
自分と彼女ならば有する願いは同じであろう、故に同調し主従契約を結ぶこともまた可能であると考えて。
現界に必要な魔力を削り、戦闘に充てることで何とか見せかけの拮抗状態を作っているに過ぎない。ネギが繋いでくれた命の時間、文字通り魂を削って、今の金木は戦っているのだ。
だからこそ、今は一分一秒でも時間が惜しい。早急にこの戦いを終わらせる必要があるし、しかし同時に彼はこの場を離脱することを一切考えていなかった。
単純な理屈だ。仮にこの場を切り抜けたとて、果たしてその後はどうする?
新たなマスターを探す―――都合よくサーヴァントだけを失ったマスター候補が運よく現れることを祈って?
他のサーヴァントを倒し契約を強制する―――たかが一戦闘にこれだけ消耗してしまう自分にそんなことが果たして可能か?
否、否だ。そんなのは可能性が低すぎる。自分は何としても聖杯を獲らなければならないのだから、取るべき道は何時だって現実的に考えなければならない。
そして彼が考えたのは―――今この場でアーチャーを打倒し、他ならぬ霧嶋董香と契約を結ぶことだった。
自分と彼女ならば有する願いは同じであろう、故に同調し主従契約を結ぶこともまた可能であると考えて。
―――ああ全く、僕って奴は。
命を懸けた修羅場であるというのに、何故だか自嘲の念が浮かび上がった。
トーカが自分を見捨てないだろうという醜い打算、そのために彼女のサーヴァントを消し去ろうという欺瞞。そんなどうしようもない選択しかできないか弱い自分への不信。
全く反吐が出る。結局のところ、自分はとっくの昔に汚れきってしまったのだろう。
ああ、それでも。聖杯を獲得し失ってしまった彼らを取り戻すために、終ぞ守れなかった主とその知己を助けるために。自分は負けることが許されない。
トーカが自分を見捨てないだろうという醜い打算、そのために彼女のサーヴァントを消し去ろうという欺瞞。そんなどうしようもない選択しかできないか弱い自分への不信。
全く反吐が出る。結局のところ、自分はとっくの昔に汚れきってしまったのだろう。
ああ、それでも。聖杯を獲得し失ってしまった彼らを取り戻すために、終ぞ守れなかった主とその知己を助けるために。自分は負けることが許されない。
「だから」
お前は。
「ここで、倒れろ」
瞬間、金木は四の赫子を限界まで伸ばし前方で交差、放たれる機銃掃射の全てを赫子で弾きながら一気に跳躍する。
暴風のように吹き荒れる弾丸の嵐を無理やりに突っ切って秒とかからぬ間に接近。少女の懐まで入り込むと、編まれた赫子の隙を縫って握った拳を一心に突き上げる。
その標的は少女の心臓部。遠距離射撃を主とする少女に迎撃の手段はなく、仮に機銃の掃射を受けようが頑強なるこの身は数瞬は耐えてくれるはずだ。
故に勝算は十分。この一撃が決まれば勝負は自分の勝ちで決まる―――
暴風のように吹き荒れる弾丸の嵐を無理やりに突っ切って秒とかからぬ間に接近。少女の懐まで入り込むと、編まれた赫子の隙を縫って握った拳を一心に突き上げる。
その標的は少女の心臓部。遠距離射撃を主とする少女に迎撃の手段はなく、仮に機銃の掃射を受けようが頑強なるこの身は数瞬は耐えてくれるはずだ。
故に勝算は十分。この一撃が決まれば勝負は自分の勝ちで決まる―――
「……甘いよ」
はずだった。
拳が少女に突き入れられるより早く、背後に隠されていた少女の右手が舞うように持ち上げられる。
そこにあったのは、今までの機銃とは全く別の砲塔。無機の大筒が吐き出すは爆撃の一矢。
これまで以上に巨大な口径が撃ち出すのは単なる銃弾に非ず、それはまさしく主力火砲。
12.7cm連装砲B型改二。今までの対空機銃などとは文字通り桁が違う、駆逐艦ヴェールヌイが誇る最大の火力がここに顕現する。
そこにあったのは、今までの機銃とは全く別の砲塔。無機の大筒が吐き出すは爆撃の一矢。
これまで以上に巨大な口径が撃ち出すのは単なる銃弾に非ず、それはまさしく主力火砲。
12.7cm連装砲B型改二。今までの対空機銃などとは文字通り桁が違う、駆逐艦ヴェールヌイが誇る最大の火力がここに顕現する。
「―――――ッ!!」
轟音。爆発。炎上。湧き上がる爆炎に呑まれ、金木の体は弾かれるように遥か後方へと吹き飛ばされた。
二度、三度、地面にバウンドしながら転がり、木にぶつかることでようやく動きが静止する。その体は、見るも無残なものと化していた。
全身が黒く焼け焦げていた。特に着弾点である腹部は完全に崩壊しており、内腑までもが焼け付いている有り様だ。当然周囲は見事なまでに炭化しており、蒸発したのか一滴の流血さえ起きていない。
瀕死であった。例えサーヴァントであれ、例え喰種であれ、例え双方の性質を備える彼であろうとも、これ以上は戦闘どころか存命すら危うい状態である。
けれど彼の肉体は依然として生存への最適解を求め駆動する。穿たれた穴から肉の芽のようなものが次々と生え、損傷を埋めるように嵩を増していく。
それは目に見えるほどの驚異的なスピードで為される再生活動ではあったが……しかし、今この場においてはどうしようもなく遅かった。既に金木の傍にはヴェールヌイが立ち、手に携える砲塔を彼の頭蓋に押し当てている。
詰みである。マスターを失い、仲間もおらず、令呪の補助すら望めない彼に、この状況を打開する方策は何一つとして存在しない。
二度、三度、地面にバウンドしながら転がり、木にぶつかることでようやく動きが静止する。その体は、見るも無残なものと化していた。
全身が黒く焼け焦げていた。特に着弾点である腹部は完全に崩壊しており、内腑までもが焼け付いている有り様だ。当然周囲は見事なまでに炭化しており、蒸発したのか一滴の流血さえ起きていない。
瀕死であった。例えサーヴァントであれ、例え喰種であれ、例え双方の性質を備える彼であろうとも、これ以上は戦闘どころか存命すら危うい状態である。
けれど彼の肉体は依然として生存への最適解を求め駆動する。穿たれた穴から肉の芽のようなものが次々と生え、損傷を埋めるように嵩を増していく。
それは目に見えるほどの驚異的なスピードで為される再生活動ではあったが……しかし、今この場においてはどうしようもなく遅かった。既に金木の傍にはヴェールヌイが立ち、手に携える砲塔を彼の頭蓋に押し当てている。
詰みである。マスターを失い、仲間もおらず、令呪の補助すら望めない彼に、この状況を打開する方策は何一つとして存在しない。
「許しは乞わないよ。ただ、そちらと同じように私も負けるわけにはいかないんだ。
そう、これ以上は、二度と負けてたまるもんか」
そう、これ以上は、二度と負けてたまるもんか」
掠れる視界に、少女の話す姿が見える。ああ、自分は敗れてしまったのかと、ここに至りようやく彼は実感することができた。
何故、負けてしまったのか。負けられないと強く願った自分は。
単純な話だ。敗北が許されないのは、何も彼に限った話ではないというだけのこと。
いいや、そもそも負けを認められる者などこの街のどこにもいないのだ。誰もが己が命を懸け、誰もが願いを胸に聖杯へと手を伸ばす。理由は様々あろうが、そこに託す祈りの重さは誰もが変わらないというのに。
何を驕っていたのだろう。無意識に自分を特別とでも考えていたのか。主を死なせてしまった自分の不幸に酔っていたのか。次々と湧き上がる負の想念は、しかし現実の脅威を取り除くことはない。
何故、負けてしまったのか。負けられないと強く願った自分は。
単純な話だ。敗北が許されないのは、何も彼に限った話ではないというだけのこと。
いいや、そもそも負けを認められる者などこの街のどこにもいないのだ。誰もが己が命を懸け、誰もが願いを胸に聖杯へと手を伸ばす。理由は様々あろうが、そこに託す祈りの重さは誰もが変わらないというのに。
何を驕っていたのだろう。無意識に自分を特別とでも考えていたのか。主を死なせてしまった自分の不幸に酔っていたのか。次々と湧き上がる負の想念は、しかし現実の脅威を取り除くことはない。
向けられた砲塔に、魔力が収束していくのが感じられる。これで死ぬのか、僕は。こんなところで、何を為すこともできないまま。
嫌だ、嫌だ、僕は戦わなければ。
もっと、もっと、もっと。
ネギくんの願いを叶えてあんていくのみんなを助けてトーカちゃんが傷つくことのないような。
そんな未来を手にするために、僕は。
嫌だ、嫌だ、僕は戦わなければ。
もっと、もっと、もっと。
ネギくんの願いを叶えてあんていくのみんなを助けてトーカちゃんが傷つくことのないような。
そんな未来を手にするために、僕は。
「僕は―――!」
戦わなくては、ならない。
――――――――――――。
▼ ▼ ▼
彼は独りで戦おうとした者。彼女は平穏な孤独を強いられた者。
泥の中で懸命に足掻き、光り輝く明日を求めて手を伸ばし続けた者。
そのどちらもが誰かの不幸など微塵も願わず、しかし互いの道は分かたれた。
現実と幻想、相容れぬ双極に立たされた彼らの再会は、けれど何をも生み出すことはない。
地獄へと続く道は善意という名の敷石で舗装されている。
彼らはただ、悪戯に失っていくだけだ。
泥の中で懸命に足掻き、光り輝く明日を求めて手を伸ばし続けた者。
そのどちらもが誰かの不幸など微塵も願わず、しかし互いの道は分かたれた。
現実と幻想、相容れぬ双極に立たされた彼らの再会は、けれど何をも生み出すことはない。
地獄へと続く道は善意という名の敷石で舗装されている。
彼らはただ、悪戯に失っていくだけだ。
▼ ▼ ▼
まず最初に感じたのは痛みだった。
高熱はあまりにも隙なく全身を包み込んで、当初それが痛みだということにさえ気付けなかった。
沈んだ意識が暗闇から引き上げられる感触と共に、視界の中に眩しいくらいの空白が広がる。
一部の隙もない白が、酸欠で鈍っていた脳髄が回復していくのと合わせるように色を取り戻していき、同時に耐えがたいほどの苦痛が全身を襲う。
痛い、痛い、痛い。浮かんでくるのはそればかり。自分が一体何者で、直前まで何をしていて、その先に何を望んでいたのかさえ、今の彼女には遠い彼岸の記憶でしかなかった。
辛さから逃れようと手を伸ばして、けれど自分に手がついてないことを思いだした。
全身の痛みに駆け出そうとして、けれど足は骨がむき出しになっていることを思いだした。
他の人に助けを求めようとして、けれど自分が人間でないということを、そこでようやく思い出した。
高熱はあまりにも隙なく全身を包み込んで、当初それが痛みだということにさえ気付けなかった。
沈んだ意識が暗闇から引き上げられる感触と共に、視界の中に眩しいくらいの空白が広がる。
一部の隙もない白が、酸欠で鈍っていた脳髄が回復していくのと合わせるように色を取り戻していき、同時に耐えがたいほどの苦痛が全身を襲う。
痛い、痛い、痛い。浮かんでくるのはそればかり。自分が一体何者で、直前まで何をしていて、その先に何を望んでいたのかさえ、今の彼女には遠い彼岸の記憶でしかなかった。
辛さから逃れようと手を伸ばして、けれど自分に手がついてないことを思いだした。
全身の痛みに駆け出そうとして、けれど足は骨がむき出しになっていることを思いだした。
他の人に助けを求めようとして、けれど自分が人間でないということを、そこでようやく思い出した。
「ぅ……ぁ……」
視界がぼやける。酷い耳鳴りがする。血が足りないせいで頭は靄がかかったみたいだ。
体がものすごく熱くなって、冷たくなって、震えが止まらなくなって、動かせなくなって、感覚が無くなって。ぽろぽろ、ぽろぽろ、崩れるように流れて行った。
私の体はどうなっているんだろう。怖くなって、碌に見えてもいないくせに目を逸らす。眼球を動かす。ただそれだけのことが億劫で、ひどく吐き気がする。
体がものすごく熱くなって、冷たくなって、震えが止まらなくなって、動かせなくなって、感覚が無くなって。ぽろぽろ、ぽろぽろ、崩れるように流れて行った。
私の体はどうなっているんだろう。怖くなって、碌に見えてもいないくせに目を逸らす。眼球を動かす。ただそれだけのことが億劫で、ひどく吐き気がする。
ここはどこなんだろう。私は何をしていたんだっけ。アーチャー……アーチャー? それって誰、どこにいるの?
蘇る記憶、白色の。そうだ、確か白い髪をしていた。いつも無理やりに笑っていて、必要もないのにボロボロになって、誰かを助けようとするくせに自分のことはほったらかしで……
あれ、違う。それはアーチャーじゃない。アーチャーでは、ない。
今はもう懐かしい記憶。そこに映ってるのは、忘れようもない―――
蘇る記憶、白色の。そうだ、確か白い髪をしていた。いつも無理やりに笑っていて、必要もないのにボロボロになって、誰かを助けようとするくせに自分のことはほったらかしで……
あれ、違う。それはアーチャーじゃない。アーチャーでは、ない。
今はもう懐かしい記憶。そこに映ってるのは、忘れようもない―――
「カネ……キ?」
そして。
そして、私は見た。
視界の向こう側、腫れ上がって碌に開かない瞼の隙間から垣間見える光の中、白髪の彼の姿があるのを。
私は、確かに見たのだ。
そして、私は見た。
視界の向こう側、腫れ上がって碌に開かない瞼の隙間から垣間見える光の中、白髪の彼の姿があるのを。
私は、確かに見たのだ。
心臓が止まるような、そんな思いをした。
彼がそこにいた。木の根元に背を預けて、その白と黒の瞳でこちらを見ていた。そんな気が、した。
とても傷ついたような、今にも泣きだしそうな顔をしていた。
やっぱりここでも、前と変わらないんだな、と。なんだか寂しいような、悲しいような、そんな感情を抱いた。
彼がそこにいた。木の根元に背を預けて、その白と黒の瞳でこちらを見ていた。そんな気が、した。
とても傷ついたような、今にも泣きだしそうな顔をしていた。
やっぱりここでも、前と変わらないんだな、と。なんだか寂しいような、悲しいような、そんな感情を抱いた。
彼は、私に負けず劣らず酷い格好をしていた。辛うじて残っている手足はどれもボロボロで、ところどころ白い骨が覗いていた。鳩尾を中心にお腹が大きく抉れて、周りはみんな真っ黒焦げ。顔なんて飛び散った血や肉で汚れていて、これじゃお店に立てないじゃないなんて、そんな場違いなことを考えた。
ああでも、お店に戻るんだったら怪我もそうだけど、まず髪の色をどうにかしなきゃね。
そんなんで店に立たれても、目立ってしょうがないし。
だから、ね。
そんなんで店に立たれても、目立ってしょうがないし。
だから、ね。
「一緒に……」
そう、口にしようとして。
飛び込んできたのは、彼に砲塔を向ける少女の姿。
飛び込んできたのは、彼に砲塔を向ける少女の姿。
「―――え?」
何が起こっているのか、一瞬分からなかった。
何故そんなことをしているのか、何故そんなことになっているのか。
一瞬だが、まるで見当がつかなくて。
何故そんなことをしているのか、何故そんなことになっているのか。
一瞬だが、まるで見当がつかなくて。
「あ……」
思い出した。
蹂躙の記憶。脳裏にこびり付いた"赤"。為す術もなく、ただ奪われていくだけだった一幕のこと。
そうだ、私はあの時、二つの令呪を使っていた。
それは"赤"を傷つけないこと、そして……
そして、彼ら以外の全員を殺すということ。
蹂躙の記憶。脳裏にこびり付いた"赤"。為す術もなく、ただ奪われていくだけだった一幕のこと。
そうだ、私はあの時、二つの令呪を使っていた。
それは"赤"を傷つけないこと、そして……
そして、彼ら以外の全員を殺すということ。
それは、あのどうしようもないバカだって、例外なんかじゃなくて。
「駄目……」
駄目、駄目だ。
そんなことは、認められない。
そんなことは、認められない。
「駄目……やめろ、アーチャー……やめて……」
私は、失いたくなかったからここまで来た。
二度と、独りにはなりたくなかった。
もう勝手にいなくなられるのは、嫌だった。
二度と、独りにはなりたくなかった。
もう勝手にいなくなられるのは、嫌だった。
だから。
「やめろ……」
にわかに、右腕の一箇所から赤い光が湧き出てくる。
それは、彼女に残された最後の令呪。
彼女を此処に繋ぎとめる、最後の楔、だった。
それは、彼女に残された最後の令呪。
彼女を此処に繋ぎとめる、最後の楔、だった。
「やめろ……」
喉が掠れる。上手く、声が出せない。
だが、手を伸ばす。潰され形を失った、けれどまだ動く手を、前に。
前に、伸ばす。
だが、手を伸ばす。潰され形を失った、けれどまだ動く手を、前に。
前に、伸ばす。
「やめろ、アーチャー!」
そして。
令呪が最後の輝きを、放って。
令呪が最後の輝きを、放って。
誰もが、動きを止めた。
金木研も、霧嶋董香も、ヴェールヌイでさえも、例外ではなかった。
動く者は、誰一人としていなかった。
金木研も、霧嶋董香も、ヴェールヌイでさえも、例外ではなかった。
動く者は、誰一人としていなかった。
意図せぬ大声を出して肩で息をするトーカは、驚いた様子でこちらを見遣る二人の視線に、ここに至ってようやく気付いた。
カネキもヴェールヌイも、揃ってこちらを見ていた。一瞬後に鳴り響くはずだった砲の轟声は起こらない。
自分が何をしたのか、トーカは正しく理解していなかった。やめろと叫んだのも、止めて欲しいと願ったのも、単なる必死の懇願だ。
けれど、聖杯の恩寵はそれを聞き届けた。
聞き届けて、しまった。
カネキもヴェールヌイも、揃ってこちらを見ていた。一瞬後に鳴り響くはずだった砲の轟声は起こらない。
自分が何をしたのか、トーカは正しく理解していなかった。やめろと叫んだのも、止めて欲しいと願ったのも、単なる必死の懇願だ。
けれど、聖杯の恩寵はそれを聞き届けた。
聞き届けて、しまった。
ヴェールヌイが何かを叫んでこちらへと駆け寄ってくる。必死の顔で、泣きそうな顔で、懸命に口と足を動かしているけれど。
何故だか声は聞こえず、その動きも酷くゆっくりに感じられた。
何故だか声は聞こえず、その動きも酷くゆっくりに感じられた。
ふと、カネキのほうを見た。
一人にしないと誓ってくれた彼は、けれど驚くばかりで動くことはなかった。
一人にしないと誓ってくれた彼は、けれど驚くばかりで動くことはなかった。
ヴェールヌイが、駆け寄りながら手を伸ばした。
何かを必死に掴むように、何かを失わせないように。
座り込むトーカのほうへ、ただ懸命に手を伸ばして。
未だ中途半端に伸ばしたままの、トーカの右手を掴もうとして。
何かを必死に掴むように、何かを失わせないように。
座り込むトーカのほうへ、ただ懸命に手を伸ばして。
未だ中途半端に伸ばしたままの、トーカの右手を掴もうとして。
だから、私は。
何かを、彼女に伝えようと―――
口を、開いて―――
何かを、彼女に伝えようと―――
口を、開いて―――
「―――――――――」
―――そこで、姿は掻き消えた。
―――最初から何も存在していなかったように、少女の姿はどこにもなかった。
―――最初から何も存在していなかったように、少女の姿はどこにもなかった。
ぶわりと風が包み込むように、大きな鳥が羽ばたいたように、吹き上がる風が木々の葉をざあざあと揺らした。
人がいた痕跡など何処にもなかった。そこにはただ、自然の生み出す静寂だけが満ちていた。
人がいた痕跡など何処にもなかった。そこにはただ、自然の生み出す静寂だけが満ちていた。
ヴェールヌイの指は、ただ空を切るばかりで。
その手は何も、掴むことはなかった。
その手は何も、掴むことはなかった。
▼ ▼ ▼
「どういうことだ、これはッ!」
その声に、意識はようやく現実へと帰還した。
見遣ればそこには、胸倉を掴んで血を吐きながら何かを叫ぶ青年の姿。
見遣ればそこには、胸倉を掴んで血を吐きながら何かを叫ぶ青年の姿。
どういうこと、とは。彼は何を言っている?
いや、そもそも彼は敵だ。敵は、討たなくては。
そうしなければならないと叫ぶ。意味は、分からない。けれどやらなくては。
敵は全て倒して、マスターを、守らなければ。
……マスター?
いや、そもそも彼は敵だ。敵は、討たなくては。
そうしなければならないと叫ぶ。意味は、分からない。けれどやらなくては。
敵は全て倒して、マスターを、守らなければ。
……マスター?
「トーカちゃんはどうして消えた! 僕も、お前も、何もしてないはずなのに!」
消えた?
彼は何を言っているんだろう。言葉の意味が分からない。
必死の形相で叫ぶ彼は何やら大声でまくしたてて、だけどその言葉は私の耳に入ってこない。何故彼が董香の名前を知っているのか、何故ここまで取り乱しているのか、そんなことさえ疑問となって浮かぶことはなかった。
けれど、彼の言った一つだけは、すんなりと頭の中に入ってきた。
彼は何を言っているんだろう。言葉の意味が分からない。
必死の形相で叫ぶ彼は何やら大声でまくしたてて、だけどその言葉は私の耳に入ってこない。何故彼が董香の名前を知っているのか、何故ここまで取り乱しているのか、そんなことさえ疑問となって浮かぶことはなかった。
けれど、彼の言った一つだけは、すんなりと頭の中に入ってきた。
消えた。
マスターが、消えた。
マスターが、消えた。
「―――あ」
失われていた現実感が、頼んでもいないのに自分の中に戻っていく。そして無意識に目を逸らしていた事実も、また。
霧嶋董香が消えた。自分の目の前で、たった今。
霧嶋董香が消えた。自分の目の前で、たった今。
―――自分のこの手は、届かなかった。
「……令呪だ」
「令呪って、それは……」
「マスターは既に二つの令呪を使っていた。あれは、最後に残っていた一つだ」
「令呪って、それは……」
「マスターは既に二つの令呪を使っていた。あれは、最後に残っていた一つだ」
淡々と告げる言葉は青年に向けたものというよりも、未だ現実味のない自分へと言い聞かせるものだった。
鈍っていた思考がだんだんとクリアになっていき、ようやく周囲を見渡す余裕ができた。
眼前の青年は、全てが抜け落ちたような風体でこちらを見ていた。その姿は本当に小さくて、痛々しかった。
胸倉を掴むその手にさえ、空しいほどに何の力も入ってなかった。
鈍っていた思考がだんだんとクリアになっていき、ようやく周囲を見渡す余裕ができた。
眼前の青年は、全てが抜け落ちたような風体でこちらを見ていた。その姿は本当に小さくて、痛々しかった。
胸倉を掴むその手にさえ、空しいほどに何の力も入ってなかった。
「――――――……」
呟いた声が何だったのか、聞き取ることはできなかった。
よく見れば青年の体は酷くボロボロだった。手足は千切れ掛け、顔も胴体も傷ついていない場所なんてない。擦り切れ使い古された布きれのように、ちょっとでも触れれば途端に崩れ去ってしまいそうな、そんな印象を抱いた。
よく見れば青年の体は酷くボロボロだった。手足は千切れ掛け、顔も胴体も傷ついていない場所なんてない。擦り切れ使い古された布きれのように、ちょっとでも触れれば途端に崩れ去ってしまいそうな、そんな印象を抱いた。
けれど、そんなことは彼女にとってはどうでもよかった。
認めたくなかった事実を自分で言葉にしたことで、どうしようもなく過ぎてしまった真実として、脳裏に刻み込まれてしまったのだから。
認めたくなかった事実を自分で言葉にしたことで、どうしようもなく過ぎてしまった真実として、脳裏に刻み込まれてしまったのだから。
心が、止まった。
今度こそ、駄目だった。
頭の中が空っぽで、まともなことは何も考えられない。体は震え、目の奥がじわりと熱くなる。視界に映る全てが曖昧で、何もかもが夢の中の出来事のようだ。
霧嶋董香は死んだ。
守れたものは何もなかった。
なのにこうして、自分だけは生きている。
ああ―――なんて出来の悪い冗談なんだろう。
今度こそ、駄目だった。
頭の中が空っぽで、まともなことは何も考えられない。体は震え、目の奥がじわりと熱くなる。視界に映る全てが曖昧で、何もかもが夢の中の出来事のようだ。
霧嶋董香は死んだ。
守れたものは何もなかった。
なのにこうして、自分だけは生きている。
ああ―――なんて出来の悪い冗談なんだろう。
何故、あの時、トーカが「やめろ」と口にしたのか。それは分からない。
けれど、自分が致命的な過ちを犯してしまったということだけは否応なく理解できてしまう。
結局、自分は最後の最後まで、正しい道を選ぶことができなかったのか。
けれど、自分が致命的な過ちを犯してしまったということだけは否応なく理解できてしまう。
結局、自分は最後の最後まで、正しい道を選ぶことができなかったのか。
なんで……
「また、私だけ生き残ってしまった……のか」
そう、口にして。
「己が生を悲観するか、小娘。ならばこのワシが引導を渡してやろう」
しわがれた老獪な声が、耳に届いた。
横合いから殴りつける衝撃が、視界を黒一色に染め上げた。
横合いから殴りつける衝撃が、視界を黒一色に染め上げた。
▼ ▼ ▼
守るということ、それは失わせないということ。
守り堰き止め押し留める。ならば、そうする理由とは一体何なのか。
彼が守りたかったもの。彼が恐れていたもの。
それは結局のところ、他ならぬ彼自身であったのだろう。
再び失うのを恐れた。二度と失いたくなかったから守りたいと願った。
これはつまり、ただそれだけのお話。
誰も彼をも救おうとして、けれど自分を掬い上げることのできなかった、ひとりぼっちの男の子の物語。
守るために殺すという唯我の宿業が、英雄譚を塗り潰して喪失譚へと貶める。
守り堰き止め押し留める。ならば、そうする理由とは一体何なのか。
彼が守りたかったもの。彼が恐れていたもの。
それは結局のところ、他ならぬ彼自身であったのだろう。
再び失うのを恐れた。二度と失いたくなかったから守りたいと願った。
これはつまり、ただそれだけのお話。
誰も彼をも救おうとして、けれど自分を掬い上げることのできなかった、ひとりぼっちの男の子の物語。
守るために殺すという唯我の宿業が、英雄譚を塗り潰して喪失譚へと貶める。
▼ ▼ ▼
「―――え?」
素っ頓狂な声が、喉の奥から漏れ出た。
酷く不快な風の音と共に、目の前の少女が忽然と姿を消した。
一瞬の出来事だった。耳を劈く空気の振動が聞こえたと思ったら、その瞬間には掻き消えたように少女はどこにもいなかった。風と共に去って行ったかのように、つい先ほどのトーカのように。
酷く不快な風の音と共に、目の前の少女が忽然と姿を消した。
一瞬の出来事だった。耳を劈く空気の振動が聞こえたと思ったら、その瞬間には掻き消えたように少女はどこにもいなかった。風と共に去って行ったかのように、つい先ほどのトーカのように。
ふと、両の手首の辺りに熱を感じた。
見下ろしてみれば、手首から先が消失していた。
少女の胸倉を掴んでいたはずの手のひらはどこかへと消え去り、ぐじゅぐじゅの断面から勢いよく鮮血が飛び出している。
そして、消えた手のひらの向こう。先ほどまで少女が立っていたはずの地面には、棒状のものが二つ、転がっていた。
醜い断面を晒すそれは、左右で残された長さが違っていた。赤黒い部分からは絶えず血が吹きだし、辺りの地面を真っ赤に染め上げて止まらない。
それは、腰より上を失った少女の足だった。
手首に感じる熱が、激痛に変わった。
見下ろしてみれば、手首から先が消失していた。
少女の胸倉を掴んでいたはずの手のひらはどこかへと消え去り、ぐじゅぐじゅの断面から勢いよく鮮血が飛び出している。
そして、消えた手のひらの向こう。先ほどまで少女が立っていたはずの地面には、棒状のものが二つ、転がっていた。
醜い断面を晒すそれは、左右で残された長さが違っていた。赤黒い部分からは絶えず血が吹きだし、辺りの地面を真っ赤に染め上げて止まらない。
それは、腰より上を失った少女の足だった。
手首に感じる熱が、激痛に変わった。
「……ッ!」
瞬時に思考を戦闘用に切り替え、後方へ一足飛びに跳躍。優に十mの距離を移動し、感覚を最大限稼働させて周囲を警戒する。それはまだ見ぬ敵への警戒は勿論あるが、それ以上にある種の忌避と嫌悪の感情も含まれていた。
何故ならこの攻撃には見覚えがある。あの時と違い視認することさえ叶わない高速ではあったが、忘れたくても忘れられない敗北の苦渋が記憶に色濃く残っている。
そうだ、このあまりにも大雑把で、触れるもの全てを抉り取っていく邪風は―――
何故ならこの攻撃には見覚えがある。あの時と違い視認することさえ叶わない高速ではあったが、忘れたくても忘れられない敗北の苦渋が記憶に色濃く残っている。
そうだ、このあまりにも大雑把で、触れるもの全てを抉り取っていく邪風は―――
「フム、見た顔だと思えば貴様か。主を失ってなお見苦しく生き足掻くかよ小僧」
―――サーカスに舞うクラウンのように、その人影は優雅に姿を現した。
見覚えのある姿だった。聞き覚えのある声だった。そして何より、強く脳裏に刻み込まれた感情がそこにはあった。
それは道化師、それは老爺。遍く全てを嘲笑して刈り取っていく悪意の源泉。
見覚えのある姿だった。聞き覚えのある声だった。そして何より、強く脳裏に刻み込まれた感情がそこにはあった。
それは道化師、それは老爺。遍く全てを嘲笑して刈り取っていく悪意の源泉。
「その醜さにはほとほとあきれ返るが―――まあ、よい。ワシがその下らぬ生に幕を下ろしてやろう」
最古の四人が一体、パンタローネが舞台へと降り立った。
▼ ▼ ▼
結論を言えば、ネギ・スプリングフィールドの死体はその場所にはなかった。
正午を大きく過ぎた午後の陽射しの中、軽装で木々と土に挟まれた獣道を歩きとおした千雨は、慣れない悪路に疲弊しつつも戦闘痕に辿りつき、その現場を目撃した。
正午を大きく過ぎた午後の陽射しの中、軽装で木々と土に挟まれた獣道を歩きとおした千雨は、慣れない悪路に疲弊しつつも戦闘痕に辿りつき、その現場を目撃した。
拍子抜けでなかったと言えば嘘になるだろう。無意識にとはいえそれなりに覚悟はしていたし、鼓動を早める心臓は今にもはちきれんばかりであったが、結果だけ見ればこの通りである。
薙ぎ倒された木々の傍ら、ちょうどいい木陰に座り込み、千雨は深く嘆息する。
薙ぎ倒された木々の傍ら、ちょうどいい木陰に座り込み、千雨は深く嘆息する。
「……何してるんだろうな、私は」
ぽつりと、そう呟いた。
意図してのものではない。心も体も疲れ果てて、その末に飛び出た戯言でしかなかった。
だが真実でもある。わざわざ自分のサーヴァントの言葉を無視して、倒した敵の死体を確認しに遠出するなど、端的に言って気が触れている。
しかも結果は骨折り損のくたびれもうけだ。何かもが馬鹿らし過ぎて、一周回ってなんだか笑えてくる。
意図してのものではない。心も体も疲れ果てて、その末に飛び出た戯言でしかなかった。
だが真実でもある。わざわざ自分のサーヴァントの言葉を無視して、倒した敵の死体を確認しに遠出するなど、端的に言って気が触れている。
しかも結果は骨折り損のくたびれもうけだ。何かもが馬鹿らし過ぎて、一周回ってなんだか笑えてくる。
「……もう、行くか」
一言、そして千雨は重い腰を持ち上げて、億劫に立ち上がる。
ライダーは既にこの場を離れていた。曰く「サーヴァントの気配を感じた」とのことらしいが……流石にこの場所で暴れすぎて他のサーヴァントを呼び寄せてしまったのか、ともあれ道化のライダーは嬉々としながら千雨のことなど放ってさっさと行ってしまった。
ま、殺し合いなんざあの野郎に任せておけばいい、などと考えながら。千雨はぶらりと先を行く。
ライダーは既にこの場を離れていた。曰く「サーヴァントの気配を感じた」とのことらしいが……流石にこの場所で暴れすぎて他のサーヴァントを呼び寄せてしまったのか、ともあれ道化のライダーは嬉々としながら千雨のことなど放ってさっさと行ってしまった。
ま、殺し合いなんざあの野郎に任せておけばいい、などと考えながら。千雨はぶらりと先を行く。
葉の隙間から降り注ぐ木漏れ日が容赦なく肌に突き刺さり、今いる場所が夢ではなく現実なのだということをこれでもかというほど主張している。見上げた空はどこまでも透き通るようで、何故だか無性に腹立たしくなってくる。
ザッザッ、と地面に落ちた葉と靴が擦れる音だけが辺りに響き、いつの間にか雑木林から抜け出た千雨は、ふと遠目に何かが映るのを見た。
平坦な地面の向こう、霞むほど遠くに見える、学校の裏山。そこが、何やらやけに騒がしいような気がして。
ザッザッ、と地面に落ちた葉と靴が擦れる音だけが辺りに響き、いつの間にか雑木林から抜け出た千雨は、ふと遠目に何かが映るのを見た。
平坦な地面の向こう、霞むほど遠くに見える、学校の裏山。そこが、何やらやけに騒がしいような気がして。
「ああ、あそこで戦ってるのか」
気負いなく、感慨もなく、自分でも底冷えするような声音でそう呟く。また性懲りもなく、他のサーヴァントと戦っているのか、ライダーは。
だがそれでいい。戦って、戦って、その果てに自分に聖杯を献上すればいいのだと考える。そして傷ついたあいつを、自分は絶対に殺してみせるのだ。
だがそれでいい。戦って、戦って、その果てに自分に聖杯を献上すればいいのだと考える。そして傷ついたあいつを、自分は絶対に殺してみせるのだ。
とはいえ、思い返してみればあのクソピエロが戦っている場面を、そういえば自分は見たことがなかったと思い至る。
この際だから一見しておくのもいいだろうと、そう思って。千雨は動乱の中心であろう山中へと足を向けた。
この際だから一見しておくのもいいだろうと、そう思って。千雨は動乱の中心であろう山中へと足を向けた。
夢遊の様相でとぼとぼと道を往く彼女は、その先に慮外の希求物を見つけることとなるのだが。
それを知る者は、少なくとも現時点では存在しなかった。
それを知る者は、少なくとも現時点では存在しなかった。
▼ ▼ ▼
「ハハハハハハハハ!!
なんだねその様は、まるで見る影がないじゃないか!」
なんだねその様は、まるで見る影がないじゃないか!」
風が疾る。空が裂ける。
道化の腕が通り過ぎる全て、進行上にあるものは何もかもが削られ抉られ塵ひとつ残らない。
二本の腕は戯画的なまでに伸縮し互いを補う複雑な軌道を描き、音速を遥かに上回るスピードで青年に襲い掛かった。
青年を構成する肉体が、爆ぜる。
道化の腕が通り過ぎる全て、進行上にあるものは何もかもが削られ抉られ塵ひとつ残らない。
二本の腕は戯画的なまでに伸縮し互いを補う複雑な軌道を描き、音速を遥かに上回るスピードで青年に襲い掛かった。
青年を構成する肉体が、爆ぜる。
「ァア……ッ」
最早悲鳴を上げる力さえ、体に残ってなどいなかった。
溢れ出た無数の血飛沫が草木を汚す。疲労と損傷から飛びそうになる意識を無理やりに現実に繋ぎ留め、両手で頭部と頸部とを庇う。何の戦術も何の計算もない、苦し紛れの防御。反応する間もなく襲いくる風切の腕はそんな児戯など容易く打ち砕き、穴あきチーズのような有り様の青年の体を更に蝕んで削り取っていく。
戦闘開始から1分、青年―――金木研はただの一度も反撃していない。いいや、できないのだ。余力、スペック差、そのどれもが絶望的なまでの開きを見せている。事ここに至り、金木はただ嬲られるだけのサンドバックと化していた。
それでも未だに生きているのは、最低限致命傷を避けようとする必死の抵抗が功を奏していることと、何より喰種としての生命力あってのものだろう。骨が折れ曲がり肉が削げ落ちようと、極少量の魔力のみで高速修復されていく肉体はサーヴァントとしても破格の代物だ。
だがそれだけだ。残された魔力は回復に宛がうのみで手一杯で、反撃に移れるだけの力など微塵も存在しない。道化師の言う通り、かつて彼と戦った時とはまるで違う、まさしく見る影もないというやつだ。
今の金木は、パンタローネが気まぐれに放つ散発的な攻撃から逃げるだけで精一杯。このままでは一方的に命と魔力を削られるだけであり、彼が力尽きてしまうのも時間の問題だろう。
溢れ出た無数の血飛沫が草木を汚す。疲労と損傷から飛びそうになる意識を無理やりに現実に繋ぎ留め、両手で頭部と頸部とを庇う。何の戦術も何の計算もない、苦し紛れの防御。反応する間もなく襲いくる風切の腕はそんな児戯など容易く打ち砕き、穴あきチーズのような有り様の青年の体を更に蝕んで削り取っていく。
戦闘開始から1分、青年―――金木研はただの一度も反撃していない。いいや、できないのだ。余力、スペック差、そのどれもが絶望的なまでの開きを見せている。事ここに至り、金木はただ嬲られるだけのサンドバックと化していた。
それでも未だに生きているのは、最低限致命傷を避けようとする必死の抵抗が功を奏していることと、何より喰種としての生命力あってのものだろう。骨が折れ曲がり肉が削げ落ちようと、極少量の魔力のみで高速修復されていく肉体はサーヴァントとしても破格の代物だ。
だがそれだけだ。残された魔力は回復に宛がうのみで手一杯で、反撃に移れるだけの力など微塵も存在しない。道化師の言う通り、かつて彼と戦った時とはまるで違う、まさしく見る影もないというやつだ。
今の金木は、パンタローネが気まぐれに放つ散発的な攻撃から逃げるだけで精一杯。このままでは一方的に命と魔力を削られるだけであり、彼が力尽きてしまうのも時間の問題だろう。
……どうしたら。
迷いは一瞬。金木はここで初めての反撃に打って出た。地を蹴り、赫子を現出させ、滑るようにパンタローネの背後に回り込む。絶対に無視できない軌道で赫子を三本抜き放ち、迎撃のために打ち出された深緑の手の死角に飛び込む。囮の赫子と、煽りを喰らった左腕が微塵に刻まれ、飛び散った血が地面に落下する間もなく粒子と消える。金木はそれらを対価に、二つの深緑の手を掻い潜り、パンタローネの胴体に肉薄する。
残された一本の赫子の姿が、霞む。
パンタローネの口元が、歪に歪んだ。
胴体を軸に周回して再度襲いくる深緑の腕が、金木の知覚限界ぎりぎりの速度で空間を流れ、頭部に襲い掛かる。避け様に放った赫子の一撃は狙いを大きく逸れ、敵手の表面を浅く削るにとどまった。
残された一本の赫子の姿が、霞む。
パンタローネの口元が、歪に歪んだ。
胴体を軸に周回して再度襲いくる深緑の腕が、金木の知覚限界ぎりぎりの速度で空間を流れ、頭部に襲い掛かる。避け様に放った赫子の一撃は狙いを大きく逸れ、敵手の表面を浅く削るにとどまった。
やられた、と思考するよりも早く金木の眼前一㎝に迫る脚部。大気の壁を突き破った衝撃波と共に襲いくるパンタローネの蹴撃は狙い違わず金木の顔面を直撃。前斜体勢だった金木の上体を後方に大きく仰け反らせ、のみならず金木の全身を木々の五、六本ごと盛大に吹き飛ばした。
木々の崩れる音に紛れ、襤褸屑のように弾き飛ばされた金木の体が転がり出る。脱力しきった体はピクリとも動かず、空気を求める荒い呼吸だけが空しく宙に溶けていった。
限界であった。元より枯渇寸前だった魔力はとうとう底を尽き、既に再生能力すら碌に働いていない。傷口から流れ出た血液や肉片は次々と魔力の粒子となって消えていき、彼が消滅するまで数分と保たないと言って憚らない。
木々の崩れる音に紛れ、襤褸屑のように弾き飛ばされた金木の体が転がり出る。脱力しきった体はピクリとも動かず、空気を求める荒い呼吸だけが空しく宙に溶けていった。
限界であった。元より枯渇寸前だった魔力はとうとう底を尽き、既に再生能力すら碌に働いていない。傷口から流れ出た血液や肉片は次々と魔力の粒子となって消えていき、彼が消滅するまで数分と保たないと言って憚らない。
「ハァッ、ハァッ、ハァッ……」
言葉すらまともに発せないほどに疲弊した金木のもとへ、パンタローネが酷くゆっくりと近づいてくる。
顔面には嘲笑の歪みを張り付けて、いっそわざとらしいまでに遅々とした歩みで死を運んでくる。
顔面には嘲笑の歪みを張り付けて、いっそわざとらしいまでに遅々とした歩みで死を運んでくる。
―――駄目だ、勝てない。今の自分ではどうにもできない。
脳を支配する敗北感よりも心を満たす屈辱よりも先に、直感として金木はそう悟った。
「さて、極東ではこれを年貢の納め時とでも言うのだったか。
まあよい。ともあれ貴様は、これにて終幕よ」
まあよい。ともあれ貴様は、これにて終幕よ」
声が聞こえる。
それは、幼い主を殺した、嗤う道化師の声。
目は霞んでよく見えない。感触もほとんどない。それでも、何故か声だけは鮮明に聞こえてくる。
それは、幼い主を殺した、嗤う道化師の声。
目は霞んでよく見えない。感触もほとんどない。それでも、何故か声だけは鮮明に聞こえてくる。
微かに、正面に風を感じた。
どちらに避ければいいのか、分からない。いや、そもそも回避行動すら取ることはできないか。
体が、思うように動かない。
不思議と恐怖はなかった。
ただ、何も為すことなく死んでいく自分が、とても情けなくて。
どちらに避ければいいのか、分からない。いや、そもそも回避行動すら取ることはできないか。
体が、思うように動かない。
不思議と恐怖はなかった。
ただ、何も為すことなく死んでいく自分が、とても情けなくて。
「いや、だ……」
知らず声が漏れる。
死の風を運ぶ道化の足取りが、ピタリと止まったような気がした。
死の風を運ぶ道化の足取りが、ピタリと止まったような気がした。
このまま死んでいくなんて嫌だ。僕にはまだ、やるべきことが残っているのだから。
助けなくては。戦わなくては。この手から零れ落ちていってしまった彼らを、どんな手段を使ってでも救わなければ。
そうしなければならない、しなければならないのだ。
助けなくては。戦わなくては。この手から零れ落ちていってしまった彼らを、どんな手段を使ってでも救わなければ。
そうしなければならない、しなければならないのだ。
「ネギくん、ネギくん、ネギく……ゲアァ!」
ボタボタと血が零れる。息が詰まる。言葉が上手く出てこない。
「トーカちゃんッ……あ、あぁ……!」
心だけが先行して体が動かない。手は、地面をガリガリと削るだけ。
「くそ、なんで……まだ、早く行かないと……
僕が助ける、僕が助けるんだ……!」
僕が助ける、僕が助けるんだ……!」
何も見えない、何も聞こえない。浮かぶのはただ、一つの意思。
―――ああ、視界の端で。
―――仮面をつけた、黒い道化師が嗤っている。
―――ああ、視界の端で。
―――仮面をつけた、黒い道化師が嗤っている。
「だずげッ……!」
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
「たずッ……!」
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
僕が僕が僕が僕が僕が僕が僕が
「僕がっ、僕がっ、僕がっ!」
僕が。
「僕があああああああああああああああああああっ!!」
助ける。
「やかましい」
ぶぢゅり、と。
道化の足が胴体を穿つ。それだけで青年の最期の足掻きは停止した。
今度こそ、あらゆる戦いは幕を下ろしたのだ。
道化の足が胴体を穿つ。それだけで青年の最期の足掻きは停止した。
今度こそ、あらゆる戦いは幕を下ろしたのだ。
「意味もなく吠えおって、最期まで煩わしい羽虫であったわ。だが」
「これで終わり、ってか。
……ったく、どんだけ遊んでんだよ、てめーは」
「これで終わり、ってか。
……ったく、どんだけ遊んでんだよ、てめーは」
ふと、パンタローネの背後から聞こえる声。
見なくても分かる。そこにいるのは長谷川千雨、他ならぬパンタローネの主である。
彼女は現場とそこに転がっているランサーの肢体を見るなり顔を顰め、心底不愉快そうに吐き捨てた。
見なくても分かる。そこにいるのは長谷川千雨、他ならぬパンタローネの主である。
彼女は現場とそこに転がっているランサーの肢体を見るなり顔を顰め、心底不愉快そうに吐き捨てた。
「なに、こやつは以前、身の丈に合わぬ生意気を言ったことがあるのでな。
それに所詮は主を失ったはぐれよ。このパンタローネが遅れを取るはずもあるまい?」
「慢心も程々にしとけよ。そんで、だ」
それに所詮は主を失ったはぐれよ。このパンタローネが遅れを取るはずもあるまい?」
「慢心も程々にしとけよ。そんで、だ」
千雨は嫌そうな顔を隠そうともせず、両者の近くへと歩いてくる。
パンタローネに踏み抜かれた金木を見下ろし、静かに問うた。
パンタローネに踏み抜かれた金木を見下ろし、静かに問うた。
「こいつ、確かてめーが殺したっていうマスターが従えてたサーヴァントだよな。特徴、大体合ってるみてえだし」
「フム、まあその通りだな。あの時は主を殺した故、消滅も時間の問題だと思うておったのだが、何やら見苦しく悪あがきでもしておったのだろう」
「フム、まあその通りだな。あの時は主を殺した故、消滅も時間の問題だと思うておったのだが、何やら見苦しく悪あがきでもしておったのだろう」
それも結局は無駄な足掻きだったようだがな、とくつくつ笑うパンタローネを無視し、千雨はただ、眼下のサーヴァントに問いかけた。
「なあ、アンタ。アンタはネギ先生に従ってたわけだ。
そんで聞きたいんだけどよ、アンタは今こうして生き延びてまで、何のために戦ってたんだ?」
そんで聞きたいんだけどよ、アンタは今こうして生き延びてまで、何のために戦ってたんだ?」
意外な問いかけだった。少なくとも、今にも死のうとしている敵に問うべきものではない。
当然の如くパンタローネも嘲笑から怪訝な顔に表情を変える。その問いかけの意味がパンタローネにも、問われた当人である金木にも、推し量ることはできなかった。
いや、金木には一つだけ分かったことがある。
彼女は今、ネギ先生と言った。この少女にはおろか、彼女が従える道化のサーヴァントにも明かしていない少年の名を。
つまり、これは―――
当然の如くパンタローネも嘲笑から怪訝な顔に表情を変える。その問いかけの意味がパンタローネにも、問われた当人である金木にも、推し量ることはできなかった。
いや、金木には一つだけ分かったことがある。
彼女は今、ネギ先生と言った。この少女にはおろか、彼女が従える道化のサーヴァントにも明かしていない少年の名を。
つまり、これは―――
「……マスターよ、その問いに一体何の意味があるという」
「別にいいだろ。どうせすぐ死ぬんだ、聞いたところで何の問題もねーよ」
「別にいいだろ。どうせすぐ死ぬんだ、聞いたところで何の問題もねーよ」
それもそうか、とパンタローネは押し黙る。金木は、振り絞るように声を出した。
「聖杯を……ネギくんの願いを、果たすためだ……」
「……てめーの願いの間違いじゃねえのか?」
「それもある。けど……ネギくんを見捨てるなんて、僕には、できない……」
「……てめーの願いの間違いじゃねえのか?」
「それもある。けど……ネギくんを見捨てるなんて、僕には、できない……」
そこで言葉は切れた。金木の息は荒く、最早これ以上言葉を紡ぐことすら難しい様子だ。
パンタローネはぐじゅり、と踵を踏みしだく。ビクリと金木の体が痙攣した。
パンタローネはぐじゅり、と踵を踏みしだく。ビクリと金木の体が痙攣した。
「さて、これで用は済んだであろうマスター。これ以上の問答は時間の無駄よ、さっさと死なすがよかろう」
「ああ、そうだな」
「ああ、そうだな」
そして、全ての猶予は過ぎ去った。
嗤う道化師と、表情のない少女。彼らは共に躊躇なく、敵の命を刈り取る希求者だ。
目的のためなら手段を択ばない。甘さなど不要、殺すべきは即座に殺す。
故に、命運は既に定まった。
嗤う道化師と、表情のない少女。彼らは共に躊躇なく、敵の命を刈り取る希求者だ。
目的のためなら手段を択ばない。甘さなど不要、殺すべきは即座に殺す。
故に、命運は既に定まった。
「けどまあ」
そう、既に。
この時、【彼】が死ぬのは決定事項だったのだ。
この時、【彼】が死ぬのは決定事項だったのだ。
「死ぬのはお前だけどな、ライダー」
掲げられた右手の甲が、赤い光を放って。
「令呪を以て命じる。パンタローネ、てめえが最も忌避する手段で自害しろ」
天下に響き渡る号令の如く、絶対遵守の命が下された。
▼ ▼ ▼
それは文字通り自動で動く人形であり、外見こそ簡易的な絡繰り人形でありながらも高度な知性と自我を有し圧倒的な戦闘能力を誇る、錬金術からこぼれた欠片の一である。
人形に意思と動力を与える疑似体液を循環させ、人の血を啜ることで機能を維持する。「武器を持たない人間を相手に視認不可な速度で動いてはならない」という黄金律を持ち、それ故に近代兵装では到底太刀打ちできない等身大の死の恐怖。
数百年前の産物でありながら最先端科学ですら到底追いつけない未知のテクノロジーの集大成。彼らは一体何故、何のために作られたのか。
その存在理由。原初の制作目的とは至って単純。「フランシーヌ人形を笑わせる」ことである。
すなわち全ての自動人形はフランシーヌ人形だけのためにあり、その存在そのものが自動人形の機構を動かす意味なのだ。
故に、彼らはフランシーヌ人形を否定してはならない。
それを為してしまえば―――彼らがこの世にある理由など、塵一つ分すらも残されないのだから。
▼ ▼ ▼
「あ……」
一帯を、静寂が包んだ。
パンタローネの最初の呻き以外、誰も口を開かなかった。なぎ倒された木々の残骸と、葉が擦れる音しか聞こえない。。
金木は倒れ、千雨は口を閉ざし。
そして、パンタローネは。
パンタローネの最初の呻き以外、誰も口を開かなかった。なぎ倒された木々の残骸と、葉が擦れる音しか聞こえない。。
金木は倒れ、千雨は口を閉ざし。
そして、パンタローネは。
「う、うぐ、ぅあ、あああああああああああああああああああああああああああ!!?」
絶叫が迸る。
今やパンタローネは半狂乱となって身悶えしていた。常の尊大さも被造物の優越も、そこにはなかった。
叫ぶ、叫ぶ、叫ぶ。腕はもがくように振り回され、顔面は用途も知れぬ液体が大量に垂れ流され、醜悪に歪んだ形相は人間では真似できない領域の歪みに達しつつある。
だが、しかし―――
叫ぶ、叫ぶ、叫ぶ。腕はもがくように振り回され、顔面は用途も知れぬ液体が大量に垂れ流され、醜悪に歪んだ形相は人間では真似できない領域の歪みに達しつつある。
だが、しかし―――
「き、さま……貴様貴様貴様ァッ!
よくも、このパンタローネを、謀って、くれ、たな……!」
よくも、このパンタローネを、謀って、くれ、たな……!」
しかしそれだけだ。パンタローネの体は何一つ傷ついていない。
憤怒の凶顔は抑えきれぬ憎悪を湛えて千雨を睨みつけ、嚇怒の念は空間さえ軋ませてただ一人に向けられていた。
恐ろしいほどの凶念を叩きつけられる千雨は、尚無表情のままである。
わき目も振らず取り乱し、隠しもしない殺意の奔流を渦巻かせるパンタローネと、それと正反対に能面のような静謐さを湛える千雨。
恐ろしいほどの凶念を叩きつけられる千雨は、尚無表情のままである。
わき目も振らず取り乱し、隠しもしない殺意の奔流を渦巻かせるパンタローネと、それと正反対に能面のような静謐さを湛える千雨。
今やパンタローネは憤死さえしかねないのではと思わんばかりに乱れ狂い。
だが、命令たる自害をする様子は微塵もなかった。
何故なら、それは。
だが、命令たる自害をする様子は微塵もなかった。
何故なら、それは。
「このパンタローネに……あまつさえ、【フランシーヌ様を否定しろ】と言うか……!
我等の存在意義、我等の在るべき根源を、貴様は……ワシ自ら凌辱しろと言うのかァ……!」
我等の存在意義、我等の在るべき根源を、貴様は……ワシ自ら凌辱しろと言うのかァ……!」
ライダーのサーヴァント、パンタローネが保有するスキルに、「最古の四人」というものがある。
文字通り自動人形 の中でも最古に作られた原初の四人であるパンタローネは、他の自動人形の例に漏れずある一つの存在意義の元に作られた。
それがフランシーヌ人形。かの者を笑わせることだけが、彼らの存在する意味なのだ。
それ故に、彼はことフランシーヌ人形に関する事象においてのみ、マスターの命令すら背いて行動することができる。
それは例えば、令呪の強制であったとしても。
彼が彼としてある根源理由のために、例外的に抵抗が可能となっているのだ。
文字通り
それがフランシーヌ人形。かの者を笑わせることだけが、彼らの存在する意味なのだ。
それ故に、彼はことフランシーヌ人形に関する事象においてのみ、マスターの命令すら背いて行動することができる。
それは例えば、令呪の強制であったとしても。
彼が彼としてある根源理由のために、例外的に抵抗が可能となっているのだ。
仮に、そう仮に。千雨が命じたのがただの自害であったならば、一瞬の思考の余地も与えられぬままに深緑の手は自らの喉笛を抉り取っていただろうが。
彼の思う最悪の自死手段がフランシーヌの否定である以上、そうは問屋が卸さない。
彼の思う最悪の自死手段がフランシーヌの否定である以上、そうは問屋が卸さない。
「……ああ、やっぱてめえにとっての最悪ってそれだったんだな」
だが笑う。千雨は、嗤った。
ここで初めて、千雨に表情が出た。それはどこまでも寒々しい、酷薄な笑みだった。
ここで初めて、千雨に表情が出た。それはどこまでも寒々しい、酷薄な笑みだった。
「それに言ったよな、慢心は程々にしとけって。
私がどれだけてめえのことを殺したいと思ってたか、まさか分からないなんて言わないよな?」
私がどれだけてめえのことを殺したいと思ってたか、まさか分からないなんて言わないよな?」
嗤う、ニタニタと。
「それともまさか―――自分は貴重な戦力だから切り捨てられないって、んなことでも考えてたのか?」
嗤う、ケタケタと。
「ンなわけねぇだろうが糞ピエロ! 代わりさえ見つかりゃあ、てめえなんざ即刻ぶっ殺すに決まってンだろうが!」
「長谷川、チサメェエエエエエエッ!!」
「悔しいか? 悔しいかよッ! 人の感情も碌に分からねえガラクタの癖に、一丁前に吠えんじゃねえ!」
「ヌ、グ、オオオオオォォォオオォォオオオオッ!!」
「長谷川、チサメェエエエエエエッ!!」
「悔しいか? 悔しいかよッ! 人の感情も碌に分からねえガラクタの癖に、一丁前に吠えんじゃねえ!」
「ヌ、グ、オオオオオォォォオオォォオオオオッ!!」
雄叫びと共に重圧を無理やり引き千切るように持ち上げられたパンタローネの腕から、不可視の真空弾が狂ったように吐き出される。
周囲の地面や木々を無秩序に破壊する真空弾は、しかし千雨を殺すことはない。所詮は令呪の強制に抗った末の苦し紛れだ、碌に狙いもつけられていない。
周囲の地面や木々を無秩序に破壊する真空弾は、しかし千雨を殺すことはない。所詮は令呪の強制に抗った末の苦し紛れだ、碌に狙いもつけられていない。
不可視の穿閃が、千雨のすぐ右側を貫いて通り過ぎていく。
ばしゃり、と。右腕が抉れて血が飛び散った。致命傷ではない。痛みすら、今は何も感じない。
ばしゃり、と。右腕が抉れて血が飛び散った。致命傷ではない。痛みすら、今は何も感じない。
「……重ねて令呪を以て命じる」
そう、パンタローネを……大切だった者たちを悉く殺したこいつを絶望させるためならば。
痛みだろうが令呪だろうが、惜しいものなど何一つ無かった。
忌まわしい赤の輝きが、再度右手から発せられる。
痛みだろうが令呪だろうが、惜しいものなど何一つ無かった。
忌まわしい赤の輝きが、再度右手から発せられる。
「パンタローネ、フランシーヌを否定しろ」
ピタリ、と。
狂声を上げて怒り狂っていたパンタローネの動きが、止まった。
ガタガタと音を鳴らし、何かを強く嫌がるように振動して。
狂声を上げて怒り狂っていたパンタローネの動きが、止まった。
ガタガタと音を鳴らし、何かを強く嫌がるように振動して。
「ワシ、は……」
「……言え」
「ワ、ワシは……フランシーヌを……」
「さっさと言いやがれ! これは命令だ!
言え、言うんだよ!」
「……言え」
「ワ、ワシは……フランシーヌを……」
「さっさと言いやがれ! これは命令だ!
言え、言うんだよ!」
嫌だ嫌だと頭を振って。
ついには、言った。
ついには、言った。
「ワシは―――フランシーヌなど関係ない!」
静寂。
「う、あ……」
静寂。
「ワ、ワシは何を言った……?
ワシは一体、何を……」
ワシは一体、何を……」
ざあ、と。土砂降りのような水音が辺りに響く。
「ワシは、ワシはああああぁぁぁぁ……!」
瞬間、堰をきったように。
パンタローネの全身から、白銀の液体が噴出した。
パンタローネの全身から、白銀の液体が噴出した。
「……とうとう言ったな、パンタローネ」
それを見て、千雨はただ静かに呟いた。
「てめえだけは許さない。
潰れろ。砕けろ。粉々に、砕け散って死ね」
潰れろ。砕けろ。粉々に、砕け散って死ね」
長谷川千雨は、パンタローネというサーヴァントのことを逐一把握していた。自分のサーヴァントなのだ、その由来程度は朧気ながらも記憶に流れ込んでいる。
自動人形が在る意味、フランシーヌという存在。その関係性。
いまいち確証がなかったから最初の令呪では曖昧な命令しか与えられなかったが、こうまで上手く嵌ってくれた今なら確信が持てる。
自動人形が在る意味、フランシーヌという存在。その関係性。
いまいち確証がなかったから最初の令呪では曖昧な命令しか与えられなかったが、こうまで上手く嵌ってくれた今なら確信が持てる。
自らが生きる理由を手放して、自動人形が存在できるはずもない。
自分の復讐は。
とうとう形を成したのだと。
とうとう形を成したのだと。
「あああァ……フランシーヌ様ぁ、お許しください……パンタローネの、このワシの本心ではないのです……!
フランシーヌ、様ァァァ……!」
フランシーヌ、様ァァァ……!」
その肢体のどこにそれだけの量が入っていたのだと言わんばかりの白液が、止め処なく溢れ出ては大地を銀に汚していく。
自分の言葉を信じられないという様子でうろたえるその姿は、捨てられることを恐れる哀れな子供のようにも思えて。
自分の言葉を信じられないという様子でうろたえるその姿は、捨てられることを恐れる哀れな子供のようにも思えて。
けれど、そんな下手くそな道化芝居を顧みる者は、どこにもいなかった。
千雨は視界の向こうで崩れ落ちる道化師を無視し、足元に倒れる青年に手を差し向ける。
哀れみではない。情でもない。それはどこまでも打算に満ちた、けれどそれ故に真摯な願いを籠めた、救いの手。
哀れみではない。情でもない。それはどこまでも打算に満ちた、けれどそれ故に真摯な願いを籠めた、救いの手。
「私は、聖杯を手に入れる」
語りかけるように、千雨は言葉を紡いでいく。
金木は、ただ彼女を見上げるだけだ。
金木は、ただ彼女を見上げるだけだ。
「何をしても、どれだけ失っても、私は奇跡を諦めない」
紡ぐ彼女の眦が、その時微かに揺らめいた。
「だから手を貸せ。お前も、それだけの理由があるんだろ」
「……君は」
「……君は」
有無を言わせぬ千雨の声に。
表情の抜け落ちた顔で、一つだけ問い返した。
表情の抜け落ちた顔で、一つだけ問い返した。
「君は、誰だ?」
白痴のような青年の問いかけに。
千雨は大きく、大きく笑った。
千雨は大きく、大きく笑った。
「ネギ先生の生徒だよ、ランサー」
そして二人の手が重なって。
荒れ果てた新緑の空間に、一際大きな光が瞬いた。
荒れ果てた新緑の空間に、一際大きな光が瞬いた。
▼ ▼ ▼
祈り、願い、誓い、信じる。
最早、彼らにそれを説く意味はない。
彼らはただ聖杯を目指し駆け抜けるのみ。
それしか、残された道は、ない。
最早、彼らにそれを説く意味はない。
彼らはただ聖杯を目指し駆け抜けるのみ。
それしか、残された道は、ない。
▼ ▼ ▼
そうして。
残ったのは、二人だけだった。
残ったのは、二人だけだった。
右腕から流れる血を一顧だにしない、眼鏡をかけた少女と。
崩れかけの肉体をそれでも繋ぎ支えて立つ、白髪の青年。
共に何かを喪失した、自分の救われる明日さえも見失った、そんな二人だった。
崩れかけの肉体をそれでも繋ぎ支えて立つ、白髪の青年。
共に何かを喪失した、自分の救われる明日さえも見失った、そんな二人だった。
互いに会話はなかった。話す必要を感じなかったから。
互いに繋がることもなかった。所詮は聖杯を手に入れるための仮初の主従関係なのだから、情が入らないほうがいいと思ったから。
互いに繋がることもなかった。所詮は聖杯を手に入れるための仮初の主従関係なのだから、情が入らないほうがいいと思ったから。
戦場跡を離れようと踵を返した今も、言葉と視線は交わさなかった。
どちらもまるで白昼夢のように存在感が不確かさだが、しかしどちらも確かにここに在り、明確な目的意識を持って活動している。
何より目が違った。体は傷つき、今にも倒れてしまいそうな危うさこそあれど、しかし意思に燃える瞳があればこそ、その肉体は不撓不屈の歩みを以て進み続けるのだと言外に示している。
彼らは戦う者だ。戦い勝ち取る者だ。後退の許されない各々の矜持を持ち合わせ、どれほど奪われ失おうとも手を伸ばし続ける落伍者だ。
失い、傷つき、打ちのめされてボロボロになって、それでも歩みを止めない敗残者だ。だからこそ、その足取りは重く、決意の音を響かせる。
どちらもまるで白昼夢のように存在感が不確かさだが、しかしどちらも確かにここに在り、明確な目的意識を持って活動している。
何より目が違った。体は傷つき、今にも倒れてしまいそうな危うさこそあれど、しかし意思に燃える瞳があればこそ、その肉体は不撓不屈の歩みを以て進み続けるのだと言外に示している。
彼らは戦う者だ。戦い勝ち取る者だ。後退の許されない各々の矜持を持ち合わせ、どれほど奪われ失おうとも手を伸ばし続ける落伍者だ。
失い、傷つき、打ちのめされてボロボロになって、それでも歩みを止めない敗残者だ。だからこそ、その足取りは重く、決意の音を響かせる。
今や彼らを止めることができるのは、その首を切り裂く刃のみ。
言葉や信念で足を止めるほど、彼らは光に身を浸してはいない。
言葉や信念で足を止めるほど、彼らは光に身を浸してはいない。
だからだろうか。
彼らに届けられたのは、言葉でも、心でもなく。
暖かみの欠片も存在しない、一発の銃声と鉛玉だった。
彼らに届けられたのは、言葉でも、心でもなく。
暖かみの欠片も存在しない、一発の銃声と鉛玉だった。
不意に逸らした金木の首の横を、風切音が通り過ぎる。
先の見えない遠くのほうで、何かが爆発する音が聞こえた。
先の見えない遠くのほうで、何かが爆発する音が聞こえた。
「ッ、てめえ……!」
「……」
「……」
驚愕と怒気を露わに振り返る千雨と、生気のない動作で緩慢に視線を向ける金木。対照的な二人の視線の先にあったのは、一人の少女の姿。
小柄な体躯に似合わぬ大口径の砲口を向け、ただ立ち尽くす弓兵の姿。
水兵服に白銀の長髪、見間違えるはずもない。
董香が使役していたサーヴァント、アーチャーであった。
小柄な体躯に似合わぬ大口径の砲口を向け、ただ立ち尽くす弓兵の姿。
水兵服に白銀の長髪、見間違えるはずもない。
董香が使役していたサーヴァント、アーチャーであった。
「君は……」
金木はただヴェールヌイを睥睨し、小さく静かに声を投げかけた。胡乱げな視線をよこす彼の姿からは、何の抑揚も感じ取ることはできなかった。
砲口を向けるヴェールヌイは、今や直立が難しいほどに激しい痙攣に襲われていた。腕は愚か全身がガクガクと揺れ、射線は杳として定まらない。先ほど放たれた砲撃は呆れるほどゆっくりで、肉体から離れた砲弾にすら影響が及んでいるのだと容易に察することができた。
そう、影響。一体どのような手段で黄泉路から蘇ったかは知らないが、彼女には未だに令呪の強制が残っている。すなわち『やめろ』、この場での戦闘行為を禁じる命令が、ヴェールヌイの体を縛って離さない。
令呪の強制力を考えれば、一撃を放てたことさえ信じられない奇跡だ。例え敵手に一切の痛打を与えられず、ただ無様に生き足掻くだけの結果に終わろうと、彼女の抱く意志力は賞賛されて余りあるものであると言える。
砲口を向けるヴェールヌイは、今や直立が難しいほどに激しい痙攣に襲われていた。腕は愚か全身がガクガクと揺れ、射線は杳として定まらない。先ほど放たれた砲撃は呆れるほどゆっくりで、肉体から離れた砲弾にすら影響が及んでいるのだと容易に察することができた。
そう、影響。一体どのような手段で黄泉路から蘇ったかは知らないが、彼女には未だに令呪の強制が残っている。すなわち『やめろ』、この場での戦闘行為を禁じる命令が、ヴェールヌイの体を縛って離さない。
令呪の強制力を考えれば、一撃を放てたことさえ信じられない奇跡だ。例え敵手に一切の痛打を与えられず、ただ無様に生き足掻くだけの結果に終わろうと、彼女の抱く意志力は賞賛されて余りあるものであると言える。
「私、は……」
震えるような声が、彼女の口から漏れ出る。
「私は、【響】。暁の水平線に勝利を刻む、誉れ高き第六駆逐隊が一隻……」
震える右手が、徐々に照準を一点に定める。
「私は、今度こそ……最期まで、マスターのために戦い抜く」
……最初とは、まるで正反対の構図となっていた。
アーチャーのクラスである彼女は、単独行動のスキルによりマスター不在でも行動が可能である。しかし、それは十全の戦闘行為が可能であるというわけでは断じてない。
マスターからの魔力供給が途絶している以上、その性能は極限まで低下しているはずだ。少なくとも、令呪の命令により生き永らえていた先ほどまでの金木と同程度には。
だからこそ、これは役者を入れ替えた上での焼き直し。眼前の敵に決して勝てないことを理解していながらも、彼女は戦うことを止めはしない。
アーチャーのクラスである彼女は、単独行動のスキルによりマスター不在でも行動が可能である。しかし、それは十全の戦闘行為が可能であるというわけでは断じてない。
マスターからの魔力供給が途絶している以上、その性能は極限まで低下しているはずだ。少なくとも、令呪の命令により生き永らえていた先ほどまでの金木と同程度には。
だからこそ、これは役者を入れ替えた上での焼き直し。眼前の敵に決して勝てないことを理解していながらも、彼女は戦うことを止めはしない。
全てを失って尚、弱さをひた隠し毅然と立ち向かうその姿は。
弁解の余地なく哀れで、無様で、滑稽で。
それでも、どうしようもなく美しかった。
弁解の余地なく哀れで、無様で、滑稽で。
それでも、どうしようもなく美しかった。
「……ランサー、さっさと殺せ」
ヴェールヌイから目を逸らすように、千雨の命令が金木に届く。
腰部から赫黒の繊手が四条、体組織を急激に変化させながら何物をも貫く剛槍として現出した。陽の光を背にするその姿は、さながら巨大な蜘蛛のようにも見えた。
腰部から赫黒の繊手が四条、体組織を急激に変化させながら何物をも貫く剛槍として現出した。陽の光を背にするその姿は、さながら巨大な蜘蛛のようにも見えた。
「……さようなら」
槍の穂先と共に、そう言葉をかけて。
「最期までトーカちゃんのために戦おうとしてくれて、ありがとう」
筋肉の爆発的な収縮によって、四条の赫子は違わず白銀の少女へと殺到した。
咲き誇る花の如く、空間を彩る赤と白が大輪となって飛び散った。
咲き誇る花の如く、空間を彩る赤と白が大輪となって飛び散った。
――――――――
最初に会った時は、なんだか迷子みたいな子だな、と思った。
光の当たらない夜の暗闇が満ちる、どこかの部屋の中。
あの子は、何かを覚悟した顔つきで、けれど隠しようもない寂しさを湛えて、こちらを見ていた。
あの頃はまだ、今と比べてあまり会話の数が多くない間柄だったと記憶している。ヴェールヌイという名前を告げたら、ヴぇ……なに? と、きょとんとした顔で返された。一瞬だけだが、そこに年相応の幼さを見たと、そう思う。
それから暫くもしないうちに分かった。この子は自分と同じなのだと。
共に置いて行かれてしまった子供。戦う力を持ちながら、けれど守りたいものを守る戦いの場に立つことすらできなかった、失っていくだけのかつての私。
この偽りの世界でただ一人、想いを共有することのできた人。
だから、ずっと思っていた。自分は必ずこの少女に、彼女の望んだ明日を取り戻してみせるのだと。ただ失っていくだけの未来など御免だから、せめて彼女にだけはそんな道を歩ませないのだと、そう誓った。
聖杯戦争の本戦が始まると告げられた時。私はただ、告げられた事実だけを淡々と伝えた。彼女はいつもと変わらないぶっすりとした表情で、ただ「そっか」、とだけ呟いた。
けれど、確かに私は覚えている。
いつも通りのやり取りを終えて索敵に戻ろうとした私に、彼女は「改めてよろしく」、と、微かに微笑んでくれたことを。
私は、決して忘れない。
きっと、それは彼女自身さえも意識しない本当に小さなものだったけど。
それだけで、私はどこか救われたような気さえしたのだ。
光の当たらない夜の暗闇が満ちる、どこかの部屋の中。
あの子は、何かを覚悟した顔つきで、けれど隠しようもない寂しさを湛えて、こちらを見ていた。
あの頃はまだ、今と比べてあまり会話の数が多くない間柄だったと記憶している。ヴェールヌイという名前を告げたら、ヴぇ……なに? と、きょとんとした顔で返された。一瞬だけだが、そこに年相応の幼さを見たと、そう思う。
それから暫くもしないうちに分かった。この子は自分と同じなのだと。
共に置いて行かれてしまった子供。戦う力を持ちながら、けれど守りたいものを守る戦いの場に立つことすらできなかった、失っていくだけのかつての私。
この偽りの世界でただ一人、想いを共有することのできた人。
だから、ずっと思っていた。自分は必ずこの少女に、彼女の望んだ明日を取り戻してみせるのだと。ただ失っていくだけの未来など御免だから、せめて彼女にだけはそんな道を歩ませないのだと、そう誓った。
聖杯戦争の本戦が始まると告げられた時。私はただ、告げられた事実だけを淡々と伝えた。彼女はいつもと変わらないぶっすりとした表情で、ただ「そっか」、とだけ呟いた。
けれど、確かに私は覚えている。
いつも通りのやり取りを終えて索敵に戻ろうとした私に、彼女は「改めてよろしく」、と、微かに微笑んでくれたことを。
私は、決して忘れない。
きっと、それは彼女自身さえも意識しない本当に小さなものだったけど。
それだけで、私はどこか救われたような気さえしたのだ。
彼女がいたから、私は今日まで戦ってこれた。
想いは最期まで交わらず、知らず与えられた暖かさに返せたものなど何一つなかったけれど。
私は、本当に、霧嶋董香というマスターのことが好きだった。
想いは最期まで交わらず、知らず与えられた暖かさに返せたものなど何一つなかったけれど。
私は、本当に、霧嶋董香というマスターのことが好きだった。
【霧嶋董香@東京喰種 消滅】
【ライダー(パンタローネ) 消滅】
【アーチャー(ヴェールヌイ) 消滅】
【ライダー(パンタローネ) 消滅】
【アーチャー(ヴェールヌイ) 消滅】
▼ ▼ ▼
彼女たちの軌跡はここで終わる。何を為すこともなく、ただ無為に命を華と散らし、無明へと溶け消えゆく幻想の一幕。
彼女たちが共に何を思い、何を願って戦いに臨んだのか。それを確りと知る者は、今や何処にも存在しない。
彼女たちが共に何を思い、何を願って戦いに臨んだのか。それを確りと知る者は、今や何処にも存在しない。
けれど。
けれど仮に、彼女たちの紡いできた軌跡を形にするならば。
けれど仮に、彼女たちの紡いできた軌跡を形にするならば。
独りになることを恐れた少女と、独りで歩み続けてしまった少女の終着を。
独りが嫌だから立ち上がった少女と、それを支えようとした少女の帰結を。
独りが嫌だから立ち上がった少女と、それを支えようとした少女の帰結を。
全て纏めて繋ぎ合わせ、仮に一つの物語としたならば。
それは、やはり"悲劇"でしかないのだろう。
【C-2/学園の裏山/一日目 午後】
【ランサー(金木研)@東京喰種】
[状態]全身に甚大なダメージ(回復中)、疲労(極大)、魔力消費(極大)、『喰種』
[装備]高等部の制服
[道具]なし。
[思考・状況]
基本行動方針:誰が相手でも。どんなことをしてでも。聖杯を手に入れる。
1.――――。
[備考]
長谷川千雨とマスター契約を交わしました。
[状態]全身に甚大なダメージ(回復中)、疲労(極大)、魔力消費(極大)、『喰種』
[装備]高等部の制服
[道具]なし。
[思考・状況]
基本行動方針:誰が相手でも。どんなことをしてでも。聖杯を手に入れる。
1.――――。
[備考]
長谷川千雨とマスター契約を交わしました。
【長谷川千雨@魔法先生ネギま!】
[状態]魔力消費(中)、精神疲労(大)、右腕上腕部に抉傷。
[令呪]残り一画
[装備]なし
[道具]ネギの杖(血まみれ)
[金銭状況]それなり
[思考・状況]
基本行動方針:絶対に生き残り聖杯を手に入れる。
1.もう迷わない。何も振り返らない。
[備考]
この街に来た初日以外ずっと学校を欠席しています。欠席の連絡はしています。
C-5の爆発についてある程度の情報を入手しました。「仮装して救助活動を行った存在」をサーヴァントかそれに類する存在であると認識しています。他にも得た情報があるかもしれません。そこらへんの詳細は後続の書き手に任せます。
ランサー(金木研)を使役しています。
[状態]魔力消費(中)、精神疲労(大)、右腕上腕部に抉傷。
[令呪]残り一画
[装備]なし
[道具]ネギの杖(血まみれ)
[金銭状況]それなり
[思考・状況]
基本行動方針:絶対に生き残り聖杯を手に入れる。
1.もう迷わない。何も振り返らない。
[備考]
この街に来た初日以外ずっと学校を欠席しています。欠席の連絡はしています。
C-5の爆発についてある程度の情報を入手しました。「仮装して救助活動を行った存在」をサーヴァントかそれに類する存在であると認識しています。他にも得た情報があるかもしれません。そこらへんの詳細は後続の書き手に任せます。
ランサー(金木研)を使役しています。
| BACK | NEXT | |
| 029:願い潰しの銀幕 | 投下順 | 031:空の騎士 |
| 041:Send E-mail | 時系列順 | 031:空の騎士 |
| BACK | 登場キャラ | NEXT |
| 024:マギステル・マギ | ランサー(金木研) | 044:禍津血染花 |
| 029:願い潰しの銀幕 | 霧嶋董香 | |
| アーチャー(ヴェールヌイ) | ||
| 028:迷いの園-Guilt- | 長谷川千雨 | 044:禍津血染花 |
| ライダー(パンタローネ) |