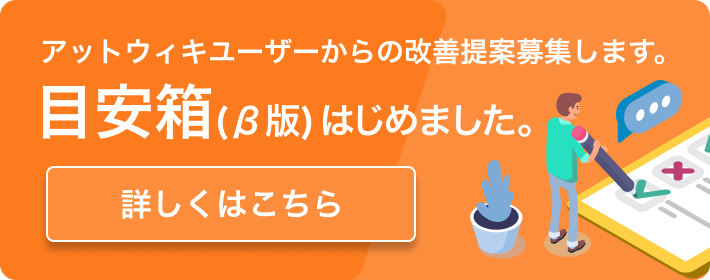▼ ▼ ▼
「何十年ぶりになるんだろうな。なあ、抜刀斎」
「知らんよ、そのような些末事など」
「知らんよ、そのような些末事など」
漆黒の闇の中。煌々と輝きを湛える月が見下ろすビルディングの屋上にて、二人は向かい合った。
全てが凪いでいた。両者は構えを取ることもせず、ただ在るがまま、静謐な面持ちで互いを見つめていた。
全てが凪いでいた。両者は構えを取ることもせず、ただ在るがまま、静謐な面持ちで互いを見つめていた。
時を超えた邂逅か、それとも因縁がもたらした悪戯か。
この再会にどのような意図が絡んでいるのか、あるいは単なる偶然か。
どちらでも良かった。ただ、この場に人斬り抜刀斎・緋村抜刀斎と、元新撰組三番隊組長・斎藤一が存在する。二人にとっては、その事実だけで十分であった。
この再会にどのような意図が絡んでいるのか、あるいは単なる偶然か。
どちらでも良かった。ただ、この場に人斬り抜刀斎・緋村抜刀斎と、元新撰組三番隊組長・斎藤一が存在する。二人にとっては、その事実だけで十分であった。
既に加藤鳴海の姿はない。新たに発生したサーヴァントの気配、それに対処するため二人の下を離れている。
それでもいいと、二人は思った。
何故なら分かるからだ。剣客として培った洞察力、そして生前における記憶によって。
あれはある意味で"流浪人緋村剣心"と同類の男であると。
それでもいいと、二人は思った。
何故なら分かるからだ。剣客として培った洞察力、そして生前における記憶によって。
あれはある意味で"流浪人緋村剣心"と同類の男であると。
最初の会敵時、あの男はマスターである音無結弦や仲村ゆりを狙えた立場にあってなお、それを実行することはなかった。実力が足りない、あるいは迂遠な策、そのどちらもでもない。奴は"そういう"人間なのだ。
だから放置する。人を殺せない敵など、今の二人にとって何ら害にならないのだから。
だから放置する。人を殺せない敵など、今の二人にとって何ら害にならないのだから。
「緋村抜刀斎、稀代の人斬りにして伝説の剣客。貴様の強さは特に多く戦った新撰組 が最も深く知っている。
そして貴様は、よりにもよって"その姿"で現界した」
「ならばどうする、ここで殺すか」
「愚問だ」
そして貴様は、よりにもよって"その姿"で現界した」
「ならばどうする、ここで殺すか」
「愚問だ」
ただ一言を以て返す。それ以上のやり取りなど、この二人には不要だった。
何故この男が流浪人・緋村剣心ではなく人斬り抜刀斎として現界したのか、その理由については最早問うまい。
戦士とは、如何なる不条理な現実をも疑わぬもの。ただ認識し、対処するのみ。
何故この男が流浪人・緋村剣心ではなく人斬り抜刀斎として現界したのか、その理由については最早問うまい。
戦士とは、如何なる不条理な現実をも疑わぬもの。ただ認識し、対処するのみ。
「あの日の続きだ、抜刀斎。貴様の抱く人斬りとしての性も、築き上げた不敗の伝説も、一切を抱えたまま地獄へ落ちることは許さん」
思い出すは血風渦巻く京の都か、武士が生きそして死んだ最後の戦場たる鳥羽・伏見の戦いか。
戦乱の幕末にて幾度も出会い、斬り合い、そして決着は付かず十年の時が無情に流れた。
その果てに彼らは再び出会い、しかしその時には既に「人斬り抜刀斎」は死に絶えていた。
戦乱の幕末にて幾度も出会い、斬り合い、そして決着は付かず十年の時が無情に流れた。
その果てに彼らは再び出会い、しかしその時には既に「人斬り抜刀斎」は死に絶えていた。
腰の刀に手をかける。抑え込まれた闘気は臨界点寸前であり、最早収まることもない。
「現世 へ置いてゆけ。せめてもの手向けだ、俺の渾身を以て太刀打ち仕ろう」
「見上げた大言壮語だ、斎藤。ならばその首級を貰い受ける」
「見上げた大言壮語だ、斎藤。ならばその首級を貰い受ける」
斎藤と呼ばれた剣鬼と、抜刀斎と呼ばれた剣鬼。
旧縁持つ二人はそれで対話を切り、斎藤は刃を抜き放ち、抜刀斎は柄へと手をかけた。
最早二度と共有できまいと悟っていた、悪・即・斬の正義を共に抱いて。
あの日つけられなかった決着を、ここに結実させるのだ。
旧縁持つ二人はそれで対話を切り、斎藤は刃を抜き放ち、抜刀斎は柄へと手をかけた。
最早二度と共有できまいと悟っていた、悪・即・斬の正義を共に抱いて。
あの日つけられなかった決着を、ここに結実させるのだ。
斎藤一は腰を深く落とし、切っ先を前方へ向けて構えた。一撃必殺、敵を突き殺す両手平突の構えである。
対する抜刀斎は納刀したまま中段に手をかける居合の構えだ。一刀両断、敵を斬り伏せる抜刀術の構えである。
対する抜刀斎は納刀したまま中段に手をかける居合の構えだ。一刀両断、敵を斬り伏せる抜刀術の構えである。
そうして相対し。
両者は凝固した。
両者は凝固した。
時が徒に流れ過ぎゆく。
手に汗握るとはこのことか、唖然と見守るとはこのことか。
しかしこの場に一切の立会人はおらず、故にただ時間だけが過ぎてゆく。
手に汗握るとはこのことか、唖然と見守るとはこのことか。
しかしこの場に一切の立会人はおらず、故にただ時間だけが過ぎてゆく。
両者が静止する意味、それは武芸に傾倒した者ならば容易に洞察することが可能であり、故に勝負の行方はこの時点では分からない。
両者いずれも、意図するところは明らかである。
両者いずれも、意図するところは明らかである。
中段に構えた斎藤は、刺突にて敵手の喉元を狙う。
この構えより斬撃せんとすれば、剣を振りかぶる余計な動作が入用となり、敵に遅れを取るため、まず突く以外の選択肢はないと言っていい。
そして脆弱な人間と違い、魔力を形として現界したサーヴァントにはかつての常道……すなわち、一寸の切れ込みさえ入れれば即死するという常識は時に通じなくなっている。
ならば狙うは破壊が死に繋がる急所のみ。すなわち脳髄、心の臓、あるいは首か。腕で庇える胴体部、そして狙いの付けにくい頭部と違い、その最も致命的たる弱点が喉周りの隙。これを突くに如かず。
この構えより斬撃せんとすれば、剣を振りかぶる余計な動作が入用となり、敵に遅れを取るため、まず突く以外の選択肢はないと言っていい。
そして脆弱な人間と違い、魔力を形として現界したサーヴァントにはかつての常道……すなわち、一寸の切れ込みさえ入れれば即死するという常識は時に通じなくなっている。
ならば狙うは破壊が死に繋がる急所のみ。すなわち脳髄、心の臓、あるいは首か。腕で庇える胴体部、そして狙いの付けにくい頭部と違い、その最も致命的たる弱点が喉周りの隙。これを突くに如かず。
対する抜刀斎は、居合中段にて相手の首元を狙う。
そこもまた構造的に守りきれぬ隙であり、放つ角度をやや上向きに寝かせ斬り込めば、頭と胴体を繋ぐ細い首筋へ刃先を打ち入れることが叶う。
他の箇所を狙おうとすれば、肉体に備わる諸々の器官が邪魔となり余計な動作が必要となる。それは敵に対しての遅れとなって現れるだろう。
そこもまた構造的に守りきれぬ隙であり、放つ角度をやや上向きに寝かせ斬り込めば、頭と胴体を繋ぐ細い首筋へ刃先を打ち入れることが叶う。
他の箇所を狙おうとすれば、肉体に備わる諸々の器官が邪魔となり余計な動作が必要となる。それは敵に対しての遅れとなって現れるだろう。
斯様に両者共、攻め手は決している。
しかし両者共、不動にて時を送る。
それは両者共、攻め手に併せて受け手を用意しており、対敵にその備えがあることを疑っていなかったからである。
しかし両者共、不動にて時を送る。
それは両者共、攻め手に併せて受け手を用意しており、対敵にその備えがあることを疑っていなかったからである。
斎藤が牙突にて打ち込めば―――
抜刀斎は僅かに身を捻るのみでその鋭鋒を躱し、反転しつつ遠心力を利用してその後頭部へと抜刀し、勝負は決するであろう。
抜刀斎は僅かに身を捻るのみでその鋭鋒を躱し、反転しつつ遠心力を利用してその後頭部へと抜刀し、勝負は決するであろう。
抜刀斎が先に斬り込めば―――
斎藤は一歩退いて剣撃を外し、すぐさま跳ね戻って宿敵を刺し殺すであろう。
斎藤は一歩退いて剣撃を外し、すぐさま跳ね戻って宿敵を刺し殺すであろう。
攻め手が必殺ならば受け手もまた必殺。
互いに対敵の手の内を知りつくし、読みつくし、故に動けず、戦況は膠着する。
かかる情勢、勝負はすなわち、体力気力の削り合い。
斎藤と抜刀斎、対峙する二者は今、敵を一足一刀にて仕留め得る体勢と敵の微細な変化をも見逃さぬ集中力、その二つを維持しながら向かい合っている。
ならばこその膠着。
互いに対敵の手の内を知りつくし、読みつくし、故に動けず、戦況は膠着する。
かかる情勢、勝負はすなわち、体力気力の削り合い。
斎藤と抜刀斎、対峙する二者は今、敵を一足一刀にて仕留め得る体勢と敵の微細な変化をも見逃さぬ集中力、その二つを維持しながら向かい合っている。
ならばこその膠着。
これが両者の心身に多大な負荷をかけることは論ずるまでもない。
渓谷を綱渡りするにも等しい過酷さである。
やがては一方が力尽き、構えを崩す。
その時もう一方が余力を残していたならば、即座にその崩れを狙って攻めかかり、勝利者となるだろう。
渓谷を綱渡りするにも等しい過酷さである。
やがては一方が力尽き、構えを崩す。
その時もう一方が余力を残していたならば、即座にその崩れを狙って攻めかかり、勝利者となるだろう。
元新撰組隊士、斎藤一。
人斬り抜刀斎、緋村剣心。
人斬り抜刀斎、緋村剣心。
いずれがいずれの役を背負うか。
時がまた流れ、戦いは静粛なまま、閉幕へと向かい―――
「―――ッ!」
あるいは、それは同時だったか。
斎藤と抜刀斎は共に勝負に出た。強い息吹を吐き出しつつ、己の体を前方へと撃ち出す!
互いに必殺の構え。さてこそと一瞬の遅れなく、互いは互いの攻撃へと反応した。
斎藤と抜刀斎は共に勝負に出た。強い息吹を吐き出しつつ、己の体を前方へと撃ち出す!
互いに必殺の構え。さてこそと一瞬の遅れなく、互いは互いの攻撃へと反応した。
けれど、いいや必然か。
機は未だ熟してはおらず、互いの必殺はしかし必勝とは成り得ない。
機は未だ熟してはおらず、互いの必殺はしかし必勝とは成り得ない。
状況は定まっていない。不確定のまま繰り出した二つの必殺は、虚しく宙を空振り、あるいは儚く宙を空撃ちするのみ。
勝負は振出へと戻る。
そうであると、思われたが……
勝負は振出へと戻る。
そうであると、思われたが……
「ッ!」
前方へと渾身の力で突きいれられた斎藤の突きは抜刀斎を捉えることなく空を穿ち、しかし中空にて軌道を変え眼下の抜刀斎へと斬りかかる。
これぞ斎藤が必殺、牙突の神髄。刺突を外されても間髪入れずに薙ぎの攻撃へと転換できる。戦術の鬼才土方歳三が考案した平刺突に死角はない。
これぞ斎藤が必殺、牙突の神髄。刺突を外されても間髪入れずに薙ぎの攻撃へと転換できる。戦術の鬼才土方歳三が考案した平刺突に死角はない。
対する抜刀斎の剣閃は斎藤を捉えることなく流れゆき、しかしそれを追随する後追いの一閃が遅れて襲来した。
これぞ飛天御剣流が誇る二段抜刀術、双龍閃。抜刀が躱された無防備を補うために考案された鞘による疑似抜刀。
白刃の幻で敵を退かせ、その隙を追い、本命の一刀を繰り出す。
"呼吸外し"の術である。
これぞ飛天御剣流が誇る二段抜刀術、双龍閃。抜刀が躱された無防備を補うために考案された鞘による疑似抜刀。
白刃の幻で敵を退かせ、その隙を追い、本命の一刀を繰り出す。
"呼吸外し"の術である。
初めの必殺は共に外れた。しかし必殺が一つきりなどとは誰も言っていない。
第二撃の剣閃は、果たして互いの首元を狙い―――
第二撃の剣閃は、果たして互いの首元を狙い―――
「やはり、強いな。抜刀斎」
「……」
「……」
結果は相討ち掠りもせず……勝敗は未だ定まらない。
斬り下ろされた斬撃は鞘で防がれ、斬り上げた鞘が打ち据えるは刃のみ。そのどちらも、敵手の体を貫くには至っていない。
共に伯仲、互角の勝負。幾度も戦い、戦い、戦い続けてその度に生き残り続けた両者は、互いの手の内を知り尽くしているが故にその刃を身に受けることがない。
斬り下ろされた斬撃は鞘で防がれ、斬り上げた鞘が打ち据えるは刃のみ。そのどちらも、敵手の体を貫くには至っていない。
共に伯仲、互角の勝負。幾度も戦い、戦い、戦い続けてその度に生き残り続けた両者は、互いの手の内を知り尽くしているが故にその刃を身に受けることがない。
「分かってはいたが、簡単には死ねんようだ。俺も、貴様も」
「それこそ分かりきったことだろう。何度戦い、何度殺し合ったと思っている」
「違いない」
「それこそ分かりきったことだろう。何度戦い、何度殺し合ったと思っている」
「違いない」
この程度でどちらかが倒れる程度ならば、そもそも彼らは宿敵になどなってはいない。
呼吸の読み合い、技の妙。その粋を尽くしての決闘すらも彼らには不足というのか。
呼吸の読み合い、技の妙。その粋を尽くしての決闘すらも彼らには不足というのか。
「ならば、行儀のいい行いはここで終わりにするとしよう」
「……そうか、お前はそのつもりか」
「ああ、そうだとも。俺と貴様の決着に、これほど相応しいものはあるまい」
「……そうか、お前はそのつもりか」
「ああ、そうだとも。俺と貴様の決着に、これほど相応しいものはあるまい」
故にこそ、彼らが死地を決するには最早人の業では到底足りない。
人を超え、剣客となりて、果てにサーヴァント として現界し、それでも足りぬと吼え猛る。
ああ、そのザマは、まるで。
人を超え、剣客となりて、果てに
ああ、そのザマは、まるで。
「ここからは死合いではなく、喰らい合いだ」
―――まるで、鬼畜生のようではないか。
▼ ▼ ▼
『大嘘吐き 』
『きみの"殺意"を【なかった】ことにした』
この世のあらゆる"負"が凝縮したかのような存在が、窓辺に腰かけ嗤っていた。その影は人の姿をしていたが、けれどあやめには、それが人であるとは到底思えなかった。
見るだけで、聞くだけで、存在感を感じ取るだけで脊椎を掴まれたかのようにおぞましい。発する圧が明らかに異常だった。
荒唐無稽な悪夢を現実に映しだし、臓物と糞尿を混ぜて煮詰めればこのようなものが出来上がるかもしれない。人型をとっていることさえ、人間に対する冒涜だった。
見るだけで、聞くだけで、存在感を感じ取るだけで脊椎を掴まれたかのようにおぞましい。発する圧が明らかに異常だった。
荒唐無稽な悪夢を現実に映しだし、臓物と糞尿を混ぜて煮詰めればこのようなものが出来上がるかもしれない。人型をとっていることさえ、人間に対する冒涜だった。
不幸にもそれを直視してしまったあやめは、当然の如く精神ごと肉体が硬直した。あまりにも強烈な嫌悪感から、逆に彼から目を逸らすことができない。
それは、かつて彼女が慣れ親しんだ異界の風景とも似て。
しかし、どこかが決定的に違う負の存在であった。
それは、かつて彼女が慣れ親しんだ異界の風景とも似て。
しかし、どこかが決定的に違う負の存在であった。
『似合わないことはするもんじゃないぜカワイコちゃん。そういうのは過負荷 の領分だ』
その言葉を境に我を取り戻し、しかし次の瞬間には再びの忘我があやめを襲った。
「な、なんで……」
気付けば、本田未央の首にかけていた手が、その力を失っていた。
指一本動かすことができなかった。いや、正確には「動かす気になれなかった」と言うべきか。
指一本動かすことができなかった。いや、正確には「動かす気になれなかった」と言うべきか。
それも当然である。何故なら、先ほどまでの彼女を突き動かしていたのは"殺意"であるのだから。
殺さねばという使命感はあった。殺して彼に報いなければという気持ちもあった。けれど、肝心要の「殺そうとする意志」は、何故か根こそぎ失われてしまっていた。
殺さねばという使命感はあった。殺して彼に報いなければという気持ちもあった。けれど、肝心要の「殺そうとする意志」は、何故か根こそぎ失われてしまっていた。
あやめは極めて善良な少女である。義憤であれ、使命感であれ、報いたいと思う心であれ、そんなもので人を殺せるほど、彼女は人道から外れた存在ではない。
この聖杯戦争に参加したサーヴァントにあって、彼女はある意味では最も人に似つかず、しかしある意味では最も人に近しい存在であったのだ。
この聖杯戦争に参加したサーヴァントにあって、彼女はある意味では最も人に似つかず、しかしある意味では最も人に近しい存在であったのだ。
「ッ! 未央チャン!」
この場にいない新たな第三の声が、病室内に響いた。
悠然と窓に腰かける男を押しのけるようにして現れたそれは、眼鏡をかけた利発そうな少女だった。年の頃は恐らく本田未央と同じほどか。いっそ哀れなほどにやつれ憔悴した様子で、しかし万感の思いが籠った声を上げ、彼女は病室内に転がり込んだ。
この時既に、本田未央は意識を取り戻していた。肺に大量の空気を取り込むためか激しく咳き込み、酸欠により白濁としていた思考も徐々に纏まりつつある。そんな彼女は、悲壮な様子で転がり込む少女をぽかんとした様子で見つめ、次いで自分の状況すらも呑みこめない様子で首を傾げていた。
悠然と窓に腰かける男を押しのけるようにして現れたそれは、眼鏡をかけた利発そうな少女だった。年の頃は恐らく本田未央と同じほどか。いっそ哀れなほどにやつれ憔悴した様子で、しかし万感の思いが籠った声を上げ、彼女は病室内に転がり込んだ。
この時既に、本田未央は意識を取り戻していた。肺に大量の空気を取り込むためか激しく咳き込み、酸欠により白濁としていた思考も徐々に纏まりつつある。そんな彼女は、悲壮な様子で転がり込む少女をぽかんとした様子で見つめ、次いで自分の状況すらも呑みこめない様子で首を傾げていた。
「未央チャン、生きて……生きてた……私、もう駄目だとばっかり……」
「……えぇっと、みくちゃん? なんでそんな泣いて……
ていうか、ここ病院? 何があって……」
「……えぇっと、みくちゃん? なんでそんな泣いて……
ていうか、ここ病院? 何があって……」
訳も分からないといった風体で、未央は周囲を見渡し。
「……」
『……』
「……」
『やあ』
『……』
「……」
『やあ』
やっほーと手を振る男を見た瞬間、未央は再びその意識を手放した。白目を剥いてベッドの上に倒れ込む。
過負荷を目撃したことによる精神の許容量の限界、お手本のような失神であった。
過負荷を目撃したことによる精神の許容量の限界、お手本のような失神であった。
『あっれーおかしいなぁ、僕は一応彼女を二度も助けた恩人のはずなのになー。
怖がられる要素なんてどこにもないよ、ねえみくにゃちゃん?』
「…………。
……もういいよ。ルーザーはそういうのだって十分過ぎるくらいに分かったから」
怖がられる要素なんてどこにもないよ、ねえみくにゃちゃん?』
「…………。
……もういいよ。ルーザーはそういうのだって十分過ぎるくらいに分かったから」
涙を拭い、微かに嗚咽を漏らしながらも、けんもほろろなみくの態度に、男―――ルーザーは芝居がかった態度で嘆息していた。
しかしそんなみくの態度も、どこか柔らかい。それも当然の話というべきか、今まで死んだと思われた本田未央が、みくの友人たる彼女がなんと生きていたというのだから。
理由は分からない。推測するならあの白銀のサーヴァントの力か。ともかく望外の奇跡にみくは涙ぐみ、それを見つめる球磨川は何とも形容のし難い表情をしていた。
しかしそんなみくの態度も、どこか柔らかい。それも当然の話というべきか、今まで死んだと思われた本田未央が、みくの友人たる彼女がなんと生きていたというのだから。
理由は分からない。推測するならあの白銀のサーヴァントの力か。ともかく望外の奇跡にみくは涙ぐみ、それを見つめる球磨川は何とも形容のし難い表情をしていた。
『まあ、そっちはハッピーエンドめでたしめでたしってことでいいとしてさ。
それじゃあこいつどうしよっか。あんま時間かけてもしょうがないしねぇ』
「あう……!」
それじゃあこいつどうしよっか。あんま時間かけてもしょうがないしねぇ』
「あう……!」
言うが早いか、球磨川は未だ呆然と座り込んでいたあやめの小柄な体躯を片手で掴みあげた。苦悶の声をあげる少女を嗤いながら睥睨する様は、何の慈悲もないように見える。
彼ら主従がこの場を訪れたのは、決して偶然の産物ではない。無論多くのサーヴァントの気配……斎藤一や緋村抜刀斎、加藤鳴海など……を感じ取ったということもあるが、それ以上に彼らは「あやめ」個人の気配を追跡してここまで来たのだ。
無論、ルーザーたる球磨川禊に気配察知系統のスキルなどなく、そもそも過負荷の王たる彼がそんな有用な手段を持つことも用いることもあり得ない。ならば何故彼女の気配が分かったかと言えば、それはあやめの持つ怪異としての気配が"限りなく過負荷に近く、そして限りなく遠い"異質なものであるからだ。
無論、ルーザーたる球磨川禊に気配察知系統のスキルなどなく、そもそも過負荷の王たる彼がそんな有用な手段を持つことも用いることもあり得ない。ならば何故彼女の気配が分かったかと言えば、それはあやめの持つ怪異としての気配が"限りなく過負荷に近く、そして限りなく遠い"異質なものであるからだ。
あやめというサーヴァントは、元は単なる村娘の一人でしかない。
何ら超常的な力を持たず、武芸にも魔術にも思想にも通じず、まして世間一般での知名度や信仰などあるはずもなく。本来であるならば英霊の座に押し上げられるなどありえない普通 こそがあやめという少女だ。
ならば彼女の一体何がサーヴァントたるに相応しい超常と成り得るのかと言えば、それは"怪異"の性質に他ならない。
あやめは忘れられた村娘である。より正確に言うならば、"異界への供儀として捧げられた娘"である。
異界に堕ちた彼女は、『彼等』によって"そう"成り果ててしまった存在なのだ。人間の心を保ちながら、しかし永遠に異形として在り続ける、『彼等』と同じモノに。
いわば後天的な形質変容である。普通 でしかなかったあやめは、しかし普通 の心を持ちながら、過負荷 とも悪平等 とも似て非なる怪異 へと変貌した。
何ら超常的な力を持たず、武芸にも魔術にも思想にも通じず、まして世間一般での知名度や信仰などあるはずもなく。本来であるならば英霊の座に押し上げられるなどありえない
ならば彼女の一体何がサーヴァントたるに相応しい超常と成り得るのかと言えば、それは"怪異"の性質に他ならない。
あやめは忘れられた村娘である。より正確に言うならば、"異界への供儀として捧げられた娘"である。
異界に堕ちた彼女は、『彼等』によって"そう"成り果ててしまった存在なのだ。人間の心を保ちながら、しかし永遠に異形として在り続ける、『彼等』と同じモノに。
いわば後天的な形質変容である。
過去の邂逅において、球磨川が彼女を一瞬でも過負荷と見間違えてしまったのはそれが理由である。そして、当然ながら怪異である彼女は通常のサーヴァントとは異なる過負荷に近しい気配を放ち、それを隠蔽するための気配遮断スキルは最早球磨川には一切機能していない。
遠隔ならばともかく、一度気配の感知圏内に捉えてしまえば追跡は容易であった。冬木に並み居るサーヴァントの中で、唯一球磨川だけが成し得る捕獲劇だったのだ。
……本田未央が生きてそこにいるとは、流石に球磨川も想定してはいなかったけど。
遠隔ならばともかく、一度気配の感知圏内に捉えてしまえば追跡は容易であった。冬木に並み居るサーヴァントの中で、唯一球磨川だけが成し得る捕獲劇だったのだ。
……本田未央が生きてそこにいるとは、流石に球磨川も想定してはいなかったけど。
『僕としては、みくにゃちゃんの言う"音無結弦の真意"を聞きだすまでは、まあ穏便に済ませてやろうって考えてたんだけどね。
でも本田ちゃんが生きてた以上、もうそんなまだるっこしい真似はナシだ。許すも許さないもないよ、【またあんなことになる】前に不穏な芽は潰しておくべきだよね』
「ルーザー、それ……」
『ああでも困ったな、今ここで殺したら色々と"良くない"ことになりそうだ。
あー、人手が足りないなぁ。どっかに都合よく動かせる駒でも落ちてないかなぁ』
でも本田ちゃんが生きてた以上、もうそんなまだるっこしい真似はナシだ。許すも許さないもないよ、【またあんなことになる】前に不穏な芽は潰しておくべきだよね』
「ルーザー、それ……」
『ああでも困ったな、今ここで殺したら色々と"良くない"ことになりそうだ。
あー、人手が足りないなぁ。どっかに都合よく動かせる駒でも落ちてないかなぁ』
躊躇いがちなみくの言葉を余所に、球磨川は勝手気ままにあやめを掴みあげながらあーでもないこーでもないと一人で盛り上がっている。あやめは愚か、彼のマスターであるみくですら、彼が一体何を考え何を望んでいるのか理解できなかった。
すると、中空を向いて思案するそぶりを見せていた球磨川の目が、突如として細められた。瞳に宿る底の無い空洞じみた虚構の闇は、ぐるぐると渦巻いて何か恐ろしいものでも映し出すかのように揺れていた。
すると、中空を向いて思案するそぶりを見せていた球磨川の目が、突如として細められた。瞳に宿る底の無い空洞じみた虚構の闇は、ぐるぐると渦巻いて何か恐ろしいものでも映し出すかのように揺れていた。
『……そうだね、そういやあいつがいるんだっけ。ちょうどいいや』
「ちょっとルーザー、さっきから何を……」
『気をつけなみくにゃちゃん、さっきぶりに"あいつ"が来るよ』
「ちょっとルーザー、さっきから何を……」
『気をつけなみくにゃちゃん、さっきぶりに"あいつ"が来るよ』
忠告するかのような球磨川の言葉と同時、病室と廊下を隔てるスライド式の扉が思い切り押し開かれた。
バン、という大きな音と共に飛び込んできたのは、みくや球磨川よりも一回りも二回りも巨大な、鍛え上げられた偉丈夫の姿。
しろがねのサーヴァント、加藤鳴海であった。
バン、という大きな音と共に飛び込んできたのは、みくや球磨川よりも一回りも二回りも巨大な、鍛え上げられた偉丈夫の姿。
しろがねのサーヴァント、加藤鳴海であった。
「てめえは……!」
焦燥した表情で病室へと駆けこんだ鳴海は、球磨川の姿を認めるや、即座にその表情を警戒と困惑の色に染めた。覚えのある相手であったが、敵かも味方かも分からないからだ。いいや、そもそも鳴海は球磨川のことを敵としても味方としても関わり合いになりたくないとさえ考えていた。
困惑はすぐさま敵意となり、鳴海はその拳を迎撃に固めた。球磨川はただ嗤うだけだ。
困惑はすぐさま敵意となり、鳴海はその拳を迎撃に固めた。球磨川はただ嗤うだけだ。
『やあカンフーくん、お互い生きてたようで何よりだよ!
ところでなんでそんなカッカしてんの? カルシウム足りてる?』
「てめえ何しに来やがった……!
いやそれはどうでもいい、てめえは俺のマスターから離れやがれ……!」
ところでなんでそんなカッカしてんの? カルシウム足りてる?』
「てめえ何しに来やがった……!
いやそれはどうでもいい、てめえは俺のマスターから離れやがれ……!」
激昂するその様に、球磨川の背後で事の推移を見守っていたみくが思わず恐慌の声を上げた。鳴海はそれを見て一瞬だけたじろぐも、すぐさま元の狂相を取り戻して球磨川へと詰め寄る。
鳴海の丸太のように太い腕が、軽々と球磨川を掴みあげた。そして威嚇するように顔を突き合わせる。敵意に相貌を歪ませる鳴海とは対照的に球磨川はどこまでも涼しい顔だ。
鳴海の丸太のように太い腕が、軽々と球磨川を掴みあげた。そして威嚇するように顔を突き合わせる。敵意に相貌を歪ませる鳴海とは対照的に球磨川はどこまでも涼しい顔だ。
『ふーん、きみはマスターの恩人に対してそんなことするんだ。わー幻滅ぅー、カッコ悪いなぁカンフーくん』
「黙りやがれ、それとこれとは話が別だ。どうにもてめえは信用ならねえんだよ……!」
「黙りやがれ、それとこれとは話が別だ。どうにもてめえは信用ならねえんだよ……!」
それ以上の問答は無用とばかりに、鳴海はもう片方の腕を振り上げる。そのまま、球磨川の顔面を打ち据えようと―――
『ところでカンフーくん、これを見てくれ。こいつをどう思う?』
「な――――ッ!?」
「な――――ッ!?」
その拳を直進上、すなわち球磨川自身の顔の高さに、彼は"それ"を持ち上げ"紹介"した。
「何の前触れもなく」「突如として出現した少女」を目の前に、鳴海は混乱と驚愕の極みに陥り、思わずその手を止めてしまい。
「何の前触れもなく」「突如として出現した少女」を目の前に、鳴海は混乱と驚愕の極みに陥り、思わずその手を止めてしまい。
『だから甘えってんだよ、きみは』
致命的な隙を晒し、がら空きとなった鳴海の胴体に、一本の長大な螺子が突き刺さった。
鳴海の体は一瞬大きく痙攣し、しかしすぐに静止して崩れ落ちるように動かなくなった。鳴海の剛腕より解放された球磨川は、やだなぁと白々しく嘯きながら軽く埃を払うように学生服をはたいた。
鳴海の体は一瞬大きく痙攣し、しかしすぐに静止して崩れ落ちるように動かなくなった。鳴海の剛腕より解放された球磨川は、やだなぁと白々しく嘯きながら軽く埃を払うように学生服をはたいた。
『こうまでみくにゃちゃんを狙わなかったことからも分かってたことだけど、改めて言っておこうか。
きみの甘さ、きみの弱さは子供を殺せないということ。いや、それどころか傷つけられないってところかな?
サーヴァントとしちゃ、つくづく甘い』
『でもその甘さ、嫌いじゃないぜ』
きみの甘さ、きみの弱さは子供を殺せないということ。いや、それどころか傷つけられないってところかな?
サーヴァントとしちゃ、つくづく甘い』
『でもその甘さ、嫌いじゃないぜ』
鋭く指を突きつけて、如何にも格好つけたポーズで球磨川は言い放った。残念なことに、それを真面目に見聞きした者は誰一人として存在しなかった。
「る、ルーザー……それ、どうしたの。
……殺しちゃったの?」
『まっさかぁ、人畜無害かつ善良な一般市民の僕がそんな物騒なことするわけないじゃん』
……殺しちゃったの?」
『まっさかぁ、人畜無害かつ善良な一般市民の僕がそんな物騒なことするわけないじゃん』
みくのほうへと振り返り、大仰な手振りで力説した。まるで説得力がない。
『ただ、ねえ』
『今のままじゃ碌に話も聞いてくれないだろうからさ』
『ちょこっとだけ、大人しくしてもらおうかなって』
『本当にそれだけさ』
『今のままじゃ碌に話も聞いてくれないだろうからさ』
『ちょこっとだけ、大人しくしてもらおうかなって』
『本当にそれだけさ』
「……それだけ?」
『それだけ。この螺子は特注品でね、殺すどころか掠り傷一つ付けることもできない、武器としちゃ【負】出来な代物なんだ』
そう言うと、球磨川は項垂れて蹲る鳴海の髪を掴むと、無理やりにその顔を上げた。
現れたのは、生気というものがこそげ落ちたような、鳴海の顔。
現れたのは、生気というものがこそげ落ちたような、鳴海の顔。
『でもその代わり、こういう時には役立ってくれるよ。何せどんな奴だって【僕】の位置まで引きずり下ろしてやれるんだからね』
そう語る球磨川の目の前で。
呆けたような面をした鳴海が、初めて口を開いた。
呆けたような面をした鳴海が、初めて口を開いた。
『なんだよお前、面倒臭えなぁ』
「……は?」
『ほら、見なよみくにゃちゃん。まるで僕みたいに露骨に最低に陰気溌剌になってるでしょ!』
「なにこれ、気持ち悪……」
『ほら、見なよみくにゃちゃん。まるで僕みたいに露骨に最低に陰気溌剌になってるでしょ!』
「なにこれ、気持ち悪……」
鳴海が口にした、まるで球磨川のような負愉快な口調と、一目で分かる異常事態に、みくはあからさまにドン引きしていた。
『却本作り 。
安心大嘘吐きに続く、僕のもう一つの宝具さ』
『この螺子で貫かれた者は、何もかもが僕と同じになる。
強さ、知性、感情、思想、あらゆるものが僕まで堕ちる。何とも使い勝手の悪い、僕にお似合いの欠陥能力さ』
『ま、今回のは一時的なものに留めておくつもりだけどね』
安心大嘘吐きに続く、僕のもう一つの宝具さ』
『この螺子で貫かれた者は、何もかもが僕と同じになる。
強さ、知性、感情、思想、あらゆるものが僕まで堕ちる。何とも使い勝手の悪い、僕にお似合いの欠陥能力さ』
『ま、今回のは一時的なものに留めておくつもりだけどね』
言うや否や、球磨川は鳴海に顔を近づけ、言った。
『さて、大人しくなったところで講義の時間だ。今から言うことをよーく聞けよ?』
その顔は、まるで面白い悪戯を思いついた子供のように、なんとも愉快気な笑みに彩られていた。
▼ ▼ ▼
仲村ゆりと音無結弦は、既に満身創痍だった。
サーヴァントに襲撃されながら未だ存命しているという事実は、何も彼らが優秀であるとか、あるいは幸運であるということを意味していない。
むしろ、彼らはこの上なく不運だったと言えるだろう。
生かさず、殺さず。
彼らを襲ったサーヴァントとは、そういった拷問めいた生殺しを愛する、生粋の加虐趣味者なのだから。
サーヴァントに襲撃されながら未だ存命しているという事実は、何も彼らが優秀であるとか、あるいは幸運であるということを意味していない。
むしろ、彼らはこの上なく不運だったと言えるだろう。
生かさず、殺さず。
彼らを襲ったサーヴァントとは、そういった拷問めいた生殺しを愛する、生粋の加虐趣味者なのだから。
「ぎ、ぃ……あ……!」
それは絶叫だった。
か細く、今にも途切れてしまいそうにか弱く、けれどそれは絶叫であった。辛うじて襲撃者にのみ聞こえる程度の絶叫。
ゆりの腹から絞り出される、最早大声を出す気力すら尽きた苦悶の声。
先刻まであった闊達な少女の面影は、もう何処にも残されていなかった。
か細く、今にも途切れてしまいそうにか弱く、けれどそれは絶叫であった。辛うじて襲撃者にのみ聞こえる程度の絶叫。
ゆりの腹から絞り出される、最早大声を出す気力すら尽きた苦悶の声。
先刻まであった闊達な少女の面影は、もう何処にも残されていなかった。
「プッククククク、もう終わりかいお嬢さん。駄目だね、張り合いってものがまるでないよ」
「ほら、もっと抵抗しなよ! このっ、このっ!」
「ほら、もっと抵抗しなよ! このっ、このっ!」
せせら笑う長身の影はキルバーンのものだ。彼は悠然と、余裕の表情でゆりを見下ろしている。ピロロは獲物の抵抗が無くなったことに不満なのか、倒れたゆりの頭を何度も蹴り上げていた。
ゆり達の抵抗は、キルバーンたちにしてみれば文字通りの兎狩りにしかならなかった。窮鼠は猫を噛むことはなく、そもそも彼我の戦力差を考えればキルバーンは猫どころか大型の肉食獣にも等しい。この顛末は順当どころか必然と言えるだろう。
ゆり達の抵抗は、キルバーンたちにしてみれば文字通りの兎狩りにしかならなかった。窮鼠は猫を噛むことはなく、そもそも彼我の戦力差を考えればキルバーンは猫どころか大型の肉食獣にも等しい。この顛末は順当どころか必然と言えるだろう。
「セイ、バー、あたしたちを……」
「おっと、そうはさせないよ」
「おっと、そうはさせないよ」
ごりっ、という鈍い音がして、声にもならないゆりの悲鳴。鎌の柄の先端で"軽く"ゆりの腕を突いたのだ。無論、絶妙なまでの手加減によりダメージと痛みだけを与えている。ちぎったり砕いたりなんて論外だ。だって"そんなもので死なれてもつまらないのだから"。
(くそ、こいつら……)
死神とその従者が悪趣味な遊びに興じる背後、音無は頭から血を流して蹲っていた。彼らは音無のことも遊びの対象にしていたが、もっぱら傷つけるのはゆりが中心であった。音無は知る由もなかったが、ゆりと彼らの間にある会敵の因縁が、ゆりに対する加虐を加速させていたのだ。
つまり音無は最低限痛めつけられただけで半ば無視されているようなものだったが、それが何らかの救いになるかと言えば、それは否だ。逃げるどころか、令呪を使う隙さえない。一度どころか二度三度と試して、その全てが失敗に終わっているのだから間違いなかった。こいつらは、自分たちを逃がす気など毛頭ないのだと。
つまり音無は最低限痛めつけられただけで半ば無視されているようなものだったが、それが何らかの救いになるかと言えば、それは否だ。逃げるどころか、令呪を使う隙さえない。一度どころか二度三度と試して、その全てが失敗に終わっているのだから間違いなかった。こいつらは、自分たちを逃がす気など毛頭ないのだと。
「あ~あ、つまんないの。ねえキルバーン、もういいからこいつら殺しちゃおうよ」
「ボクとしちゃもう少し弄びたかったんだけどねぇ。でもピロロが言うなら仕方ないかな。あんまり遊び過ぎるとサーヴァントが戻ってくるかもしれないしね」
「うんうん。遊ぶのは大事だけど、余裕を持つのはもっと大事だよ」
「ボクとしちゃもう少し弄びたかったんだけどねぇ。でもピロロが言うなら仕方ないかな。あんまり遊び過ぎるとサーヴァントが戻ってくるかもしれないしね」
「うんうん。遊ぶのは大事だけど、余裕を持つのはもっと大事だよ」
二人揃ってクスクスと嘲笑。キルバーンの爪先がゆりの体を蹴り上げ、無理やりに仰向けにする。
手に持つ鎌がくるりと回り、その刃先がゆりの首元へと突きつけられた。
手に持つ鎌がくるりと回り、その刃先がゆりの首元へと突きつけられた。
「それじゃあ名残惜しいけどさよならだ。バイバイ、可愛いお嬢さん」
そのまま、死神の鎌は円を描くように高く振り上げられて―――
「ま、待ってくれ……」
「うん?」
「うん?」
そこに待ったをかけたのは、他ならぬ音無であった。
傷む腹部を抑えながら、音無は立ち上がる。今そうしなければ自分たちはすぐさま殺されてしまうのだと分かったから、立ち上がらざるを得ない。
傷む腹部を抑えながら、音無は立ち上がる。今そうしなければ自分たちはすぐさま殺されてしまうのだと分かったから、立ち上がらざるを得ない。
「交渉を、させてくれ。俺達が知ってる情報を教える、だから……」
「見逃せ、と。いいねぇ、そうこなくちゃ」
「見逃せ、と。いいねぇ、そうこなくちゃ」
キルバーンは鎌持つ手を止め、話を聞く段となった。
首の皮一枚で、彼らは命の綱を繋いだ。
首の皮一枚で、彼らは命の綱を繋いだ。
そうして音無は、促されるままに訥々と今までのことを語った。
本田未央、前川みく、ネギ・スプリングフィールド。今までに自分が遭遇したマスターのこと。彼らが使役しているサーヴァントの情報。
それらを入念に、できるだけ長く、音無は説明した。
ゆりが出会ったマスターたちのことも語った。しかしこちらは、ほとんどが遭遇の場にキルバーンも関わっていたため、彼にとって有益な情報はほとんどなかった。唯一、キリヤ・ケイジというマスターのことだけは興味深そうに聞いていたが。
本田未央、前川みく、ネギ・スプリングフィールド。今までに自分が遭遇したマスターのこと。彼らが使役しているサーヴァントの情報。
それらを入念に、できるだけ長く、音無は説明した。
ゆりが出会ったマスターたちのことも語った。しかしこちらは、ほとんどが遭遇の場にキルバーンも関わっていたため、彼にとって有益な情報はほとんどなかった。唯一、キリヤ・ケイジというマスターのことだけは興味深そうに聞いていたが。
「なるほどねぇ……意外や意外、きみたちは中々に優秀なマスターだったみたいだ」
全てを聞き終えたキルバーンは、心底から愉快気な様子で頷いていた。
「学校、学校か。所詮は子供ばかりの環境と思ってたけど、結構な数のマスターが紛れ込んでいたみたいだね。これは今日の予定を入れ替える必要があるかな?」
「お人形がいっぱいの遊び場だね、キルバーン!」
「ああ、そうだねピロロ。準備が整ったら盛大に遊んでやろうか……ククククク……」
「お人形がいっぱいの遊び場だね、キルバーン!」
「ああ、そうだねピロロ。準備が整ったら盛大に遊んでやろうか……ククククク……」
「そして―――」
「きみもそろそろお終いだ」
「……く、そっ」
「……く、そっ」
キルバーンは嘲笑の相を浮かべ、ゆりと音無のほうへと振り返る。
空を裂く鎌が、不可思議な音色を立てて旋回した。
空を裂く鎌が、不可思議な音色を立てて旋回した。
「きみの魂胆なんて分かっていたよ……情報を引き換えに見逃されるなんて最初から期待していない、きみが狙っていたのは時間稼ぎだ。
セイバーか、それともきみのサーヴァントか。令呪も使えないきみたちは、だからサーヴァントが自発的に戻ってくるのを待っていたわけだ。
けど、アテが外れたみたいだねぇ……!」
「ッ、くそ!」
セイバーか、それともきみのサーヴァントか。令呪も使えないきみたちは、だからサーヴァントが自発的に戻ってくるのを待っていたわけだ。
けど、アテが外れたみたいだねぇ……!」
「ッ、くそ!」
跳ね飛ぶように駆け出そうとして、しかしあっさりと足を掬われ転倒する。
無様に顔から地面に突っ込み、音無は奇しくも倒れるゆりの隣へと投げ出された。
無様に顔から地面に突っ込み、音無は奇しくも倒れるゆりの隣へと投げ出された。
「最期くらいは潔くしたまえよ、坊や。
なに安心したまえ、隣のお嬢さんもすぐきみのところへ連れて行ってあげるからね」
なに安心したまえ、隣のお嬢さんもすぐきみのところへ連れて行ってあげるからね」
そうして、彼らの命を刈り取る鎌は振るわれた。
音無の目に映ったのは、見ることも叶わない速度の白刃と、その向こうに浮かぶ煌々とした月だった。
視界が真っ黒に染まる。
掴む感触が無くなる。
その最中。
音無の目に映ったのは、見ることも叶わない速度の白刃と、その向こうに浮かぶ煌々とした月だった。
視界が真っ黒に染まる。
掴む感触が無くなる。
その最中。
「―――たすけて」
スローモーションになった世界の中で。
失われゆく聴覚が、か細く囁かれた声を聞いたような。
そんな気がした。
失われゆく聴覚が、か細く囁かれた声を聞いたような。
そんな気がした。
▼ ▼ ▼
静寂の空間に刃が激突する反響音が間断なく響き渡る。道ならぬ道を、ビルディングで構築された石造りの森を、影も捉えきれぬ何者かが駆け抜け、跳ね合い、颶風となりて相交わる。
影が交錯する度に散らすは刃鳴、舞うは剣弧。煌めき光るは刀刃に映る月光か。
三次元空間を縦横無尽に渡り歩き、そこかしこで激突する様は天狗かはたまたその化身か。
地に足つける人とは思えず、中空にて舞うは縮地の業なり。塔や壁すら彼らにとっては主戦場、今は懐かしき戦場にて踏みしめる土の感触である。
影が交錯する度に散らすは刃鳴、舞うは剣弧。煌めき光るは刀刃に映る月光か。
三次元空間を縦横無尽に渡り歩き、そこかしこで激突する様は天狗かはたまたその化身か。
地に足つける人とは思えず、中空にて舞うは縮地の業なり。塔や壁すら彼らにとっては主戦場、今は懐かしき戦場にて踏みしめる土の感触である。
―――彗星となりて散る火花。閃光となった刃撃の逢瀬が、再び対となって両雄の間で灼光する。
苛烈さは嘗ての比に非ず。互いの機を読み一刀のみを繰り出す剣客同士の構図は崩れ、今は共に二体の修羅。繰り出すは幾重に織り成す剣刃乱舞、これぞ悪鬼羅刹の喰らい合いなり。
剣閃、乱れ飛びて剣戟と化し―――
剣戟、狂い踊りて剣嵐と成る―――
よって双極、乱れ狂いて仕手と化し、血煙渦巻く死合とならん。
寄越せ、寄越せ、その首寄越せと刃が血肉を求め打ち震える。
剣に宿るは純なる殺意。修羅道を彩る絢爛の血道。ひとたび鞘走れば散華なしに戻りはしない。
一刀一撃、必殺の領域に突入している。音速を遥か超越した斬撃の応酬は、まるでよくできた殺陣のようでもあった。
一刀一撃、必殺の領域に突入している。音速を遥か超越した斬撃の応酬は、まるでよくできた殺陣のようでもあった。
「おおおおおおおォォォッ!」
「ぬぅううううああああッ!」
「ぬぅううううああああッ!」
一呼吸の間もなく跳躍、反転して狙い穿つは敵手の眉間。逆手に構えた切っ先は垂直に天下る神の杖として飛来し、下方より迎え撃つは天に突き上げる神速の対空平刺突。
飛天御剣流龍槌閃・惨、牙突・参式。両者の激突は大気を切り裂く波濤となって反響し、仕切り直しとばかりに地に足つけて再度の剣戟を開始する。
飛天御剣流龍槌閃・惨、牙突・参式。両者の激突は大気を切り裂く波濤となって反響し、仕切り直しとばかりに地に足つけて再度の剣戟を開始する。
鏡合わせであるかの如く、鉄刃と鉄刃が交差する。袈裟に逆袈裟、八相に正眼、技とも言えぬそれらはしかし極大の剣気を伴い、無双の一閃となりて空間を断割する。
どれ一つをとっても並み居る剣士ならば百度は命を散らす魔剣の応酬に、しかしそのような攻撃など見るに値しないと言わんばかりに共に意識の外へと追いやる。眺めるのは、滾る互いの眼のみ。
どれ一つをとっても並み居る剣士ならば百度は命を散らす魔剣の応酬に、しかしそのような攻撃など見るに値しないと言わんばかりに共に意識の外へと追いやる。眺めるのは、滾る互いの眼のみ。
そこには最早、人の目など映ってはいなかった。ここには既に人などいない。疑うべくもない戦鬼の業、修羅道へ堕ちた二人の悪鬼がそこには在った。
「いざ、ここに倒れろ抜刀斎ッ!!」
「抜かせ、散るのはどちらか知るがいいッ!!」
「抜かせ、散るのはどちらか知るがいいッ!!」
束の間の会話と同時、対の剣戟を放ち合う。
力を上回る技術をぶつければ、技術を上回る力をぶつけてくる。
術理を上回る直感を見せつければ、直感を押しつぶす術理で以て相殺する。
永劫に続くと錯覚させる剣乱舞踏の中、二人は吼えた。自らの気概を振り絞るために、これが俺だと叫ぶように。
その叫びに身を任せる斎藤に対し、しかし抜刀斎は心中にてその趣を異としていた。
力を上回る技術をぶつければ、技術を上回る力をぶつけてくる。
術理を上回る直感を見せつければ、直感を押しつぶす術理で以て相殺する。
永劫に続くと錯覚させる剣乱舞踏の中、二人は吼えた。自らの気概を振り絞るために、これが俺だと叫ぶように。
その叫びに身を任せる斎藤に対し、しかし抜刀斎は心中にてその趣を異としていた。
(猛っているのか、俺は……)
そこにあるのは疑念、そして抑えきれない高揚か。待ち遠しいとでも言うかのように、その心臓は鼓動を早めて止まらない。
それは斎藤とて同じだった。猛る、昂ぶる、待ち遠しいと叫んで止まない。されど、その心を是とする斎藤とは違い、抜刀斎の思考は真逆のものだった。
それは斎藤とて同じだった。猛る、昂ぶる、待ち遠しいと叫んで止まない。されど、その心を是とする斎藤とは違い、抜刀斎の思考は真逆のものだった。
すなわち―――"やめろ、そんなものは必要ない"
抜刀斎はあくまで暗殺の任を負ってこの場に立っていた。斎藤との決着を望む心は本物であるし、それに応えたのも事実ではあった。しかし因縁を全てに優先するつもりは毛頭ない。
当然の話だろう。緋村抜刀斎は個人的な妄執を実現するためではなく、万人の未来のためにこそ戦っているのだから。
当然の話だろう。緋村抜刀斎は個人的な妄執を実現するためではなく、万人の未来のためにこそ戦っているのだから。
交差の瞬間を狙い己が刃で地を穿つ。外したわけではない、その剣閃は衝撃となって地面を伝い、抉り貫いて斎藤へと殺到した。
飛天御剣流が一、土竜閃。例え石であろうがアスファルトであろうが、舗装された地面であっても刃は容易く地を切り裂き技の一部と為す。
飛天御剣流が一、土竜閃。例え石であろうがアスファルトであろうが、舗装された地面であっても刃は容易く地を切り裂き技の一部と為す。
「はああああァァァッ!!」
広範囲に広がった衝撃波を、しかし斎藤は薄布を切り裂くかのように牙突で以て貫いた。
地を抉る衝撃の嵐を己が身一つで踏破する様はまさしく修羅戦鬼の現人か。抜刀斎は身を捻ると同時に回転、半身を滑り込ませ逆向きの抜刀を繰り出す。
飛天御剣流・龍巻閃。最上の返し技は、しかしそれを熟知した斎藤相手には通じず一刀の下に防がれる。
地を抉る衝撃の嵐を己が身一つで踏破する様はまさしく修羅戦鬼の現人か。抜刀斎は身を捻ると同時に回転、半身を滑り込ませ逆向きの抜刀を繰り出す。
飛天御剣流・龍巻閃。最上の返し技は、しかしそれを熟知した斎藤相手には通じず一刀の下に防がれる。
炸光する火花、弾け飛ぶ対の刀剣。
戦闘の余波によって飛び散る瓦礫の中で、大義と信義が牙を打つ。
斬る、斬る、斬る、斬る―――斬って貫き穿って捌く。
苛烈に、熾烈に、猛然と。超至近距離で放たれる剣戟の嵐は閃光とも形容できる火花によって彩られた。
振るわれる剣閃は拮抗している。その嵩を増すことなく、まして減らすこともなく。一手をしくじれば即座に首が飛ぶ死の領空域。
刃がぶつかる毎に発生する轟音は大気を貫いて、怒涛の奔流となって止まらない。
戦闘の余波によって飛び散る瓦礫の中で、大義と信義が牙を打つ。
斬る、斬る、斬る、斬る―――斬って貫き穿って捌く。
苛烈に、熾烈に、猛然と。超至近距離で放たれる剣戟の嵐は閃光とも形容できる火花によって彩られた。
振るわれる剣閃は拮抗している。その嵩を増すことなく、まして減らすこともなく。一手をしくじれば即座に首が飛ぶ死の領空域。
刃がぶつかる毎に発生する轟音は大気を貫いて、怒涛の奔流となって止まらない。
修羅同士の交錯、醜きは人の成れの果てと言うかのように、それは刃と刃、信念と矜持の衝突に他ならなかった。
決闘などと呼べはしない。これは精神の支柱ごと砕き、相手の道を粉砕する喰らい合いだ。
決闘などと呼べはしない。これは精神の支柱ごと砕き、相手の道を粉砕する喰らい合いだ。
戦闘開始より既に幾ばくか、正確な時間などどちらにも判別できていない。
休む暇もなく剣を振るい、ただ一度の停止もなく連撃を放ち続けた彼らに、時間の概念など意味を為さない。
だが故にか、互いの呼吸、疲労の密度。それらが合わさり、神域のタイミングによって、両者は同時にその足を止めた。
休む暇もなく剣を振るい、ただ一度の停止もなく連撃を放ち続けた彼らに、時間の概念など意味を為さない。
だが故にか、互いの呼吸、疲労の密度。それらが合わさり、神域のタイミングによって、両者は同時にその足を止めた。
「……」
「……」
「……」
ここが限界だった。あと一度技を放てば、それで全ての力を使い切る。
そう悟っていた。斎藤も、抜刀斎も。自分と相手が共に"その状態"であると理解した。
皮肉にも、それが当初と同じにらみ合いの構図へと互いを誘導していた。
そう悟っていた。斎藤も、抜刀斎も。自分と相手が共に"その状態"であると理解した。
皮肉にも、それが当初と同じにらみ合いの構図へと互いを誘導していた。
互いに言葉はなかった。この期に及び、この二人にそんなものは不要だった。
言葉なく、各々の必殺へと構えを移行する。
言葉なく、各々の必殺へと構えを移行する。
斎藤は先と同じ、両手平刺突の構え。彼の十八番である牙突を放つための構えだ。
そして抜刀斎もまた、同じく納刀しての中段居合の構えだ。そこから何が飛び出すのかは、抜刀術を生業とする飛天御剣流故に判別がつかない。
そして抜刀斎もまた、同じく納刀しての中段居合の構えだ。そこから何が飛び出すのかは、抜刀術を生業とする飛天御剣流故に判別がつかない。
修羅へと堕ちたはずの二人は、最期の一幕においてただ一時、その身を人へと戻したのだ。
「これで最期だ」
「是非もない」
「是非もない」
……ただ一言だけ。
一言だけ交わし、二人は最後の突撃を敢行した。
一言だけ交わし、二人は最後の突撃を敢行した。
「――――ッ!」
声にもならない雄叫びと共に突進するは斎藤一、放つは必殺の牙突・弐式。
弾丸が如くその身を撃ち出し、後手を取るは未だ納刀したままの抜刀斎。
弾丸が如くその身を撃ち出し、後手を取るは未だ納刀したままの抜刀斎。
唸りを上げる斎藤の剣が空を切り裂き疾走する。その切っ先が目前まで迫り、ここでようやく、抜刀斎がその刃を抜き放った。
狙うは後の先か、それとも返しか。そのどちらをも叩き潰さんと斎藤が吼え猛り―――
狙うは後の先か、それとも返しか。そのどちらをも叩き潰さんと斎藤が吼え猛り―――
「……!」
しかし、前方へ抜き放たれるはずだった刀は、その軌道を変じ目にも止まらぬ速度で再び納刀された。小気味良い金属音が辺りに反響する。
同時、突撃を仕掛けていた斎藤の動きに乱れが生じた。
同時、突撃を仕掛けていた斎藤の動きに乱れが生じた。
「ぐッ……!?」
―――飛天御剣流・龍鳴閃。抜刀と対を成す、神速の納刀術。
その奥秘とは、「納刀の衝撃波による聴覚の破壊」。
その奥秘とは、「納刀の衝撃波による聴覚の破壊」。
抜刀の欺瞞、騙し討ち。
フェイントと呼ばれるそれは、相手が集中していればしているほど、本命であれば本命であるほど効力を増す。
例えば、このように"命を懸けた最後の交差"であるとか。
言うまでもなく、効力は覿面である。
フェイントと呼ばれるそれは、相手が集中していればしているほど、本命であれば本命であるほど効力を増す。
例えば、このように"命を懸けた最後の交差"であるとか。
言うまでもなく、効力は覿面である。
納刀された居合で狙い撃つは無防備となった敵手の胴体、あるいは首。横薙ぎに両断できる箇所。
対手が失敗を悟って跳ね戻るよりも先に、その死命を斬り伏せ得るだろう。
意表を突かれた者と、想定通りの者。
どちらが速く動けるかは自明の理である。
対手が失敗を悟って跳ね戻るよりも先に、その死命を斬り伏せ得るだろう。
意表を突かれた者と、想定通りの者。
どちらが速く動けるかは自明の理である。
かくして、先手を取ったはずの斎藤は動きを封じられ。
後手を取った抜刀斎こそが後の先を得る。
状況は刹那の間に激変を遂げた。
後手を取った抜刀斎こそが後の先を得る。
状況は刹那の間に激変を遂げた。
今度こそ本当に、抜刀斎の剣が抜き放たれる。
前方へと攻め入り、未だ身動きの叶わぬ斎藤に横薙ぎの居合を繰り出す。
勝敗が、決する。
前方へと攻め入り、未だ身動きの叶わぬ斎藤に横薙ぎの居合を繰り出す。
勝敗が、決する。
………。
……。
…。
▼ ▼ ▼
「何……?」
驚嘆の声は一体誰のものであるのか。
キルバーンか、ピロロか、あるいは音無かゆりであるのか。
瞠目し、空けた声を上げるような、荒唐無稽な光景が彼らの眼前にて展開されていた。
キルバーンか、ピロロか、あるいは音無かゆりであるのか。
瞠目し、空けた声を上げるような、荒唐無稽な光景が彼らの眼前にて展開されていた。
―――光の剣が、死神の鎌を防いでいた。
青白く光る光条の剣、大気を灼く甲高い音を響かせて。命を切り裂く鎌と一人でに鍔競り合いを行っていた。
瞬間、キルバーンはそれまでの遊び感覚ではなく戦闘用の思考へと切り替え、瞬時に刃を引き戻し渾身の斬撃を繰り出した。およそ人では捉えられない超速、しかしそれすらも光の剣は捌き、容易に弾き返す。
瞬間、キルバーンはそれまでの遊び感覚ではなく戦闘用の思考へと切り替え、瞬時に刃を引き戻し渾身の斬撃を繰り出した。およそ人では捉えられない超速、しかしそれすらも光の剣は捌き、容易に弾き返す。
「う、うわ、あああ!!?」
その光景を前に、音無はただ悲鳴を上げると、そのまま走り去った。必死に、死にもの狂いで、キルバーンとは反対の方向に。
けれど、それに構っている余裕など、今のキルバーンにはなかった。
けれど、それに構っている余裕など、今のキルバーンにはなかった。
「剣、セイバーかッ……!
いいや違う、前にみたあいつはこんなもの使っちゃいなかった。だったら……!」
いいや違う、前にみたあいつはこんなもの使っちゃいなかった。だったら……!」
後方へと飛びのき周囲を振り返る。見間違いではない、そこには"誰もいなかった"。
自分の感覚が狂ったわけではないと、キルバーンは確信した。あまりにもあり得なさすぎて、自らの耄碌不覚すら、彼は一瞬疑ったのだ。
だが違う、彼は今も正常だ。
ならば、だというのなら。
自分の感覚が狂ったわけではないと、キルバーンは確信した。あまりにもあり得なさすぎて、自らの耄碌不覚すら、彼は一瞬疑ったのだ。
だが違う、彼は今も正常だ。
ならば、だというのなら。
サーヴァントの気配知覚範囲、半径およそ数百m。
攻撃を防がれるまで、その警戒網のどこにも気配が引っ掛からなかったのは。
一体、どういうことであるというのか―――!
攻撃を防がれるまで、その警戒網のどこにも気配が引っ掛からなかったのは。
一体、どういうことであるというのか―――!
「―――待たせたな」
声が―――
涼やかな声が届く。
それは、キルバーンの背後から。
それは、キルバーンの背後から。
振り返る死神から、倒れ伏す少女を守るように。
声の主を、死神は見た。白い男だった。
何時の間に現れたのか。彼は、仲村ゆりを庇うように立って。
何時の間に現れたのか。彼は、仲村ゆりを庇うように立って。
「機械帯、起動―――」
告げる言葉だけが、伽藍の空間に澄み渡った。
▼ ▼ ▼
―――男の。
―――姿が。
―――変わって。
―――姿が。
―――変わって。
―――黒の襟巻、たなびいて。
閃光が奔る。
雷鳴が轟く。
雷鳴が轟く。
眩い光が奔る。
それは蒼白色をした輝きだった。
それは遥かな果ての輝きだった。
それは蒼白色をした輝きだった。
それは遥かな果ての輝きだった。
空の彼方に見えるもの。
漆黒に染まった空に輝くもの。
漆黒に染まった空に輝くもの。
雷の―――
輝き―――
輝き―――
「輝きを持つ者よ。尊さを失わぬ若人よ」
「お前の声を聞いた。ならば呼べ、私は来よう」
揺れる道化の視線を受け止めながら。
腕を組み、輝きの中で彼は言った。
腕を組み、輝きの中で彼は言った。
その腰部には機械帯 が。
その腕部には機械籠手 が。
その腕部には
たなびく黒い襟巻は僅かに雷電を帯びて。
白い詰襟服には見たこともない意匠。
白い詰襟服には見たこともない意匠。
遠い異国の服を纏い、
空の果ての雷を纏い、
刹那に、彼はその姿を変えていた。
空の果ての雷を纏い、
刹那に、彼はその姿を変えていた。
漆黒領域の中心。
そこで、弱者を守るが如く佇む。
そこで、弱者を守るが如く佇む。
―――そして。
―――彼の瞳、輝いて。
―――彼の瞳、輝いて。
―――周囲に浮かぶ光の剣、4つ。
「……ひか、り……?」
「お前の輝きだ。少々、遅くなってしまったがな」
「お前の輝きだ。少々、遅くなってしまったがな」
僅かに身を起こすゆりが呟く。その双眸は周囲に瞬く紫電の光を映していた。
眩い輝きはゆりにある光景を幻視させる。それは、遠く記憶の彼方に埋もれた、幼い日の情景。
雨降りしきる山景に映える、一条の稲妻―――
眩い輝きはゆりにある光景を幻視させる。それは、遠く記憶の彼方に埋もれた、幼い日の情景。
雨降りしきる山景に映える、一条の稲妻―――
「メインディッシュを邪魔してくれちゃって……!
ボクと同じアサシンか、奇襲を成功させたからって調子に乗られちゃ困るんだよねぇ……!」
ボクと同じアサシンか、奇襲を成功させたからって調子に乗られちゃ困るんだよねぇ……!」
「否、我がクラスはアサシンに非ず。
隠れ潜み闇討つは、貴様が如き影の専売特許と知れ」
隠れ潜み闇討つは、貴様が如き影の専売特許と知れ」
黒を纏った道化師を前に、彼は堂々と言った。
慌てるそぶりなんて少しもなくて、目元を少し歪ませる程度。
慌てるそぶりなんて少しもなくて、目元を少し歪ませる程度。
飛び退いたキルバーンと、腕を組み仁王立ちする白い男。両雄が睨みあう。
「ライダー、大丈夫!?」
路地の向こうから駆け寄り、大声で呼びかける少女が一人。小柄な、艶やかな黒髪を腰まで伸ばした少女だ。
少女―――南条光は辿りついた現場を一目見るや、「はっ」と息を呑み、倒れ伏すゆりを相手に行われていたであろう惨状を朧気ながらに理解した。
少女―――南条光は辿りついた現場を一目見るや、「はっ」と息を呑み、倒れ伏すゆりを相手に行われていたであろう惨状を朧気ながらに理解した。
「マスターか。そこな少女を連れて後ろへ下がっているといい。ここは今から戦場となる」
「わ、分かった! お姉さんこっち!」
「わ、分かった! お姉さんこっち!」
小柄な体躯に見合わぬ膂力で、光は力なく倒れるゆりの肩を組み後退する。
それを見たキルバーンは、吐き捨てるように叫んだ。
それを見たキルバーンは、吐き捨てるように叫んだ。
「戦場になるだって―――そんなの願い下げさ!」
そしてそのまま反転し、脱兎の如くに逃走した。一歩の跳躍で10mの距離を稼ぎ、息を吐く間もなく疾走。その体は瞬間的に亜音速にも到達し、最早人の追い縋れる速度ではありえない。
そもそもの話、キルバーンにはサーヴァントを相手に戦うつもりなど微塵もないのだ。ゆりと音無を襲撃したのは、あくまで彼らがサーヴァントを連れない格好のカモだったからで、仮にゆりが使役するセイバーなりの気配が感知圏内に入ってきたならその時点で遊びを打ち切って、ゆりと音無の命を手土産にさっさと逃げ去るつもりだったのだ。
例え死んでも蘇生できる「命のストック」という保険がないというのに、誰が命がけの戦いなどするものか。そんなものは頭の足りない猪サーヴァントだけがやっていればいい。自分はその隙を突き存分に漁夫の利を得させてもらうだけだ。
例え死んでも蘇生できる「命のストック」という保険がないというのに、誰が命がけの戦いなどするものか。そんなものは頭の足りない猪サーヴァントだけがやっていればいい。自分はその隙を突き存分に漁夫の利を得させてもらうだけだ。
故に選択するのは逃走の一択。無駄に遊んだだけに終わってしまうのはもったいないが、命の危険に比べれば遥かにマシである。
魔力回復のアテも、遊びのアテもまだまだたくさんあるのだ。こんなところとはさっさとおさらばして―――
魔力回復のアテも、遊びのアテもまだまだたくさんあるのだ。こんなところとはさっさとおさらばして―――
「残念だが、遅い」
声が聞こえた瞬間、疾駆するキルバーンに追いつくように、四条の光閃が踊りかかった。
今まさに獲物を呑みこまんとする猛獣の咢の如く。迫りくる衝撃の余波で地面のアスファルトを砕き捲れ上がらせながら、光剣は握る者もなく自在に襲い掛かる。
今まさに獲物を呑みこまんとする猛獣の咢の如く。迫りくる衝撃の余波で地面のアスファルトを砕き捲れ上がらせながら、光剣は握る者もなく自在に襲い掛かる。
「ぬぅ……ッ!?」
受けきれない、そう判断したキルバーンは疾走の勢いのままに跳躍。戯画的なまでに身を捻ることで無理やりに電刃を回避する。
回転する雷刃はキルバーンの衣服を浅く切り裂くに留まり、しかしキルバーンは逃走の足を止めることを余儀なくされる。
危うげなく着地し、振り返った先にいたのは、いつの間にかキルバーンの直近へと移動を完了していたライダーの姿だった。瞬間移動でも行ったのかと、瞠目する。
回転する雷刃はキルバーンの衣服を浅く切り裂くに留まり、しかしキルバーンは逃走の足を止めることを余儀なくされる。
危うげなく着地し、振り返った先にいたのは、いつの間にかキルバーンの直近へと移動を完了していたライダーの姿だった。瞬間移動でも行ったのかと、瞠目する。
「中々どうして、やってくれるじゃないか……!
そこのガキは見逃してやるってんだから、潔くお別れしようっていうボクの心遣いを理解できないのかい……!?」
そこのガキは見逃してやるってんだから、潔くお別れしようっていうボクの心遣いを理解できないのかい……!?」
「貴様のような道化を見逃すものか。その不遜、その傲慢。
世界には貴様以外の知性もあると、どうせ認識もしない輩だ。端的に、醜い」
世界には貴様以外の知性もあると、どうせ認識もしない輩だ。端的に、醜い」
ピクリ、と死神の眉が動いたような気配があった。その素顔は仮面に覆われて、けれど変質する感情の影が如実にそれを伝えてくる。
「醜い……醜いと言ったか。侮辱したな、ボクを……!」
「ならば何だと言う。その鎌で我が喉笛を掻き切ってみせるとでも言うか。生まれてこの方他者を貶める真似しかできていない貴様が」
「……いいだろう。ボクをその気にさせたこと、後悔するなよ……!」
「ならば何だと言う。その鎌で我が喉笛を掻き切ってみせるとでも言うか。生まれてこの方他者を貶める真似しかできていない貴様が」
「……いいだろう。ボクをその気にさせたこと、後悔するなよ……!」
声と同時、キルバーンはその痩躯を漆黒の旋風と化して疾走した。
振るうは手に持つ死神の鎌。一振りごとに人の命を刈り取る魔刃が、独特の風切り音と共にライダーへと殺到する!
舞い踊る光の剣、その一本が躍り出て死神の鎌を受け止める。鋼鉄の刃が彼の雷電を反射し、眩んだ光を一筋、瞬かせる。
振るうは手に持つ死神の鎌。一振りごとに人の命を刈り取る魔刃が、独特の風切り音と共にライダーへと殺到する!
舞い踊る光の剣、その一本が躍り出て死神の鎌を受け止める。鋼鉄の刃が彼の雷電を反射し、眩んだ光を一筋、瞬かせる。
「フフ、驚いたかい?」
喜悦を滲ませるキルバーンの言葉通り、ライダーの眉は微かな驚きに顰められていた。
その剣閃、その速度。暗殺者などと生温い、キルバーンの剣技は一流の領域に手をかけている!
その剣閃、その速度。暗殺者などと生温い、キルバーンの剣技は一流の領域に手をかけている!
「舐めてもらっちゃ困る。暗殺だけがボクの得意技じゃないんだ。
武器を使っても、まあこれくらいのものさ……!」
武器を使っても、まあこれくらいのものさ……!」
お喋りの間も振るわれる鎌は留まることを知らず、縦横無尽に空間を薙ぐ。
様々な方向から、時に呼吸をずらして。空を裂き奏でられる笛の音はさながら死の舞踏でもあるかのように。
的確にライダーを追い詰める。一人でに舞う光剣、その動きが徐々に追いつけなくなる。
様々な方向から、時に呼吸をずらして。空を裂き奏でられる笛の音はさながら死の舞踏でもあるかのように。
的確にライダーを追い詰める。一人でに舞う光剣、その動きが徐々に追いつけなくなる。
「口ほどにもない……これでトドメだ!」
踊りかかる光剣を弾き飛ばして、振り返り様の一撃だった。横薙ぎに振るわれた鎌が、一直線にライダーの胴を狙う。
獲った―――!
と、確かにそう思わせる見事なタイミングであったが。
獲った―――!
と、確かにそう思わせる見事なタイミングであったが。
「小癪」
漆黒の空に重い音が響き渡る。
鮮血の代わりに、音が。
堅い感触が死神の腕に伝わったであろう。肩関節がみしりと音立てる。
鮮血の代わりに、音が。
堅い感触が死神の腕に伝わったであろう。肩関節がみしりと音立てる。
刃は止まっていた。
機械籠手に覆われた、左の掌で―――!
機械籠手に覆われた、左の掌で―――!
「何……!?」
「暗殺だけが能ではないと貴様は言ったが。私も言わせてもらおう。
我が力は剣のみに非ず。そう、私にはバリツがある」
「暗殺だけが能ではないと貴様は言ったが。私も言わせてもらおう。
我が力は剣のみに非ず。そう、私にはバリツがある」
掴む鎌を受け流し、返す刃で眼前の胸に紫電の掌底。
打ち込まれる電流を震と散らしながら、死神は叩き込まれるがままに後方へと吹き飛ばされた。
打ち込まれる電流を震と散らしながら、死神は叩き込まれるがままに後方へと吹き飛ばされた。
「無刀術か……嫌だねぇ、奴のことを思い出す」
与えられたダメージに蹲りながら、しかしキルバーンは不適に笑みを絶やさない。
何故なら、そう。ここまで打ち合ったというのなら、そろそろ兆候が出始めるからだ。
死神の鎌、振るうごとに掻き鳴らされる特有の音色。
敵手を自覚なき間に貶め、そして幻惑の淵へと誘う死神の吹く笛が、確かにライダーを侵食している!
何故なら、そう。ここまで打ち合ったというのなら、そろそろ兆候が出始めるからだ。
死神の鎌、振るうごとに掻き鳴らされる特有の音色。
敵手を自覚なき間に貶め、そして幻惑の淵へと誘う死神の吹く笛が、確かにライダーを侵食している!
「けど、それも終わりだ。そろそろ黄泉路へ堕ちてもらおうか……!」
乾坤一擲、これまでに倍する文字通り全力の一撃をキルバーンは放つ。
止められない―――死の音色を聞いた者は皆須らく五感を奪われるべし。正常な認識を失ったライダーはこの一刀にて打ち倒されるのだ!
止められない―――死の音色を聞いた者は皆須らく五感を奪われるべし。正常な認識を失ったライダーはこの一刀にて打ち倒されるのだ!
そう、そのはずであったが。
「黙れ。
たかが、揺らめく影ひとつ―――!」
たかが、揺らめく影ひとつ―――!」
言葉を残して、ライダーの姿が掻き消える。
否、実際に消えているわけではない。驚異的な速度で移動する様が、まるで消えているかのように錯覚させるだけなのだ。
それは、最初にキルバーンの鎌を止めた時のように。
気配察知圏外から、一瞬で間合いを詰めた時のように。
否、実際に消えているわけではない。驚異的な速度で移動する様が、まるで消えているかのように錯覚させるだけなのだ。
それは、最初にキルバーンの鎌を止めた時のように。
気配察知圏外から、一瞬で間合いを詰めた時のように。
何処へ行ったと、死神は当惑して振り返る。左右、どちらにも彼はいない。
ならばまさかと見上げれば、そこには月光を背に跳躍する男の姿。
中空にて猛々しく、その足を振り上げて―――
ならばまさかと見上げれば、そこには月光を背に跳躍する男の姿。
中空にて猛々しく、その足を振り上げて―――
「バリツ式―――」
空間が裂ける!
高々と振り上げられた白い彼の踵が、落下しながら死神の鎌を縦に断つ!
高々と振り上げられた白い彼の踵が、落下しながら死神の鎌を縦に断つ!
紫電を纏った彼の靴。
光剣を伴った彼の体。
それが、鋼を切り裂いていた。
光剣を伴った彼の体。
それが、鋼を切り裂いていた。
暗い空を一条の雷が落ちゆくように。
砂鉄の絨毯に磁石を滑らせるように。
熱したナイフでバターを切るように。
砂鉄の絨毯に磁石を滑らせるように。
熱したナイフでバターを切るように。
石畳ごと地面を砕いて、彼はすくと立ち上がる。
勢いのままに地面に突き刺さった光の剣も、ひとりでに。くるりと彼の周囲に集う。
勢いのままに地面に突き刺さった光の剣も、ひとりでに。くるりと彼の周囲に集う。
「……バリツ式、雷電踵落とし」
「馬鹿な……」
「馬鹿な……」
呆然と呟く声が、漆黒の闇に消えて行った。
「接触したはず、確かに耳にしたはずだ!
精神に、五感に影響を受けるはずでは……」
精神に、五感に影響を受けるはずでは……」
「我が電磁力を以てすれば、無形の音を斬ることも容易い。
そして」
そして」
その言葉に繋げるかのように、ライダーの背後に幾本もの稲妻が地に落ちる!
雷雲、発生源もなしに、しかし蒼白の電光が瞬き、衝撃に地を抉った。
同時、ガラスのような何かが砕ける音が、いくつも。
雷雲、発生源もなしに、しかし蒼白の電光が瞬き、衝撃に地を抉った。
同時、ガラスのような何かが砕ける音が、いくつも。
「貴様が仕掛けた見えざる刃、我が雷電にて打ち砕かせてもらったぞ。
最早打つ手はあるまい」
「こ、こいつ……!」
最早打つ手はあるまい」
「こ、こいつ……!」
雷電纏わせる機械掌。己に向けられるそれを前に。
追い詰められたキルバーンは、しかし素顔見せぬ仮面の下で、ニヤリと勝利を確信した笑みを浮かべたのだった。
追い詰められたキルバーンは、しかし素顔見せぬ仮面の下で、ニヤリと勝利を確信した笑みを浮かべたのだった。
「ライダー……」
視界の先で行われる戦闘を垣間見て、南条光は心配そうな声をあげた。
ライダーと死神のアサシンとの間でどのような戦闘が行われているのか、分からない。あまりにも速すぎて。
人間である光の目では、その影すら捉えられない。辛うじて、そこで戦闘が起こっているということだけが、激突する大気の振動で理解できたけど。
ライダーと死神のアサシンとの間でどのような戦闘が行われているのか、分からない。あまりにも速すぎて。
人間である光の目では、その影すら捉えられない。辛うじて、そこで戦闘が起こっているということだけが、激突する大気の振動で理解できたけど。
「……つ、うぅ……」
「あ、お姉さん、気が付いた!?」
「あ、お姉さん、気が付いた!?」
その腕の中、抱きかかえられるように瞼閉じるゆりが、苦痛に喘ぐようにうめき声をあげた。
光の声に反応するように、ゆりはその瞼を開けた。憔悴した瞳が、街灯の灯りを反射して鈍く煌めいた。
光の声に反応するように、ゆりはその瞼を開けた。憔悴した瞳が、街灯の灯りを反射して鈍く煌めいた。
「あなた……あたしたちを、助け……」
「あ、ああ! アタシたちはお姉さんを助けに来たんだ!
アタシ……は、何もできないけど、でもライダーがいるからもう大丈夫!」
「あ、ああ! アタシたちはお姉さんを助けに来たんだ!
アタシ……は、何もできないけど、でもライダーがいるからもう大丈夫!」
朦朧としたゆりを励ますように、光はできるだけ頼もしく映るようにと声をかけた。大丈夫、と断言できるだけの根拠なんてないし、光とて心配なのは同じだけど、でも傷つけられ憔悴した誰かを元気づけられないのに何がアイドルか。
だから光は断言する。自分はあなたを助けに来た、来たからにはもう大丈夫なのだと。
だから光は断言する。自分はあなたを助けに来た、来たからにはもう大丈夫なのだと。
「そう……ありがとう、ね……」
「ううん、礼なんていらないよ。それよりお姉さん、もう喋らないほうが……」
「いえ……あたしにも、まだやれることが、あるから……」
「ううん、礼なんていらないよ。それよりお姉さん、もう喋らないほうが……」
「いえ……あたしにも、まだやれることが、あるから……」
そう言うと、ゆりはだらりと下げられた右手を無理やりに持ち上げる。苦痛に顔が歪むけど、そんなの振り払って宿る令呪を掲げる。
「令呪を以て、命令するわ……セイバー、あたしたちの……」
それは起死回生の一手、この場に己が侍従たるサーヴァントを呼び出す虎の子の最終手段。あの死神を確実に打倒するための切り札。
今それを使う。あの対敵を潰すために、ゆりは魔力込めた命令をここに下そうと―――
今それを使う。あの対敵を潰すために、ゆりは魔力込めた命令をここに下そうと―――
「そんなもの使わせるわけないだろバァ~~~カッ!」
「ッ!?」
場違いなまでに響く軽薄な口調に、光とゆりは驚愕と共に振り返る。
そこには、杖の先端をこちらに向け、嘲笑を浮かべた一つ目の使い魔の姿―――!
そこには、杖の先端をこちらに向け、嘲笑を浮かべた一つ目の使い魔の姿―――!
嗤っていた、ピロロは。キルバーンは。こうなることを予測して、あらかじめ布石を打って。サーヴァントではなくマスターを殺すこの時のために!
キルバーンは暗殺者である。武器を使わせても一流の腕を持つ彼は、しかしそのクラスが示すように生粋の暗殺者。詭弁詭道に闇討ち詐術、暗殺こそが生業なのだ。
そも、最初に言った通り、彼はハナからサーヴァント相手にまともにやり合う気など毛頭ないのだ。如何に強いサーヴァントであれ、マスターなしでは生き残ること叶わぬならば、急所たるそいつだけを狙えばいい話である。
ピロロは嗤った。高らかに。己の勝利を確信して、不覚をとったライダーを嘲笑って。
そも、最初に言った通り、彼はハナからサーヴァント相手にまともにやり合う気など毛頭ないのだ。如何に強いサーヴァントであれ、マスターなしでは生き残ること叶わぬならば、急所たるそいつだけを狙えばいい話である。
ピロロは嗤った。高らかに。己の勝利を確信して、不覚をとったライダーを嘲笑って。
その瞬間、光とゆりは自分たちに打てる手が何もないということを、走馬灯のようにスローとなった視界の中で悟った。
令呪を使ってセイバーを呼び戻す―――間に合わない。
ライダーに命じてこの場に急行してもらう―――間に合わない。
ならば、自分たちが攻撃を躱す―――間に合わない。
間に合わない、間に合わない、間に合わない……何もかもが手遅れで、挽回の機会は永遠に失われた。
死んでしまう、ここで。使い魔の放つ魔術で、自分たちは。
そう確信してしまい、二人はぎゅっと目を閉じた。耐えるように、忍ぶかのように。来たる衝撃に身を備えて。
令呪を使ってセイバーを呼び戻す―――間に合わない。
ライダーに命じてこの場に急行してもらう―――間に合わない。
ならば、自分たちが攻撃を躱す―――間に合わない。
間に合わない、間に合わない、間に合わない……何もかもが手遅れで、挽回の機会は永遠に失われた。
死んでしまう、ここで。使い魔の放つ魔術で、自分たちは。
そう確信してしまい、二人はぎゅっと目を閉じた。耐えるように、忍ぶかのように。来たる衝撃に身を備えて。
そして、ピロロの「ヒャダルコ」という詠唱が、二人に向かって放たれた。
………。
……。
…。
――――――――――――――――――。
「が、はぁ!?」
鮮血が舞った。一閃の斬撃音と共に。
空を斬る、次いで何かが倒れる音が一つ。それだけが鳴り響き、辺りは再び静寂を取り戻した。
空を斬る、次いで何かが倒れる音が一つ。それだけが鳴り響き、辺りは再び静寂を取り戻した。
「……え?」
目を開ける。それは、二人にも予想できていなかった展開故に。
瞼を開いた視界の先、そこにあったのは胸を裂かれて血を流し倒れるピロロの姿と。
一人でに浮かぶ、一本の光剣だった。
瞼を開いた視界の先、そこにあったのは胸を裂かれて血を流し倒れるピロロの姿と。
一人でに浮かぶ、一本の光剣だった。
「馬鹿な!?」
確信した勝利を外されて、キルバーンは驚愕の色でそう叫ぶ。
それを見て、ライダーはただ睥睨したまま言った。
それを見て、ライダーはただ睥睨したまま言った。
「……貴様が如き影の性根、見破れんとでも思っていたか。
どのような戦況に陥ろうとも、貴様がまともにやり合わんというのは目に見えていた。故に、備えた」
どのような戦況に陥ろうとも、貴様がまともにやり合わんというのは目に見えていた。故に、備えた」
ライダーはこの場へ急行する直前、お守りだと言って光にあるものを手渡していた。光の目には、それが小さなチェスの駒に見えただろう。
黒磁の素材で構築された小さなチェスの駒。
それこそは深淵の鍵。ニコラ・テスラが有する電界の剣を成す柄にして、神々の残骸。五本あるうちの最後の一つ―――ペルクナスである。
黒磁の素材で構築された小さなチェスの駒。
それこそは深淵の鍵。ニコラ・テスラが有する電界の剣を成す柄にして、神々の残骸。五本あるうちの最後の一つ―――ペルクナスである。
「さて、もう一度言おう。貴様に最早打つ手はない。潔く往生際を知るがいい」
「ふ、ふざけるな!
恐怖の死神と呼ばれたボクを、こけにしやがって……!」
「ふ、ふざけるな!
恐怖の死神と呼ばれたボクを、こけにしやがって……!」
声に混ざる焦燥。
呆然。状況、多分理解できていない。
死神の表情が変わっていた。他者を害する愉悦、見下して止まない自尊、敵へと向ける殺意、それらを塗りつぶすのは混乱と。未知への戸惑いと。
きっと恐怖も。そんな顔をしている。
呆然。状況、多分理解できていない。
死神の表情が変わっていた。他者を害する愉悦、見下して止まない自尊、敵へと向ける殺意、それらを塗りつぶすのは混乱と。未知への戸惑いと。
きっと恐怖も。そんな顔をしている。
「恐怖に怯える者が、恐怖を僭称するなど」
その瞬間。
「言語道断!」
彼の全身が輝く!
翠色の雷を激しく纏う!
翠色の雷を激しく纏う!
「……また侮辱したな、ボクを!」
憤怒の気色が、キルバーンを覆う。
「侮辱することは許さない……!
ボクは、あらゆる恐怖を我が物とし、全ての人間の生を統括する死の神!
キミら如きが及ぶ存在じゃないんだよォ!」
ボクは、あらゆる恐怖を我が物とし、全ての人間の生を統括する死の神!
キミら如きが及ぶ存在じゃないんだよォ!」
地を蹴り全力で後退すると同時、キルバーンは手刀にて己が左腕を斬り落とした。
それは自暴自棄の表れであるとか、窮状にて狂ったとか、そういうわけではない。それは、彼が有する最大最強の攻撃、そのための準備なのだ。
切り離して左腕を、キルバーンは天高く放り上げる。頭上にて固定された腕は急速に回転を速め、いつしかその総身を巨大な火球へと変じていた。
それは自暴自棄の表れであるとか、窮状にて狂ったとか、そういうわけではない。それは、彼が有する最大最強の攻撃、そのための準備なのだ。
切り離して左腕を、キルバーンは天高く放り上げる。頭上にて固定された腕は急速に回転を速め、いつしかその総身を巨大な火球へと変じていた。
キルバーンの体に流れる血液は魔界のマグマと同じ成分でできている。オリハルコンをも腐食させる強酸、常軌を逸した超高温。
それに点火すればこのように、万象焼き尽くす神火となって具現するのだ。
仮に、これを名づけるとするならば。
それに点火すればこのように、万象焼き尽くす神火となって具現するのだ。
仮に、これを名づけるとするならば。
「決めたよ、キミらはここで完全に殺す……!
バーニング・クリメイション……魔界の業火に灼かれて消えろォ―――!」
バーニング・クリメイション……魔界の業火に灼かれて消えろォ―――!」
掲げられた右腕を振りおろし、連動して大火球もテスラの元へと投げうたれた。
超スピードで躱されることは考えない。何故ならその背後にはマスターの少女たちがいる。テスラはこれを受け止めるしかないのだ。
超スピードで躱されることは考えない。何故ならその背後にはマスターの少女たちがいる。テスラはこれを受け止めるしかないのだ。
それを悟ってか、テスラもまた自分から火球へと突貫した。燃え盛る炎が唸りを上げ、テスラの体の全てを呑みこむ。
「ら、ライダー!」
「馬鹿め、自分から死にに行ったか!」
「馬鹿め、自分から死にに行ったか!」
炎に呑まれた自分のサーヴァントを見て、南条光は絶叫した。それを遠目に見て、キルバーンは思わず愉悦にほくそ笑む。
これだ、この表情だ。
いつもそうだ、人間というものは。死に瀕すれば絶望に堕ち、仲間だ絆だと言う奴ほどそれを失うことを恐れる。寿命が短いから魔族などよりも深刻に考える、人間だけの特徴だ。
キルバーンはそういった人間の表情が大好きだった。
目の前で仲間が、頼れる誰かが燃え尽きていくのに手も足も出せない……!
そんな時に彼らが浮かべる、絶望と! 苦悩と! 悲しみに満ちた表情が!
いつもそうだ、人間というものは。死に瀕すれば絶望に堕ち、仲間だ絆だと言う奴ほどそれを失うことを恐れる。寿命が短いから魔族などよりも深刻に考える、人間だけの特徴だ。
キルバーンはそういった人間の表情が大好きだった。
目の前で仲間が、頼れる誰かが燃え尽きていくのに手も足も出せない……!
そんな時に彼らが浮かべる、絶望と! 苦悩と! 悲しみに満ちた表情が!
「火葬か。なるほど、皮肉な名だ」
けれど。
炎の中から。声、響いて。
炎の中から。声、響いて。
「しかし生憎だが、私の死に場所は既に決まっている」
にわかに、雷が迸って。
「な、何故……」
内側から掻き消すように炎を散らして、テスラが静謐の面持ちで歩む。
全身からは膨大な雷電の放出、その全てが炎を砕いて止まらない。
全身からは膨大な雷電の放出、その全てが炎を砕いて止まらない。
「如何なる熱量も、
如何なる質量も、
我が雷電を打ち砕くこと能わず」
如何なる質量も、
我が雷電を打ち砕くこと能わず」
輝く双眸が、キルバーンを見据えた。
「こんなバカなァッ!?」
絶叫して、キルバーンを腰の剣を抜き放った。
何処からともかく現れた雷がそれを砕いた。
何処からともかく現れた雷がそれを砕いた。
「くそ、くそッ!」
縦に裂かれながらも蠢いて、怒涛の勢いで吹き付ける炎熱の風を、テスラは砕く。
前に歩みながら体でぶつかるだけで砕く。
苦し紛れに再配置されたファントムレイザーを機械籠手が砕く。
再び、槍と化す炎を全身が砕く。
悉く、砕いて。砕いて。
前に歩みながら体でぶつかるだけで砕く。
苦し紛れに再配置されたファントムレイザーを機械籠手が砕く。
再び、槍と化す炎を全身が砕く。
悉く、砕いて。砕いて。
砕きつくしてしまって。
それから―――
それから―――
「―――!」
瞬間、彼の姿が消えていた。
どこへ消えた、と。相対していたキルバーンも、マスターたる光さえも視線を彷徨わせる間。既に。
どこへ消えた、と。相対していたキルバーンも、マスターたる光さえも視線を彷徨わせる間。既に。
「もういい、十分だ」
既に彼は死神の背後へと立っていた。
その両手、輝かせて―――!
その両手、輝かせて―――!
「電刃―――」
「《電位雷帝の剣先 》」
細い細い、閃光が―――
誰しもの瞳を、白く白く染め上げて―――
誰しもの瞳を、白く白く染め上げて―――
轟音が、響き渡った。
▼ ▼ ▼
「……相討ちだろうと、俺は構わなかった」
静かな、静かな声があった。
無音の静寂の中、ただその声だけが、漆黒の中に澄み渡った。
無音の静寂の中、ただその声だけが、漆黒の中に澄み渡った。
「それでも良かった。相討ち が俺達の、果たせなかった決着の形だというなら。
この命くれてやろうと、俺は腹を据えていた」
この命くれてやろうと、俺は腹を据えていた」
睥睨して語る声は、どこまでも静かだった。
「だから貴様が何をしようと構わなかった。
貴様が動いた時、喉笛を射抜いてやることだけを考えていた」
貴様が動いた時、喉笛を射抜いてやることだけを考えていた」
睥睨して放たれる声は、しかし実のところ相手に語りかける類のものではなかった。
それは己に言い聞かせるように、独り言のように、滔々と呟かれた。
それは己に言い聞かせるように、独り言のように、滔々と呟かれた。
「だが貴様は違った。この世に未練を残し、過ぎ去った過去に悔いを残し、故に最期に"勝ち"を狙った。
無用の欲をかき、小細工を弄し、そうまでして死地 を生き抜きたいと願った」
無用の欲をかき、小細工を弄し、そうまでして
口元の煙草を摘み取り、深く息を吐く。紫煙が一筋の糸のように流れた。
「故に、斯様な無様を晒すことになった。
―――なあ、抜刀斎」
「づ、あ……」
―――なあ、抜刀斎」
「づ、あ……」
そこにあったのは、全てが終わった戦場跡だった。
縦横無尽に切り裂かれたアスファルト、大小様々な無数の斬痕を残すコンクリ壁、まき散らされた鮮血。そして、勝者と敗者。
―――倒れ伏す緋村抜刀斎と、それを見下ろす斎藤一の姿だった。
最期の一瞬、龍鳴閃が放たれたあの瞬間において、抜刀斎の予想とは裏腹に斎藤は一切の動きを止めることがなかった。
一瞬止まったかのように見えたのは、あくまで技を繰り出すための予備動作だったのだ。それを、抜刀斎は見抜くことができなかった。
一瞬止まったかのように見えたのは、あくまで技を繰り出すための予備動作だったのだ。それを、抜刀斎は見抜くことができなかった。
牙突・零式。
それは間合いのない密着状態より、上体の発条のみで放たれる最強最後の牙突。
いずれ抜刀斎との決着のためにと考案し、しかし終ぞ使われることのなかった斎藤の奥の手だ。
それは間合いのない密着状態より、上体の発条のみで放たれる最強最後の牙突。
いずれ抜刀斎との決着のためにと考案し、しかし終ぞ使われることのなかった斎藤の奥の手だ。
あの一瞬、斎藤はただこの技を放つことのみを考え、しかし抜刀斎は龍鳴閃と次なる一手という"二手"を要した。
ならば先手を取れるのがどちらかなど論ずるに値せず。
順当に、ここに結果をもたらしたのだ。
ならば先手を取れるのがどちらかなど論ずるに値せず。
順当に、ここに結果をもたらしたのだ。
「そうまでして聖杯が欲しいか。貴様が信じる新時代とやらが、それほどまでに愛おしいか」
「何、を……言って……」
「何、を……言って……」
しかしそれでも、抜刀斎は死んでいなかった。
牙突が放たれたその瞬間、死地にて開眼せし剣士の閃きか、積み上げた修練による結果か。いずれによせ彼は神懸かり的な反応を示し、その直撃を避けていた。
牙突が放たれたその瞬間、死地にて開眼せし剣士の閃きか、積み上げた修練による結果か。いずれによせ彼は神懸かり的な反応を示し、その直撃を避けていた。
無論、それが無傷という結果に繋がるわけではないのは一目瞭然だ。
常人であった生前ですら、ティンベーと呼ばれる堅固な盾ごと人体を真っ二つにする威力を誇る零式だ。サーヴァントとなり、宝具として昇華された現在において、それは対人宝具として遜色ない比類なき威力を誇る。
事実、抜刀斎は虫の息だ。口からは赤色の濁流が止め処なく垂れ流され、周囲は血の海に沈んでいる。未だ人の形を保っているというそれ自体は奇跡的な事態ではあったが、それだけである。
常人であった生前ですら、ティンベーと呼ばれる堅固な盾ごと人体を真っ二つにする威力を誇る零式だ。サーヴァントとなり、宝具として昇華された現在において、それは対人宝具として遜色ない比類なき威力を誇る。
事実、抜刀斎は虫の息だ。口からは赤色の濁流が止め処なく垂れ流され、周囲は血の海に沈んでいる。未だ人の形を保っているというそれ自体は奇跡的な事態ではあったが、それだけである。
勝敗は決した。
人斬り抜刀斎と呼ばれた剣客は、ここに敗北を喫したのだ。
人斬り抜刀斎と呼ばれた剣客は、ここに敗北を喫したのだ。
「だがな、よく見ろ。この世界を。この街並みを。
戦もなく、疫病もなく、飢餓もない世の在り方を」
戦もなく、疫病もなく、飢餓もない世の在り方を」
哀れむでもなく、斎藤はただ言った。
倒れる抜刀斎の頭を掴み、高く掲げて。
倒れる抜刀斎の頭を掴み、高く掲げて。
「無論世に悲劇の種は尽きんだろうがな。しかし、貴様が目指した新時代とやらは、既に実現してるんだよ。
貴様や俺達のような過去を生きた人間、そして今を生きる人間によってな」
「あ……」
貴様や俺達のような過去を生きた人間、そして今を生きる人間によってな」
「あ……」
見せつける。目を逸らせないよう、徹底的に。
かつて維新の志士たちが、幕府を守ろうとした剣士たちが。共に夢見、築き上げようとした未来の形を。
かつて維新の志士たちが、幕府を守ろうとした剣士たちが。共に夢見、築き上げようとした未来の形を。
「時代は変えるものじゃない、変わっていくものだ。
そして時代を作り上げるのは、その世を生きる全ての人間だ。死者(おれたち)じゃない」
そして時代を作り上げるのは、その世を生きる全ての人間だ。死者(おれたち)じゃない」
それは、あるいは手向けであったのかもしれない。
その身を貫く剣の一撃ではなく、あえて言葉によって、斎藤はこの"歪められてしまった"宿敵に最後の慈悲を与えた。
ひとりの人間として新時代を生きた、心優しき不殺の剣士を知る者として。
その身を貫く剣の一撃ではなく、あえて言葉によって、斎藤はこの"歪められてしまった"宿敵に最後の慈悲を与えた。
ひとりの人間として新時代を生きた、心優しき不殺の剣士を知る者として。
「まだ、だ……俺は、生きて……」
顔を掴まれ、その半ば以上を影に落とす抜刀斎が虚ろに言葉を漏らす。それは生きるという渇望か、願いを諦めきれないという悔恨か。
しかし、斎藤はそれを聞き届けることはなかった。龍鳴閃によって破壊された聴覚は未だ治癒していないのだ。
しかし、斎藤はそれを聞き届けることはなかった。龍鳴閃によって破壊された聴覚は未だ治癒していないのだ。
斎藤が手を離す。支えを失った抜刀斎の体が崩れ落ち、血の雫が飛び散った。
倒れ伏した抜刀斎を見下ろし、斎藤は今一度、腰の刀を抜き放つ。
一切の欠けがない白刃が、月光を反射して妖しく煌めいた。
振り上げられた切っ先が天頂を向く。物打ちが狙い定めるのは、首級。
倒れ伏した抜刀斎を見下ろし、斎藤は今一度、腰の刀を抜き放つ。
一切の欠けがない白刃が、月光を反射して妖しく煌めいた。
振り上げられた切っ先が天頂を向く。物打ちが狙い定めるのは、首級。
風切る音と共に、刃が今、振り下ろされた。
▼ ▼ ▼
「ちぃ、どこまで行きゃいいんだよ」
夜の街に聳えるビルを、風のように飛び交う影がひとつ。
月の光を反射して、きらりと光る長い髪は、白銀。
恵まれた体躯をした、男の影だ。夜街を駆ける、加藤鳴海だ。
月の光を反射して、きらりと光る長い髪は、白銀。
恵まれた体躯をした、男の影だ。夜街を駆ける、加藤鳴海だ。
「あ、あの……」
「? おう」
「なんか、すみません。うちのルーザーが色々と失礼なことをして……」
「……いや、いいさ。アンタは多分悪くないだろ」
「? おう」
「なんか、すみません。うちのルーザーが色々と失礼なことをして……」
「……いや、いいさ。アンタは多分悪くないだろ」
男の背から、ひょっこりと顔を出すみく。それに、鳴海は多少無愛想に対応した。
別に嫌いであるとか、敵意があるわけではない。ただ単に、距離感が分からないだけだ。
別に嫌いであるとか、敵意があるわけではない。ただ単に、距離感が分からないだけだ。
「っと、こんなところでいいか」
手近なビルの屋上へと着地し、鳴海は言う。背負ったみくを降ろし、腕に抱いていた未央―――未だ失神している―――を優しげな手つきでみくに渡した。
「……未央ちゃん、生きてる。本当に、生きてた……」
「ああ……そういやアンタ、俺のマスターの友達なんだってな」
「ああ……そういやアンタ、俺のマスターの友達なんだってな」
眠る未央を掻き抱き、みくはここに来てようやく、彼女が生きていたのだという実感が湧いたのか、言葉を震わせて涙ぐんでいた。
それを見下ろす鳴海は、何とも言えない、けれどその奥に優しさを秘めたような目つきをしていた。
それを見下ろす鳴海は、何とも言えない、けれどその奥に優しさを秘めたような目つきをしていた。
「……ありがとな。俺のマスターを気遣ってくれて」
「ううん、私なんて何も……あなたこそ、今まで未央ちゃんのこと助けようとしてくださって、ありがとうございます」
「ううん、私なんて何も……あなたこそ、今まで未央ちゃんのこと助けようとしてくださって、ありがとうございます」
何ともぎこちない、不器用な会話であった。
それもそうだろう。何せ二人は、つい先ほどまで敵と言っていい関係だったのだから。
その垣根を壊したのは、みくのサーヴァントたるルーザーだった。
それもそうだろう。何せ二人は、つい先ほどまで敵と言っていい関係だったのだから。
その垣根を壊したのは、みくのサーヴァントたるルーザーだった。
―――単刀直入に言おう。僕は今からこいつを殺す。とはいえだ、実はちょーっと厄介な問題があってね。
―――まあ具体的には僕にも分かってないんだけどさ。でも一つ言えるのは、こいつを殺す現場に僕やきみのマスターを近づけちゃ駄目ってことだ。
―――そういうわけで、きみには今から二人を連れて遠くまで逃げてもらうよ。なに、きみのマスターを助けたことを思えば軽いもんだろ?
―――まあ具体的には僕にも分かってないんだけどさ。でも一つ言えるのは、こいつを殺す現場に僕やきみのマスターを近づけちゃ駄目ってことだ。
―――そういうわけで、きみには今から二人を連れて遠くまで逃げてもらうよ。なに、きみのマスターを助けたことを思えば軽いもんだろ?
―――まさかとは思うけど、本田ちゃんの親友なうちのマスターを殺したりはしねえよな?
思い出すのは、病院にて交わされたルーザーとの会話だ。いや、会話というよりは一方的な講義であったが。
それが終わった瞬間、鳴海に打ち込まれた螺子は綺麗さっぱり消えて無くなり、鳴海は正気を取り戻した。そして彼の言うままに、二人を連れて逃避行と相成っていた。
それが終わった瞬間、鳴海に打ち込まれた螺子は綺麗さっぱり消えて無くなり、鳴海は正気を取り戻した。そして彼の言うままに、二人を連れて逃避行と相成っていた。
鳴海としては、最初からみくを殺すつもりなどなかった。未央の親友云々もそうだが、マスターの、それも子供を殺すなんて真似を、彼がするはずもない。
けれど。
けれど。
(……今からどうすりゃいいんだ、これ)
鳴海はサーヴァントを打倒することによる聖杯の獲得を狙っていた。サーヴァントを失ったマスターはこの世界の消失と共に消えてなくなることを、それが問題を先延ばしにするだけの逃避であることを承知の上で。
けれど、こうして未央の親友である前川みくがマスターとして現れた。現れてしまった。
死なせるわけにはいかなかった。本田未央の笑顔を取り戻すという、かつて誓った想いに懸けて。
けれど、こうして未央の親友である前川みくがマスターとして現れた。現れてしまった。
死なせるわけにはいかなかった。本田未央の笑顔を取り戻すという、かつて誓った想いに懸けて。
ならば、自分はどうすべきなのだろうか。
泣きじゃくるみくを見下ろす鳴海は、未だ纏まらない思考で呟いた。
自分はどうするべきなのか、と。
泣きじゃくるみくを見下ろす鳴海は、未だ纏まらない思考で呟いた。
自分はどうするべきなのか、と。
『C-9/ビル屋上/二日目・深夜』
【本田未央@アイドルマスターシンデレラガールズ(アニメ)】
[状態]失血(中)、魔力消費(小)、失神
[令呪]残り3画
[装備]なし
[道具]なし
[金銭状況]着の身着のままで病院に搬送されたので0
[思考・状況]
基本行動方針:疲れたし、もう笑えない。けれど、アイドルはやめたくない。
1.いつか、心の底から笑えるようになりたい。
2.加藤鳴海に対して僅かながらの信頼。
[備考]
前川みくと同じクラスです。
前川みくと同じ事務所に所属しています、デビューはまだしていません。
気絶していたのでアサシン(あやめ)を認識してません。なので『感染』もしていません。
自室が割と酷いことになってます。
C-8に存在する総合病院に担ぎ込まれました。現在は脱走中の身です。
家族が全滅したことをまだ知りません。
[状態]失血(中)、魔力消費(小)、失神
[令呪]残り3画
[装備]なし
[道具]なし
[金銭状況]着の身着のままで病院に搬送されたので0
[思考・状況]
基本行動方針:疲れたし、もう笑えない。けれど、アイドルはやめたくない。
1.いつか、心の底から笑えるようになりたい。
2.加藤鳴海に対して僅かながらの信頼。
[備考]
前川みくと同じクラスです。
前川みくと同じ事務所に所属しています、デビューはまだしていません。
気絶していたのでアサシン(あやめ)を認識してません。なので『感染』もしていません。
自室が割と酷いことになってます。
C-8に存在する総合病院に担ぎ込まれました。現在は脱走中の身です。
家族が全滅したことをまだ知りません。
【しろがね(加藤鳴海)@からくりサーカス】
[状態]精神疲労(中)
[装備]拳法着
[道具]なし。
[思考・状況]
基本行動方針:本田未央の笑顔を取り戻す。
0.これからどうするべきか。
1.全てのサーヴァントを打倒する。しかしマスターは決して殺さない。
2.この聖杯戦争の裏側を突き止める。
3.本田未央の傍にいる。
4.学生服のサーヴァントは絶対に倒す……?
[備考]
ネギ・スプリングフィールド及びそのサーヴァント(金木研)を確認しました。ネギのことを初等部の生徒だと思っています。
前川みくをマスターと認識しました。
アサシン(あやめ)をぎりぎり見てません。
[状態]精神疲労(中)
[装備]拳法着
[道具]なし。
[思考・状況]
基本行動方針:本田未央の笑顔を取り戻す。
0.これからどうするべきか。
1.全てのサーヴァントを打倒する。しかしマスターは決して殺さない。
2.この聖杯戦争の裏側を突き止める。
3.本田未央の傍にいる。
4.学生服のサーヴァントは絶対に倒す……?
[備考]
ネギ・スプリングフィールド及びそのサーヴァント(金木研)を確認しました。ネギのことを初等部の生徒だと思っています。
前川みくをマスターと認識しました。
アサシン(あやめ)をぎりぎり見てません。
【前川みく@アイドルマスターシンデレラガールズ(アニメ)】
[状態]魔力消費(中)、決意
[令呪]残り三画
[装備]なし
[道具]学生服、ネコミミ(しまってある)
[金銭状況]普通。
[思考・状況]
基本行動方針:聖杯を取るのかどうか、分からない。けれど、何も知らないまま動くのはもうやめる。
1.人を殺すからには、ちゃんと相手のことを知らなくちゃいけない。無知のままではいない。
2.音無結弦に会う。未央は生きていたが、それとこれとは話が別。
[備考]
本田未央と同じクラスです。学級委員長です。
本田未央と同じ事務所に所属しています、デビューはまだしていません。
事務所の女子寮に住んでいます。他のアイドルもいますが、詳細は後続の書き手に任せます。
本田未央、音無結弦をマスターと認識しました。
アサシン(あやめ)を認識しました。
[状態]魔力消費(中)、決意
[令呪]残り三画
[装備]なし
[道具]学生服、ネコミミ(しまってある)
[金銭状況]普通。
[思考・状況]
基本行動方針:聖杯を取るのかどうか、分からない。けれど、何も知らないまま動くのはもうやめる。
1.人を殺すからには、ちゃんと相手のことを知らなくちゃいけない。無知のままではいない。
2.音無結弦に会う。未央は生きていたが、それとこれとは話が別。
[備考]
本田未央と同じクラスです。学級委員長です。
本田未央と同じ事務所に所属しています、デビューはまだしていません。
事務所の女子寮に住んでいます。他のアイドルもいますが、詳細は後続の書き手に任せます。
本田未央、音無結弦をマスターと認識しました。
アサシン(あやめ)を認識しました。
▼ ▼ ▼
それは、全ての因縁が終末へと差し掛かった時のこと。
歪められた人斬りの鬼へと、人を嘲笑う道化人形へと、その刃が振り下ろされようとした時のこと。
歪められた人斬りの鬼へと、人を嘲笑う道化人形へと、その刃が振り下ろされようとした時のこと。
『さて』
『ここが終だよ、カワイコちゃん』
周囲に誰もいない、街の中。
ただ一人立つ球磨川は、常と全く変わらない面持ちでそう言った。
ただ一人立つ球磨川は、常と全く変わらない面持ちでそう言った。
『僕は今からきみを殺す。いや、サーヴァントどころか怪異でしかないきみに、この形容は不適切かな』
『ともあれだ、僕はきみをここで終わらせる。僕だけならともかく、みくにゃちゃんまで巻き込むのは本意じゃないからね』
『仕方ない、ああ仕方ないとも。そういうわけでだ』
『ともあれだ、僕はきみをここで終わらせる。僕だけならともかく、みくにゃちゃんまで巻き込むのは本意じゃないからね』
『仕方ない、ああ仕方ないとも。そういうわけでだ』
語る球磨川の腕には、一人の少女が掴まれていた。
透き通るかのような長い黒髪、臙脂の服。奇妙なまでに古風な、それでいて神秘的な。そんな少女が、掲げられていた。
透き通るかのような長い黒髪、臙脂の服。奇妙なまでに古風な、それでいて神秘的な。そんな少女が、掲げられていた。
『ベタな台詞だけどね、一応言っておかなきゃいけない。
最期に言い残すことはあるかい?』
「わた、しは……」
最期に言い残すことはあるかい?』
「わた、しは……」
微かに唇開く。鼻先より上は影になって、球磨川からはよく見えない。
「……ますたーに」
『うん?』
「わたしのますたーに会うことがあれば、一つだけ」
『……いいよ、聞こう』
『うん?』
「わたしのますたーに会うことがあれば、一つだけ」
『……いいよ、聞こう』
彼にしては、珍しく。
心持ち穏やかな声で。
ただ、その言葉を聞いた。
心持ち穏やかな声で。
ただ、その言葉を聞いた。
「……たった数日でしたけど、わたしはとても楽しかったです、とだけ。お願いします」
語る少女の頬には。
つぅと一筋、伝って落ちるものがあった。
つぅと一筋、伝って落ちるものがあった。
『……OK、会うことがあれば伝えよう』
そのまま、逆の腕に持つ螺子を構え。
少女の胸に、突き刺した。
少女の胸に、突き刺した。
――――――世界がはじけ飛んだ。
▼ ▼ ▼
例えるなら、風船がぱちんと割れるように。
空間が弾けた。世界が弾けた。あまりにも呆気なく、簡単に。普通の世界は【なかった】ことになった。
より正確に形容するなら、あやめとは風船に描かれた人物画だったのだ。世界は風景画であり、風船に描かれた背景。あやめはその一部。そこに螺子を突き刺して、割れた。
空間が弾けた。世界が弾けた。あまりにも呆気なく、簡単に。普通の世界は【なかった】ことになった。
より正確に形容するなら、あやめとは風船に描かれた人物画だったのだ。世界は風景画であり、風船に描かれた背景。あやめはその一部。そこに螺子を突き刺して、割れた。
世界と異世界を隔てる壁は、かくして脆くも崩れ去った。
風船が弾けるように空間がめくれて、その向こうにある"本物"の風景が露出した。
一瞬で世界は塗り潰された。
一瞬で世界は塗り潰された。
……………。
影絵のビルが、摩天楼のように突き立っていた。
無機的な光を放つ街灯が、等間隔で真っ直ぐ並んでいた。まるで葬列のように、ずらりと、遠くまで。
無機的な光を放つ街灯が、等間隔で真っ直ぐ並んでいた。まるで葬列のように、ずらりと、遠くまで。
街の中心。
誰もが、空を見上げていた。
誰もが、空を見上げていた。
夜空は、真っ赤だった。
絵具をぶちまけたように、そこは一色の赤だった。赤い空に、月が、まるで巨大な眼球のように"ぬらり"とした光沢で浮かんでいた。ぽっかりと浮かぶグロテスクな月が、ビルや街灯の影を地に落としていた。
影は、赤い。
赤く、長く、それを映す街路樹は、元の青々とした色を失っているのだった。
葉も、幹も、枝も。白く色褪せ、瑞々しいまでの枯草色と化していた。
赤い闇に、失われた命の色。それが、この世界を構築する全てだった。
絵具をぶちまけたように、そこは一色の赤だった。赤い空に、月が、まるで巨大な眼球のように"ぬらり"とした光沢で浮かんでいた。ぽっかりと浮かぶグロテスクな月が、ビルや街灯の影を地に落としていた。
影は、赤い。
赤く、長く、それを映す街路樹は、元の青々とした色を失っているのだった。
葉も、幹も、枝も。白く色褪せ、瑞々しいまでの枯草色と化していた。
赤い闇に、失われた命の色。それが、この世界を構築する全てだった。
耳鳴りが酷い。
気圧が違うのだろうか。だが、大気そのものが違うのだろう。この異界に堕とされた者は、誰もがそれを感覚的に捉えていた。
空気の香りが違うのだ。
やけに乾燥した、その"猛烈な枯草の匂いに微かに鉄錆を混ぜたような"奇妙な香りのする空気は、今まで誰もが呼吸したことのない種類のものだった。
弾けるように世界が切り替わった瞬間、濃密に周囲の空間に満ちた空気だった。
狂った世界の空気だった。
気圧が違うのだろうか。だが、大気そのものが違うのだろう。この異界に堕とされた者は、誰もがそれを感覚的に捉えていた。
空気の香りが違うのだ。
やけに乾燥した、その"猛烈な枯草の匂いに微かに鉄錆を混ぜたような"奇妙な香りのする空気は、今まで誰もが呼吸したことのない種類のものだった。
弾けるように世界が切り替わった瞬間、濃密に周囲の空間に満ちた空気だった。
狂った世界の空気だった。
そこにいた全員が、異なる世界に呑まれていた。
下手人たる球磨川禊も。
いざ決着を付けんとする二人の剣客も。
外敵を退け歓喜する少女たちも。
敗れ去った道化師も。
ただ逃避する少年も。
いざ決着を付けんとする二人の剣客も。
外敵を退け歓喜する少女たちも。
敗れ去った道化師も。
ただ逃避する少年も。
全てが、ここでは平等だった。
その日、世界は本物の"異界"となった。
………。
……。
…。
―――――――――――――――――。
▼ ▼ ▼
『大嘘吐き 』
『僕への干渉を【なかった】ことにした』
こつん、と。
道路に降り立つ者がいた。それは、夜よりも尚暗い学生服を着て。
けれども常に浮かべている薄気味悪い笑みは、鳴りを潜め。
混沌よりも這い寄る過負荷、球磨川禊は現実世界への帰還を果たしていた。
けれども常に浮かべている薄気味悪い笑みは、鳴りを潜め。
混沌よりも這い寄る過負荷、球磨川禊は現実世界への帰還を果たしていた。
余人には分かるまい、直前まで彼が一体どこにいたのかを。
何も変わらぬように見える街並み。彼が踏みしめる地点より、あと一歩でも後ろに下がればどうなるか。
何もないように見えるその境界を踏み越えれば、途端に世界が様変わりするのだということに。
気付く者は、いない。
何も変わらぬように見える街並み。彼が踏みしめる地点より、あと一歩でも後ろに下がればどうなるか。
何もないように見えるその境界を踏み越えれば、途端に世界が様変わりするのだということに。
気付く者は、いない。
『薄々感づいちゃいたけど、こりゃ正直予想以上だ。斜め上というか、急降下爆撃というか。
まあ僕の予想が当たったことなんてまるで覚えがないんだけどさ』
まあ僕の予想が当たったことなんてまるで覚えがないんだけどさ』
してやられた、というよりは。
幾度も味わい、けれど決して慣れることのないある感覚に襲われて。
球磨川は、その表情を渋いものとしていた。
幾度も味わい、けれど決して慣れることのないある感覚に襲われて。
球磨川は、その表情を渋いものとしていた。
『やられたよ。まんまとしてやられた。こんな状況に追い込まれた時点で、僕は負けたも同然だったんだ』
例えみくを守るためだとしても。
例え惚れた相手を助けるためだとしても。
例え惚れた相手を助けるためだとしても。
無抵抗な女の子を一方的に傷つけてしまうなんて。
『また、勝てなかった』
そんなもの、徹頭徹尾どうしようもなく【敗北】でしかないだろう。
『C-8/街中/二日目・深夜』
【ルーザー(球磨川禊)@めだかボックス】
[状態]『……僕だってセンチな気分になることはあるよ』
[装備]『いつもの学生服だよ、新品だからピカピカさ』
[道具]『螺子がたくさんあるよ、お望みとあらば裸エプロンも取り出せるよ!』
[思考・状況]
基本行動方針:『聖杯、ゲットだぜ!』
0.『また、勝てなかった』
1.『みくにゃちゃんに惚れちまったぜ、いやぁ見事にやられちゃったよ』
2.『裸エプロンとか言ってられる状況でも無くなってきたみたいだ。でも僕は自分を曲げないよ!』
3.『道化師(ジョーカー)はみんな僕の友達―――だと思ってたんだけどね』
4.『ぬるい友情を深めようぜ、サーヴァントもマスターも関係なくさ。その為にも色々とちょっかいをかけないとね』
5.『本田ちゃん、生きてたねえ』『みくにゃちゃんはこれからどうするのかな?』
[備考]
瑞鶴、鈴音、クレア、テスラへとチャットルームの誘いをかけました。
帝人と加蓮が使っていた場所です。
本田未央、音無結弦をマスターと認識しました。
アサシン(あやめ)を認識しました。彼女の消滅により感染は解除されました。
※音無主従、南条主従、未央主従、超、クレア、瑞鶴を把握。
[状態]『……僕だってセンチな気分になることはあるよ』
[装備]『いつもの学生服だよ、新品だからピカピカさ』
[道具]『螺子がたくさんあるよ、お望みとあらば裸エプロンも取り出せるよ!』
[思考・状況]
基本行動方針:『聖杯、ゲットだぜ!』
0.『また、勝てなかった』
1.『みくにゃちゃんに惚れちまったぜ、いやぁ見事にやられちゃったよ』
2.『裸エプロンとか言ってられる状況でも無くなってきたみたいだ。でも僕は自分を曲げないよ!』
3.『道化師(ジョーカー)はみんな僕の友達―――だと思ってたんだけどね』
4.『ぬるい友情を深めようぜ、サーヴァントもマスターも関係なくさ。その為にも色々とちょっかいをかけないとね』
5.『本田ちゃん、生きてたねえ』『みくにゃちゃんはこれからどうするのかな?』
[備考]
瑞鶴、鈴音、クレア、テスラへとチャットルームの誘いをかけました。
帝人と加蓮が使っていた場所です。
本田未央、音無結弦をマスターと認識しました。
アサシン(あやめ)を認識しました。彼女の消滅により感染は解除されました。
※音無主従、南条主従、未央主従、超、クレア、瑞鶴を把握。
▼ ▼ ▼
「また、面倒なことを」
中空に、迸る一条の閃光。
瞬いた瞬間には、既に人の形を取っていた。
瞬いた瞬間には、既に人の形を取っていた。
「現象数式領域か、あるいは《結社》の心理強制空間か。
どちらでもないのだろうな。酷似こそしてはいるが、あれは異界法則そのものだ」
どちらでもないのだろうな。酷似こそしてはいるが、あれは異界法則そのものだ」
両の手には、それぞれ気絶した少女を一人ずつ抱えている。必要だったから、咄嗟に彼がそうした。
あれは人の認識に訴えるものだ。経験上それが分かっていたから、即座に気を失わさせた。見ないものは無いも同然、その理屈である。
あれは人の認識に訴えるものだ。経験上それが分かっていたから、即座に気を失わさせた。見ないものは無いも同然、その理屈である。
「あれを見ては、私の《恐怖麻痺》も通じまい。願わくば、あれに巻き込まれた者が少ないことを祈るしかないが……」
そう言って、テスラは傍らの少女に目線をやる。
「まずはこの少女の治療が先だな。早急な対応が必要になる」
そうして、彼はどこか遠い場所を見つめるように。
瞼を細めた。あるいは、何かを考えているのか。
瞼を細めた。あるいは、何かを考えているのか。
「……道化人形は逃がしてしまったか。しかし、あれも長くはあるまい。
影潜む者は同じく影潜む者に討たれる。それが関の山であろうよ」
影潜む者は同じく影潜む者に討たれる。それが関の山であろうよ」
それだけを残すと、テスラは夜の中へと消えて行った。
雷電魔人、未だ倒れることはなく。
雷電魔人、未だ倒れることはなく。
【C-8/無人の街中/二日目・深夜】
【仲村ゆり@Angel Beats!】
[状態]不調、全身にダメージ、気絶
[令呪]残り三画
[装備]私服姿、リボン付カチューシャ
[道具]お出掛けバック
[金銭状況]普通の学生よりは多い
[思考・状況]
基本行動方針:ふざけた神様をぶっ殺す、聖杯もぶっ壊す。
0.……
1.とりあえず、音無と行動。
2.赤毛の男(サーシェス)を警戒する。 死神(キルバーン)、金髪(ボッシュ)、化物(ブレードトゥース)は必ず殺す。
[備考]
学園を大絶賛サポタージュ中。
家出もしています。寝床に関しては後続の書き手にお任せします。
赤毛の男(サーシェス)の名前は知りません。
ケイジと共闘戦線を結びました。
音無結弦と同盟を結びました。
音無が対聖杯方針であると誤認しています。
異界を認識しなかったことにより、その精神にも影響は出ていません。
[状態]不調、全身にダメージ、気絶
[令呪]残り三画
[装備]私服姿、リボン付カチューシャ
[道具]お出掛けバック
[金銭状況]普通の学生よりは多い
[思考・状況]
基本行動方針:ふざけた神様をぶっ殺す、聖杯もぶっ壊す。
0.……
1.とりあえず、音無と行動。
2.赤毛の男(サーシェス)を警戒する。 死神(キルバーン)、金髪(ボッシュ)、化物(ブレードトゥース)は必ず殺す。
[備考]
学園を大絶賛サポタージュ中。
家出もしています。寝床に関しては後続の書き手にお任せします。
赤毛の男(サーシェス)の名前は知りません。
ケイジと共闘戦線を結びました。
音無結弦と同盟を結びました。
音無が対聖杯方針であると誤認しています。
異界を認識しなかったことにより、その精神にも影響は出ていません。
【南条光@アイドルマスターシンデレラガールズ】
[状態]健康、気絶
[令呪]残り三画
[装備]深淵の鍵"ペルクナス"
[道具]
[金銭状況]それなり(光が所持していた金銭に加え、ライダーが稼いできた日銭が含まれている)
[思考・状況]
基本行動方針:打倒聖杯!
0.……
1.聖杯戦争を止めるために動く。しかし、その為に動いた結果、何かを失うことへの恐れ。
2.無関係な人を巻き込みたくない、特にミサカ。
[備考]
C-9にある邸宅に一人暮らし。
異界を認識しなかったことにより、その精神にも影響は出ていません。
学校鞄(中身は勉強道具一式)、思い出のプリクラは家に置いてます。
[状態]健康、気絶
[令呪]残り三画
[装備]深淵の鍵"ペルクナス"
[道具]
[金銭状況]それなり(光が所持していた金銭に加え、ライダーが稼いできた日銭が含まれている)
[思考・状況]
基本行動方針:打倒聖杯!
0.……
1.聖杯戦争を止めるために動く。しかし、その為に動いた結果、何かを失うことへの恐れ。
2.無関係な人を巻き込みたくない、特にミサカ。
[備考]
C-9にある邸宅に一人暮らし。
異界を認識しなかったことにより、その精神にも影響は出ていません。
学校鞄(中身は勉強道具一式)、思い出のプリクラは家に置いてます。
【ライダー(ニコラ・テスラ)@黄雷のガクトゥーン ~What a shining braves~】
[状態]魔力消費(小・急速回復中)、南条光と仲村ゆりを抱えている。
[装備]なし
[道具]メモ帳、ペン、スマートフォン 、ルーザーから渡されたチャットのアドレス
[思考・状況]
基本行動方針:聖杯を破壊し、マスター(南条光)を元いた世界に帰す。
0.さて……
1.マスターを守護する。
2.負のサーヴァント(球磨川禊)に微かな期待と程々の警戒。
3.負のサーヴァント(球磨川禊)のチャットルームに顔を出してみる。
[備考]
一日目深夜にC-9全域を索敵していました。少なくとも一日目深夜の間にC-9にサーヴァントの気配を持った者はいませんでした。
主従同士で会う約束をライダー(ガン・フォール)と交わしました。連絡先を渡しました。
個人でスマホを持ってます。機関技術のスキルにより礼装化してあります。
キルバーンに付着していた金属片に気付きました。
[状態]魔力消費(小・急速回復中)、南条光と仲村ゆりを抱えている。
[装備]なし
[道具]メモ帳、ペン、スマートフォン 、ルーザーから渡されたチャットのアドレス
[思考・状況]
基本行動方針:聖杯を破壊し、マスター(南条光)を元いた世界に帰す。
0.さて……
1.マスターを守護する。
2.負のサーヴァント(球磨川禊)に微かな期待と程々の警戒。
3.負のサーヴァント(球磨川禊)のチャットルームに顔を出してみる。
[備考]
一日目深夜にC-9全域を索敵していました。少なくとも一日目深夜の間にC-9にサーヴァントの気配を持った者はいませんでした。
主従同士で会う約束をライダー(ガン・フォール)と交わしました。連絡先を渡しました。
個人でスマホを持ってます。機関技術のスキルにより礼装化してあります。
キルバーンに付着していた金属片に気付きました。
▼ ▼ ▼
それは、発生した異界が収縮するように消え去った後のこと。
「くそ……ボクを馬鹿にしやがって……」
這いずるように遠ざかっていく。
それは人型をしながら、しかし人よりも遥かに小さい影。子供よりも尚小さい。
負った傷を自前で癒しながら、けれども完治には程遠く。痛みをおして遠ざかり行く。
それは人型をしながら、しかし人よりも遥かに小さい影。子供よりも尚小さい。
負った傷を自前で癒しながら、けれども完治には程遠く。痛みをおして遠ざかり行く。
現状、彼を蝕んでいるのは肉体的な損傷の他に、精神的なそれも含まれていた。
かの赤い空を見た瞬間、ピロロはあらゆる思考と感情が消し飛んで脳内が漂白される感触を経験した。それは画布に塗られた少量の絵具が、大津波で諸共に押し流されるように。彼の感性は一時的な喪失状態となっていた。
かの赤い空を見た瞬間、ピロロはあらゆる思考と感情が消し飛んで脳内が漂白される感触を経験した。それは画布に塗られた少量の絵具が、大津波で諸共に押し流されるように。彼の感性は一時的な喪失状態となっていた。
元が魔界の存在である彼は、それでも辛うじて異界の消滅まで耐えきることができたが。
精神に刻まれた傷は、癒されることなく彼の心象に深く根付いた。
精神に刻まれた傷は、癒されることなく彼の心象に深く根付いた。
「いや……いや、まだだ……まだ誰もボクをサーヴァントだとは気付いてない。ならまだチャンスはある……!」
ピロロの持つスキルに、正体秘匿というものがある。
生前においてその正体を誰にも知られることなく、最終目的を完遂する直前まで行ったという逸話が昇華したこのスキルは、文字通りピロロの正体を絶対的に隠匿するというものだ。
契約を結んだマスターであろうとも、ピロロをサーヴァントとして認識することは誰にもできない。ピロロは単なる使い魔としてしか表示されず、アサシンのサーヴァントとして認識されるのはあくまでキルバーン。彼を身代わりに、ピロロは如何なる危難であろうとも逃れ得る。
例えばつい先ほどのように。
生前においてその正体を誰にも知られることなく、最終目的を完遂する直前まで行ったという逸話が昇華したこのスキルは、文字通りピロロの正体を絶対的に隠匿するというものだ。
契約を結んだマスターであろうとも、ピロロをサーヴァントとして認識することは誰にもできない。ピロロは単なる使い魔としてしか表示されず、アサシンのサーヴァントとして認識されるのはあくまでキルバーン。彼を身代わりに、ピロロは如何なる危難であろうとも逃れ得る。
例えばつい先ほどのように。
「魔力なんてそこらの連中を殺せばどうとでもなる……キルバーンさえあればボクがやられることなんてないんだ……!
そうさ、誰もボクの正体を知ることなんてないんだから……!」
そうさ、誰もボクの正体を知ることなんてないんだから……!」
故に、ピロロは下卑た笑みを絶やすことなく、次なる行動へと移るのだ。
どんな状況に追い込まれても、自分には再起の芽が存在する。
何故なら誰も、例え裁定者であろうとも、自身の正体を知ることはありえないのだから!
どんな状況に追い込まれても、自分には再起の芽が存在する。
何故なら誰も、例え裁定者であろうとも、自身の正体を知ることはありえないのだから!
――――――――――――――――――。
『こんにちは、ピロロ』
――――――――――――――――――。
正体を知られることは、ありえない。
その、はずだ。
その、はずだ。
【C-8/無人の街中/二日目・深夜】
【アサシン(キルバーン)@DRAGON QUEST -ダイの大冒険- 】
[状態]全壊、死神の笛全壊、ファントムレイザー喪失
[装備]いつも通り
[道具]なし
[思考・状況]
基本行動方針:マスターに付き合い、聖杯戦争を楽しむ。
1. ……
[備考]
身体の何処かにT-1000の液体金属が付着しています。
[状態]全壊、死神の笛全壊、ファントムレイザー喪失
[装備]いつも通り
[道具]なし
[思考・状況]
基本行動方針:マスターに付き合い、聖杯戦争を楽しむ。
1. ……
[備考]
身体の何処かにT-1000の液体金属が付着しています。
【アサシン(ピロロ)@DRAGON QUEST -ダイの大冒険-】
[状態]魔力消費(中)、ダメージ(大・ホイミにより回復中)、精神疲労(極大)、ストック0
[装備]いつも通り
[道具]なし
[思考・状況]
基本行動方針:マスターに付き合い、聖杯戦争を楽しむ。
0.今は逃げる。
1.とにかくキルバーンを復活させられるだけの魔力を補充する。手段は問わない。
[備考]
緊急事態であったため、まだT-1000の液体金属には気付いていません。
しかしじっくり観察すれば気付く事ができます。
異界を認識したことにより一時的発狂状態に陥りました。もう回復しました。
[状態]魔力消費(中)、ダメージ(大・ホイミにより回復中)、精神疲労(極大)、ストック0
[装備]いつも通り
[道具]なし
[思考・状況]
基本行動方針:マスターに付き合い、聖杯戦争を楽しむ。
0.今は逃げる。
1.とにかくキルバーンを復活させられるだけの魔力を補充する。手段は問わない。
[備考]
緊急事態であったため、まだT-1000の液体金属には気付いていません。
しかしじっくり観察すれば気付く事ができます。
異界を認識したことにより一時的発狂状態に陥りました。もう回復しました。
▼ ▼ ▼
「俺は……生き残ったのか」
壁に寄り掛かるようにして辛うじて立つ人影が一つ。
夥しい量の血液を流し、無残に切り裂かれた装いで、しかし手に持つ剣だけは決して手放すことなく、緋村抜刀斎は這いずるように歩を進めていた。
夥しい量の血液を流し、無残に切り裂かれた装いで、しかし手に持つ剣だけは決して手放すことなく、緋村抜刀斎は這いずるように歩を進めていた。
「どうなったんだ……俺は、あの時……斎藤は……」
斎藤に敗れ倒れた後、次に目を開いた時には全てが終わっていた。枯草と、僅かな鉄錆が混じったような香りが鼻腔に広がったかと思えば。
凪いでいた。半刻前のように、元治元年の冬のように。
凪いでいた。半刻前のように、元治元年の冬のように。
あらゆる物が、消え失せていた。
宿敵たる、斎藤一でさえも。
宿敵たる、斎藤一でさえも。
「どこだ……」
……流血は既に止まっている。損傷は全快には程遠いが、致命傷に成り得ないだけの浅さまで無理やりに補填が完了している。
身に宿す魔力を用いれば、この程度は魔術の素養のない抜刀斎であろうとも、サーヴァントに備わった治癒能力として再生が可能であった。無論、元々の貯蔵量の少なさと魔力ステータスの低さ、そして負った傷の深さからか、瀕死の重傷であることに変わりはないが。
身に宿す魔力を用いれば、この程度は魔術の素養のない抜刀斎であろうとも、サーヴァントに備わった治癒能力として再生が可能であった。無論、元々の貯蔵量の少なさと魔力ステータスの低さ、そして負った傷の深さからか、瀕死の重傷であることに変わりはないが。
失血により思考が鈍麻していた。視界が白み、朦朧として考えが纏まらない。しかし、抜刀斎はただ"生きる"のだという根源的な指針に基づいて、生存へと向けて体を動かしていた。
そこが、彼と斎藤の命運を分けた差であった。
斎藤一は一切の未練も願いも持ち合わせてはいなかった。この聖杯戦争に喚ばれたのはあくまで座の気まぐれと語り、当初より悪辣な輩の討伐のみを方針に掲げ、聖杯を破壊するというマスターの意向に否を示さなかった。
それは人生を全うした者としての潔さの表れであったが、同時に死者の生に縋らないという、生の欲求の薄さの裏返しでもあった。
だからこそ斎藤は、土壇場で相討ち必至の剣戟を演じることができたし、その果てに一時の勝利を得ることもできた。
それは人生を全うした者としての潔さの表れであったが、同時に死者の生に縋らないという、生の欲求の薄さの裏返しでもあった。
だからこそ斎藤は、土壇場で相討ち必至の剣戟を演じることができたし、その果てに一時の勝利を得ることもできた。
だが、それだけだ。
彼は決して捨て鉢ではなかったのだろう。命ある限り剣を振るい、できるだけ長く生存し悪・即・斬の志を貫こうともしたのだろう。だがそれは、決して生きたいと願っていたわけではないのだ。
彼は決して捨て鉢ではなかったのだろう。命ある限り剣を振るい、できるだけ長く生存し悪・即・斬の志を貫こうともしたのだろう。だがそれは、決して生きたいと願っていたわけではないのだ。
抜刀斎は違った。
彼はあの瞬間、誰よりも切実に"生きたい"と願った。生きて聖杯を掴み、焦がれてやまない願いを叶えるのだと、そのために生きるのだと願った。
例えそれが後世の逸話により捻じ曲げられたものであったとしても、それは彼の真であり、生への欲求であった。
彼はあの瞬間、誰よりも切実に"生きたい"と願った。生きて聖杯を掴み、焦がれてやまない願いを叶えるのだと、そのために生きるのだと願った。
例えそれが後世の逸話により捻じ曲げられたものであったとしても、それは彼の真であり、生への欲求であった。
生きたいと願った者。偽りの生を唾棄すべきと否定した者。
どちらが生き残るかなど、論ずるまでもないことであった。
どちらが生き残るかなど、論ずるまでもないことであった。
異界の残り香は消え果てた。
枯草と鉄錆の匂いはもうしない。
芳るは、ほのかに―――
【C-8/無人の街中/2日目・深夜】
【アサシン(緋村剣心)@るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-】
[状態]ダメージ(大)、疲労(大)、失血、魔力消費(大)
[装備]
[道具]なし
[思考・状況]
基本行動方針: 平和な時代を築く為にも聖杯を取る。
1. どこへ行った、斎藤……
[備考]
サーシェスが根城にしているホテルを把握しました。
C-8で発生した戦闘を一部目撃しました。ボッシュ及びブレードトゥースとガン・フォールの戦闘を垣間見ました。仲村ゆり、斉藤一、キリヤ・ケイジ、キルバーンの姿は見ていません。
マスターである神条紫杏と情報を共有しました。
仲村ゆり、音無結弦、加藤鳴海を認識しました。
斎藤一が死んだことに気付いていません。
[状態]ダメージ(大)、疲労(大)、失血、魔力消費(大)
[装備]
[道具]なし
[思考・状況]
基本行動方針: 平和な時代を築く為にも聖杯を取る。
1. どこへ行った、斎藤……
[備考]
サーシェスが根城にしているホテルを把握しました。
C-8で発生した戦闘を一部目撃しました。ボッシュ及びブレードトゥースとガン・フォールの戦闘を垣間見ました。仲村ゆり、斉藤一、キリヤ・ケイジ、キルバーンの姿は見ていません。
マスターである神条紫杏と情報を共有しました。
仲村ゆり、音無結弦、加藤鳴海を認識しました。
斎藤一が死んだことに気付いていません。
▼ ▼ ▼
この物語は、ここでお終いである。
主を守護せんとするしろがねは、二人の少女と共に舞台に関わることはなく。
雷電王はただ己が主命を果たすだけで。
南条光と仲村ゆりは、ただ一時その身を安寧に委ね。
緋村剣心と斎藤一はかつての決着をつけ。
死神はただ逃避し。
負の王たる球磨川禊は全てを台無しにして。
雷電王はただ己が主命を果たすだけで。
南条光と仲村ゆりは、ただ一時その身を安寧に委ね。
緋村剣心と斎藤一はかつての決着をつけ。
死神はただ逃避し。
負の王たる球磨川禊は全てを台無しにして。
ならば、最後の一人。
死神と雷電王の対峙から逃げ出し、そのまま消え去った少年は一体どうしたというのか。
死神と雷電王の対峙から逃げ出し、そのまま消え去った少年は一体どうしたというのか。
それは―――
………。
……。
…。
―――――――――――――。
赤色の空で。
月が、ひとりでに嗤っていた。
月が、ひとりでに嗤っていた。
異界の夜。
空には"ぬらり"と光沢を放つ月が瞬いて。
空には"ぬらり"と光沢を放つ月が瞬いて。
空には月があった。
空には星があった。
しかし、どちらも寓話的に歪んで。
空には星があった。
しかし、どちらも寓話的に歪んで。
惑星、恒星、衛星の輝きではない。
もっともっと禍々しいものだ。
もっともっと禍々しいものだ。
異界にて孤高なる月。
異界にて異形なる月。
異界にて異形なる月。
それはまるで眼球のように。
それはまるで相貌のように。
まるで、地上の人々を嘲笑うかのような。
それはまるで相貌のように。
まるで、地上の人々を嘲笑うかのような。
たったひとりで空に浮かび、孤独もなく。寂寥もなく。
あらゆるものを嗤うのか。
あらゆるものに慈悲の瞳を投げかけて。
あらゆるものに侮蔑の瞳を見せつけて。
あらゆるものを嗤うのか。
あらゆるものに慈悲の瞳を投げかけて。
あらゆるものに侮蔑の瞳を見せつけて。
月が嗤う。
月が嗤う。
虚空に浮かびて嘲笑う、黄金の月が―――
月が嗤う。
虚空に浮かびて嘲笑う、黄金の月が―――
「あやめ……あやめッ!」
その中を、音無結弦はただ懸命に駆けていた。
失ったものを取り戻すように、これ以上失わせないように。
失ったものを取り戻すように、これ以上失わせないように。
「あやめ、どこだ……くそっ」
―――異界が発生した瞬間、音無には何故か"それがあやめに起因するもの"であるということが分かった。
状況は分からない。しかし、彼女の身に何かがあったことだけは、分かった。
だから駆けていた。彼女を失うわけにはいかないから、失いたくなかったから。
状況は分からない。しかし、彼女の身に何かがあったことだけは、分かった。
だから駆けていた。彼女を失うわけにはいかないから、失いたくなかったから。
音無は駆け出し、赤い影に覆われた細い路地を曲がる。更に細い路地の向こうで、誰かの影が見えた。小柄な影、臙脂の色が見えたようにも思う。
病院は近い。音無は更に細い路地へと入る。大通りは駄目だった。直感ではあるが、あそこに行ってはいけないような気がするのだ。"大勢の誰かの気配がある"大通りには。
病院は近い。音無は更に細い路地へと入る。大通りは駄目だった。直感ではあるが、あそこに行ってはいけないような気がするのだ。"大勢の誰かの気配がある"大通りには。
「待て、待ってくれ……俺は……!」
影は路地の向こうで角へと消える。音無は追い、更に奥へと分け入る。影は更にその向こうの角へ、音無は追い縋り、更に昏い路地へ―――
「!?」
急な暗転に、音無は動転した。
闇が、辺りを包んでいた。今までのような夜の闇ではない。向こう側まで見通せるような、日毎現れるそれではない。
音無を包んでいるのは、一片の光もない、闇。
それでいて地平線の彼方までをも見渡せる、矛盾した闇だった。
闇が、辺りを包んでいた。今までのような夜の闇ではない。向こう側まで見通せるような、日毎現れるそれではない。
音無を包んでいるのは、一片の光もない、闇。
それでいて地平線の彼方までをも見渡せる、矛盾した闇だった。
闇。
静寂。
ただ、自分の荒い呼吸の音だけが、むなしく宙へと拡散した。
沈黙。
静寂。
…………。
……………………。
静寂。
ただ、自分の荒い呼吸の音だけが、むなしく宙へと拡散した。
沈黙。
静寂。
…………。
……………………。
ふと、気付いた。
人の姿に、音無は気付いた。
見ると、遠い向こうに、白い人型が立っている。
音無は、思わず声をあげた。
人の姿に、音無は気付いた。
見ると、遠い向こうに、白い人型が立っている。
音無は、思わず声をあげた。
「あやめ……」
果たして、本当にそうなのか。遠すぎてよく見えない。
白い人型は背を向け、歩み去っていた。
遠くへ、遠くへ。
闇から、闇へ。
徐々に離れていくその姿は、何故だか今にも消えていってしまいそうなほどに希薄だった。
今にも溶けて、消えてしまいそうだった。
酷く、胸騒ぎがした。
白い人型は背を向け、歩み去っていた。
遠くへ、遠くへ。
闇から、闇へ。
徐々に離れていくその姿は、何故だか今にも消えていってしまいそうなほどに希薄だった。
今にも溶けて、消えてしまいそうだった。
酷く、胸騒ぎがした。
「……あやめ!」
呼ぼうとしたが、声が掠れて言葉にならなかった。異常に喉が渇き、喉の奥が張り付いて言葉が出ない。喉は、ただ空気を嚥下して喘ぐことしかできない。
そうするうち、白い誰かは闇に呑まれ、消えてしまった。
その姿に酷い不安を感じ、一歩を踏み出した。
そうするうち、白い誰かは闇に呑まれ、消えてしまった。
その姿に酷い不安を感じ、一歩を踏み出した。
その時だった。
『こんにちは、ユヅル』
闇が、嗤った。
「ッ!?」
囁く声に音無は振り返る。
声はすぐ近くから聞こえた。まるで自分の背中から、耳元で囁かれたように。
声はすぐ近くから聞こえた。まるで自分の背中から、耳元で囁かれたように。
音無は、驚愕と共に振り返って。
その向こうにあるものを、見て。
その向こうにあるものを、見て。
―――あやめが、いた。
―――瞼閉じる彼女は、もう二度と動くことはなく。
―――瞼閉じる彼女は、もう二度と動くことはなく。
―――黒い道化師に、その体を抱かれていた。
音無は見た。瞼の先にあるもの。
一寸の先をも見通せぬ闇の中にあって、しかし地平の彼方まで見通せる矛盾を孕んだ視界の先を。
決して幻ではない。それは、確かに崩壊の中の現実だった。
一寸の先をも見通せぬ闇の中にあって、しかし地平の彼方まで見通せる矛盾を孕んだ視界の先を。
決して幻ではない。それは、確かに崩壊の中の現実だった。
―――ああ。
―――視界の中央で道化師が踊っている。
―――視界の中央で道化師が踊っている。
音無は現実の何たるかを知っていた。そして、視覚がもたらす情報を正確に認識していたはずだった。
しかし、それを音無は疑う。
それはありえない。
しかし、それを音無は疑う。
それはありえない。
闇の中で踊る影。
それはサーヴァントでも、まして人でもなかった。
黒色の道化師。囁きかける何者か。
それは、この街において音無の視界の端にいた。
それは、決して現実ではない幻影のはずだった。
諦めの証。
偽りの街にあって自分が諦めかけているのだと、音無自身に自覚させていた、狂った道化師。
それはサーヴァントでも、まして人でもなかった。
黒色の道化師。囁きかける何者か。
それは、この街において音無の視界の端にいた。
それは、決して現実ではない幻影のはずだった。
諦めの証。
偽りの街にあって自分が諦めかけているのだと、音無自身に自覚させていた、狂った道化師。
それが、こうして視界の真ん中にいて。
あやめを掴んで離さない。
あやめを掴んで離さない。
「お、まえ……は……」
彼は踊っていた。
片腕の中に、瞼閉じるあやめの体を抱いて。
ひときわ高い高い場所にある尖塔の先に立って、道化師は少女を捕え、小さな顎を掴み、滑らかに体を踊らせる。
片腕の中に、瞼閉じるあやめの体を抱いて。
ひときわ高い高い場所にある尖塔の先に立って、道化師は少女を捕え、小さな顎を掴み、滑らかに体を踊らせる。
―――異界による世界の崩壊と侵食で満たされた中で。
―――道化師だけが、その影響を受けずに。
―――道化師だけが、その影響を受けずに。
「お前は……なんだ……?」
知らず、声が漏れ出た。
無意識の声だった。それは、音無自身も自覚しないままに。
無意識の声だった。それは、音無自身も自覚しないままに。
「馬鹿な……そんなことあってたまるか。お前は、俺の……」
呆然と呟く。震える声で、今や消えゆく彼は、静かに呟いた。
「俺の、幻……幻のはずだ……」
『そうだね。でも、そうじゃない』
それは言葉。
耳へと届く声ではない。
耳へと届く声ではない。
崩壊と侵食がもたらす無音の世界に在って、道化師の言葉は確かに音無の耳に届いた。
嘲笑する声。"お前も諦めたのか"という声。
嘲笑する声。"お前も諦めたのか"という声。
『こんにちは、ユヅル』
『既に天使は失われた』
『だから、共に眠るといい』
『既に天使は失われた』
『だから、共に眠るといい』
『―――諦めるときだ』
瞬間。
視界が再び暗転した。
視界が再び暗転した。
世界が切り替わった。道化踊る赤色の闇から、元の書割じみた街の情景へ。
踊る道化師の姿は消え失せていた。
代わりに目の前にいたのは、白い人型。
踊る道化師の姿は消え失せていた。
代わりに目の前にいたのは、白い人型。
ああ、その姿は、まるで。
「かな、で……?」
それは、音無が求めてやまない姿だった。
もう一度見たいと思った顔だった。
もう一度聞きたいと思った声だった。
もう一度会いたいと思った人だった。
けれど、今はこうして異界の中で。
何か得体の知れない別のものとしか、認識できなくて仕方がない。
もう一度見たいと思った顔だった。
もう一度聞きたいと思った声だった。
もう一度会いたいと思った人だった。
けれど、今はこうして異界の中で。
何か得体の知れない別のものとしか、認識できなくて仕方がない。
『どうして』
問いかける声が、音無に届く。
表情は見えない。俯いたその顔は、暗くて表情が伺えない。
表情は見えない。俯いたその顔は、暗くて表情が伺えない。
『どうして』
声が届く。
答えられない。彼女は、何を、言っているのか。
答えられない。彼女は、何を、言っているのか。
音無は答えない。答えられず、ただ、その手を伸ばして―――
ばしゃり。
と、水音だけを残して、天使の姿は溶けてなくなった。
水が弾けて崩れるように、白い人型はその姿を散らせていた。
水が弾けて崩れるように、白い人型はその姿を散らせていた。
「あ、あ……」
音無は、ただそれを見つめていた。
今まで天使がいた空間を、見つめていた。
口から漏れ出るのは悲鳴だ。それは喪失から来る悲嘆か。
いいや違う、音無は歪んだ表情をして、そこに込められた感情は、恐怖。
今まで天使がいた空間を、見つめていた。
口から漏れ出るのは悲鳴だ。それは喪失から来る悲嘆か。
いいや違う、音無は歪んだ表情をして、そこに込められた感情は、恐怖。
「あ、ああ、あ――――ああああああああああああああああぁぁぁぁああああぁぁぁああぁぁああぁぁッ!?」
音無は空間の一点を見つめ、ただただ悲鳴を上げていた。
今まで天使がいた空間。今は誰もいない。水音と共に、弾けて消えた。
しかし何が見えるのか。音無はそこに視点を固定したまま、叫んだ。
音無の顔は、歪んでいた。
今まで天使がいた、今は何もない空間の地面から、まるで今そこに天使が立っているかのように人の形をした影が伸びていた。
赤い、赤い影。
そこに何がいるのか。
音無は何を観たのか。
今まで天使がいた空間。今は誰もいない。水音と共に、弾けて消えた。
しかし何が見えるのか。音無はそこに視点を固定したまま、叫んだ。
音無の顔は、歪んでいた。
今まで天使がいた、今は何もない空間の地面から、まるで今そこに天使が立っているかのように人の形をした影が伸びていた。
赤い、赤い影。
そこに何がいるのか。
音無は何を観たのか。
次の瞬間、吹き抜ける風と共に空間が鳴動し、赤に染まった異界の風景は一瞬にして"元の世界"へと戻っていた。
月が、空が、影が、草木が、瞬く間に元の色を取り戻した。風に持ち去られるように、異界の空気が失われた。
元の姿へ戻った世界は、何もなかったかのように、ただ無機質な静けさのみを湛えていた。
月が、空が、影が、草木が、瞬く間に元の色を取り戻した。風に持ち去られるように、異界の空気が失われた。
元の姿へ戻った世界は、何もなかったかのように、ただ無機質な静けさのみを湛えていた。
異界があったという痕跡は。音無結弦という少年がいたという証は。
最早どこにも残されていなかった。
最早どこにも残されていなかった。
【あやめ@missing 消滅】
【斎藤一@るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 消滅】
【音無結弦@Angel Beats! 消滅】
【斎藤一@るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 消滅】
【音無結弦@Angel Beats! 消滅】
※C-8の特定箇所を中心に同エリア内の一定範囲に異界が発生し、範囲内のNPCが全滅しました。現在は終息しています。
| BACK | NEXT | |
| 052:そしてあなたの果てるまで(前編) | 投下順 | 053:願い、今は届かなくても |
| 052:そしてあなたの果てるまで(前編) | 時系列順 | 053:願い、今は届かなくても |
| BACK | 登場キャラ | NEXT |
| 052:そしてあなたの果てるまで(前編) | 仲村ゆり | |
| セイバー(斎藤一) | GAME OVER | |
| 音無結弦 | ||
| アサシン(あやめ) | ||
| 本田未央 | 055:そして、彼らは手を取った | |
| しろがね(加藤鳴海) | ||
| アサシン(緋村剣心) | ||
| 前川みく | 055:そして、彼らは手を取った | |
| ルーザー(球磨川禊) | ||
| 南条光 | 060:その願いは冒涜 | |
| ライダー(ニコラ・テスラ) | ||
| アサシン(キルバーン・ピロロ) | 057:戦の真は千の信に顕現する | |
| 042:生贄の逆さ磔 | 天使 | 053:願い、今は届かなくても |